小谷野敦 著
2015年04月23日
この世には、読んでどんなに愉快でもつまらない本と、どうにも不愉快だが実におもしろい本がある。読むべきなのは当然後者で、本書はその典型。
『江藤淳と大江健三郎――戦後日本の政治と文学』(小谷野敦 著 筑摩書房)
不愉快なのに、華がある。昭和の或る時期に文字どおり肩を組み、併走し、やがて対立していった大物2人の軌跡を交互に、詳細に描いて、おもしろ過ぎる。読みだしたらとまらない。
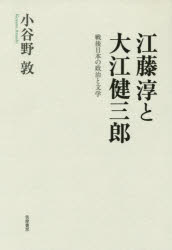 『江藤淳と大江健三郎――戦後日本の政治と文学』(小谷野敦 著 筑摩書房) 定価:本体2400円+税
『江藤淳と大江健三郎――戦後日本の政治と文学』(小谷野敦 著 筑摩書房) 定価:本体2400円+税一方(本人に取材を敢行した)大江は健在の大作家で、長年小説を愛読した著者の嗜好もあって、江藤ほど容赦ない叙述ではない。評価すべき作品に絶賛も惜しまない。
とはいえ、駄作は駄作と言明する厳正さは見事で、その政治的立場に対しても手きびしい。酒癖の悪さ、或る種の女性観への言及もぬかりない。
また、2人とも雌伏期間は短いとはいえ、それぞれの出生・年少時をじっくり辿り、成年後の志向を予想させる構成も、隙がない。
著者と世代が近い「個人的な体験」を少しだけつぶやくと、昔々、大江を文学の彼方を照らす《巨星》と仰ぎ見つつ、江藤を批評の海の《按針》として引き寄せたこともある。
本書を読むと、うかつに近づくといまだ焼き尽くされそうな《大江巨星》の成分に興奮する一方、《江藤按針》が指し示していた航路の危うさに、暗然とする。
ときに著者は、慶應英文科卒の江藤を、東大英文科卒の研究者として苛酷なまでに睨みつけ、我々をたじろがせるけれど、自らの留学体験と比べる細かい述懐には、苦笑してしまう(江藤は愛妻と2人で、著者は独身で渡航)。
こうしたボヤキのようなツッコミ(小谷野節?)をスパイスと感じるかどうかで、好みは分かれるかもしれない。
しかし賞賛すべきは、多彩で巧緻な引用、同時代の証言とともに描かれる緊張感である。
その手際は、既刊書に批判をもつ読者も、公正に評価すべきだろう。
2人の軌跡に加え、佐藤春夫・西脇順三郎をはじめとする三田系の大立者の相貌や、小林秀雄・埴谷雄高ほか文壇の大看板の発言など、いわば《役者が揃った昭和文学群像》も、これまでの著者の成果が存分に注ぎこまれ、意地悪くねっとり、じゃなく、輪郭鮮やかに活写され、痛快極まりない。
著者は、やがて権威へと駆け昇る江藤の初期の仕事は認めつつ、あまりに若くして評価され過ぎたのが「その後の歩みに災いした」と言う。
そして「家」へのただならぬ自意識をえぐり出す。どう好意的に見ても1.5流止まりの海軍将官だった祖父(江頭安太郎。海大主席卒、日露戦時の大本営参謀ながら中将で待命)と、一銀行員の実父。その格差が、尊大な家族中心史観、あるいは、擬似英国流階級意識をはぐくんだのかと思うと、冷えびえとする。
皮肉だなと思わせるのは、文学賞を数多く受賞し、国を憂い、政権党に親しみ、公的履歴を重ね、園遊会に招かれ、藝術院会員にも選ばれながら、ついに江藤は、国からの賞勲に縁がなかったのに、政権が煙たがる主張をやめない大江への評価は国を越え、ノーベル賞という国際的栄誉を得たこと。
当時、江藤は存命。かつての盟友への海外での喝采を、どう見ていたのか。何しろ江藤という「保守」言論人は、一族が皇族の姻戚に連なったこと(雅子妃は、江藤の従妹の長女)で、かえって「国家的褒章から遠ざけられることを危惧していた」(p.309)というのだ。
大江が描く「滅亡」「終末」が彼の「性的興奮」の所産とする結論には、異論もあるだろう。だが、ここに至るまでに繰り返し示される、家族の事情や現代史の闇に挑む深刻な主題と、度胆を抜く(ときに脱力感に陥る)ユーモアの兼備こそ、《成熟》を超えた巨星の証なのかとも思う。
そうしたユーモアが、(小説家と批評家との違いを超えて)江藤には欠けていたという裁定に、不気味な説得力がある。なぜなら、最晩年の悲劇が饒舌を排し《粛々と》綴られるから。かかる《喪失》への道もまた、江藤自らの指針が招き寄せたとすれば哀れとしか言いようがない。
一気に読んでしまったが、もう一度読みたい。繰り返すが、たとえ過去の著者の仕事に対し批判的な読者でも、本書の意義は素直に認めるべきだ。巻末には、江藤(1932-99)・大江(1935-)それぞれの充実した年譜もつく。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください