2014年01月06日
特定秘密保護法案なるものは、知れば知るほど危険な代物だ。だから法案を成立させようとする側は、まるで詳しく知られないうちに成立させてしまおうとしているかのようだ(11月26日、衆院を通過させた※)。
秘密は秘密を呼ぶ。自然に拡大する。Aという秘密事項があると、Aに隣接するAダッシュもまた秘密になる。そうするとAとAダッシュに関連したBという事項も、AとAダッシュの存在を隠すために秘密に指定され、同様にBダッシュも秘密となる。何ともおぞましい秘密の自己増殖が始まる。具体例をいくつか記そう。
かつて内閣府行政透明化検討チームのメンバーだったこともあり、市民の立場から行政情報などの情報公開を進めるNPO法人を立ち上げた三木由希子さんは、特定秘密保護法案の政策形成プロセスを知ることが必要だと考えて、それらの情報を公開するように請求した。
そもそもこの法案の骨格が、いつ、どこで、どのような人物たちによって、どのような話し合いを経てできあがってきたものなのか、その全部とは言わないまでも概要でさえわからなければ、市民はこの法案が本当に必要なのかどうか、その中身が妥当であるのかどうか検証することができない。
ところが返ってきたのは、例えば2009年4月21日にまとめられた「秘密保全法制の在り方に関する基本的な考え方について(案)」という政府検討チームの基本文書だと、延々と30数ページにわたって墨塗り(彼らの身内では「マスキング」と言うらしい)が施された文書というか「紙」だった。
まるで一昔前(僕がまだ高校生くらいだった頃)に、海外から輸入された雑誌のヘアヌード写真の局部が丹念に墨塗りされていたかのごとく、何から何まで精緻に隠されていたのである。何が秘密で何が秘密でないのかも秘密なのだ。
政府の秘密保全法制策定に関わる有識者会議とか検討チーム、作業グループに名前を連ねている人たちに言いたい。こんなことをやっていて、恥ずかしくないのでしょうか、と。先進欧米諸国でこんなことを報じればもの笑いの種になるような事態が、この2013年の日本ではまかり通っているのである。
欧米社会は国家の秘密が過剰に拡大していく弊害を身をもって体験している。だからこそ、今、行政情報の情報公開は世界的な潮流となっているのだ。
元ビートルズのジョン・レノンに対して、アメリカ連邦捜査局=FBIが、1971年の渡米以来、長期間にわたって監視や尾行、盗聴をしていたことは、今ではよく知られている。というのも、勇気ある学者らが情報公開法に基づいて、FBIの捜査資料の公開を求め続けた結果、その文書が公開されるにいたったからだ。すべてが開示されるまでには実に23年を要した。
カリフォルニア大学の歴史学教授ジョン・ウィナーはその中心人物だ。アメリカの先鋭的な報道番組「デモクラシー・ナウ!」(05年12月5日、写真)で放送されたウィナー教授のインタビューは、今の日本人にとっては実に有意義な内容だ。
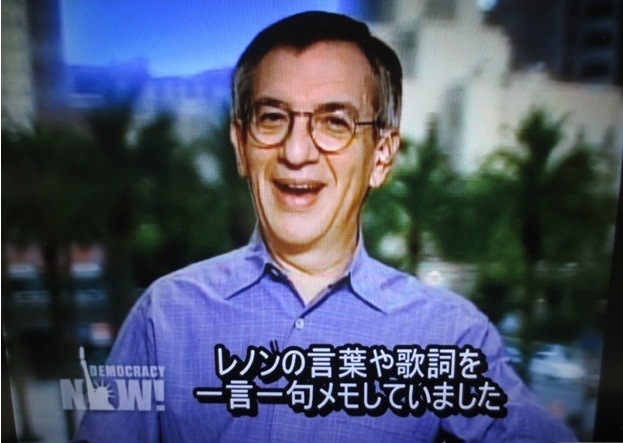
ウィナー教授は80年にジョン・レノンが射殺された直後から、530ページに及ぶレノンに関するFBI文書の情報開示を求めた。開示されたFBI文書の第2部(50~53ページ)にあるのだが、71年12月、ジョン・レノンがミシガン州で行った政治犯(ジョン・シンクレア。少量のマリファナ所持で懲役10年の刑を言い渡された)の釈放を求める集会で歌った曲の歌詞が、何と「機密」扱いになっていたのだという。1万5千人の集会参加者の前で堂々と歌った歌詞が、どうして「機密」になるのか? カントリー調のこの歌のサビの部分はこんな歌詞だ。
Gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, set him free.〈絶対に、絶対に、絶対に、絶対に、絶対に、絶対に、絶対に、彼を自由にしなきゃならないんだ〉
一番ロックっぽい箇所なのだけれど、この歌詞をFBIは何と「機密」に指定して、少なくとも12年は公開を拒んでいたのだ。今となっては笑い話だが、彼らが「機密」にしていたのは、FBIのエージェントがこそこそと集会に紛れ込んで情報収集活動をしていたこと自体が「うしろめたい」と思ったからなのかもしれない。国家の秘密指定行為とは常にそのような不条理さを含んでいる。
さて、僕らの国では特定秘密保護法案をめぐって、政府の森雅子秘密保護法担当大臣が、「西山事件の判例に匹敵するような行為は処罰される」と明言した。耳を疑うような発言である。
菅官房長官も、定例の記者会見で「私も捜査対象になる可能性はあるんでしょうか?」とのある記者の質問に対して、「通常の取材行為は処罰対象ではない。このことは外務省の機密漏えい事件の最高裁判決で明らかになっているから、報道または取材の自由に十分配慮しなければならないと規定するなかで、処罰対象にならないことを明らかにしている」と述べている。
つまり、外務省機密漏洩事件のケースは「通常の」取材行為ではないから処罰対象になると主張しているのだ。
毎日新聞の西山太吉記者が国家公務員法(守秘義務)違反で逮捕されたのは、72年4月のことだ。西山記者は、沖縄返還にまつわる日米両政府の密約(沖縄返還に絡んで本来はアメリカが支払うべき土地の原状回復費用400万ドルを日本側が肩代わりして支払うという密約)を紙面で暴露した。
政府は「そのような密約などない」と答弁していた。実際は肩代わりの密約があった。そのことは後年(2006年2月)、元外務省アメリカ局長の吉野文六氏が北海道新聞の取材に対して明言している。つまり国民を欺いていたのだ。端的に言えば、国家犯罪である。政府が国民にウソをついていた。このことがこの出来事の本質である。だが当時の事件のフレームは、そのようには形作られなかった。
東京地検特捜部は、西山記者が外務省の機密公電を入手した取材のプロセスの付随的な行為(西山氏が情報を入手した相手側と男女関係をもったこと)を問題化した。しかも人々の劣情を煽るような形で、その事実を拡大視して、この出来事は男女間の「情を通じた」スキャンダル事件に転化されたのである。
その結果、国家犯罪の方(密約を結んでいたこと、およびそのことを隠ぺいし国民を欺いたこと)を不問に付すことに成功した。これが外務省機密漏洩事件の本質である。
森担当大臣が言うように、仮に特定秘密保護法が当時あったとしたら、西山事件は処罰対象になる、ということは、政府が密約を他国との間で結び、それが国民を欺く性質の違法なものであっても、「特定秘密」に指定してしまえば、それを暴こうとしたものはすべて大罪となると言っていることに等しい。
また、その事実を内部告発しようとした公務員がいたら、その公務員も大罪に問われることになる。密約の存在を退官してから勇気をもって証言した吉野元局長も、守秘義務は終身だから大罪を犯したことになる。
何とも理不尽なことは、沖縄返還にまつわる密約の存在の事実は、その多くがアメリカ政府の情報公開された公文書からまず明らかになってきたことである。となれば今後も、日本で「特定秘密」とされたことが、情報公開制度が日本に比べてはるかに進んでいるアメリカ側から初めて明らかになるケースが生まれるであろうことも想像できる。一体何のための「特定秘密」創設なのだろうか。
現政権が国会に提出した特定秘密保護法案に対する私たちメディアの側の報道ぶりをみて強く感じるのは、何だかひどく腰が引けているな、という寂寥感だ。テレビ、新聞、出版、ネットといったメディアの違いにかかわらず、報道、表現に関わるすべての人々にとって、当局(authority)が「特定秘密」に恣意的に指定できるとなれば、メディアの報道活動が大きく制限されるばかりか、ひいては国民の「知る権利」が根本のところから侵害されることになる。
ところが、テレビ報道をはじめ、メディアの側からのこの法案に対する反応が鈍いのはどうしたことか。すべての局の報道ぶりをウォッチしているわけではないが、例えばNHKだと、同じ局のなかでも番組によって随分とスタンスが違っていることもある。「ニュース7」「クローズアップ現代」と「ニュースウォッチ9」ではかなり違う。
そうかと思うと、この法案が閣議決定された日でさえ、法案の中身の検証を報道番組でほとんど行っていないテレビ局があったり、とにかく反応が鈍いのである。なぜ、こんな大事な法案に対するテレビの関心、報道意欲が低いのか。思いつく限りの理由を列挙してみる。
(1)映像を重視するテレビメディアにとっては、法律案の検証という作業がそもそも苦手な分野であること。
(2)テレビ報道に関わっている人材の想像力が鈍化してきていること。歴史的な知識や現状に対する危機感がそもそも欠如していること。
(3)中国・北朝鮮の脅威というストーリーが、テレビ報道に関わる人材(特に若年層)に根深く刷り込まれていること。
(4)メディア間、系列ネットワーク間の横断的な連携、協力関係が希薄になってきていること。個人よりも組織を重視する傾向がますます強まっていること。
(5)権力への迎合姿勢が強くなってきていること。そうすることが営利を追求する企業メディアの生き残りや組織人としての自己の保身に都合がよいこと。
どれもこれも、指摘してしまえば元も子もないようなことがらである。
(1)については、所詮テレビの力は映像次第だという誤ったメディア観に拠っている。むしろ抽象的なものを可視化できることがテレビの力なのである。
(2)については、特に歴史的な事実について、とりわけ近過去についての、メディアに関わる人材の知識・伝承が欠如している。外務省機密漏洩事件をそもそも知らない記者がいたりする。日本の現代史において情報統制がどのように行われたのかについての知識がない。海外で現在進行形の事象と特定秘密保護法案の関係をつなげられない。例えば、ウィキリークスやエドワード・スノーデン氏のケースと同法案が密接に通底していることがらであるということに想像力が及ばない。
(3)については一部の同法案支持を標榜するメディアの論拠とさえなっている点だ。11年4月に情報公開法改正案を国会に上程していた民主党政権の進路が、真逆に転換していくきっかけは、10年11月のいわゆる尖閣ビデオ流出問題だったことは実に象徴的である。あの出来事を起点として、民主党自体が情報を隠す側に回っていったのだから。「中国の脅威」論は情報公開の流れを変えた。
(4)は、組織vs個人という古くからのテーマだが、メディアの危機に対するメディア間の連帯や協調が極端になくなってきていることは確かだ。
問題は(5)だ。権力を監視するウォッチドッグ(監視犬)としての機能がこれ以上低下すると、権力にとっての「愛玩犬」だらけのメディア状況が出現する。今、メガ与党の強大な権力を前にして、テレビのジャーナリズムとしての働きの覚悟が問われているという現状認識は、おそらく間違っていない。
秘密の多い社会は息苦しい非民主的な社会である。かつてのソ連や中国、北朝鮮には秘密が多い(多かった)。
旧ソ連の有名なアネクドートがある。ウォッカでしたたか酔った男がひとり夜道で「ブレジネフの大馬鹿野郎!」と叫んだところ、すぐさま公安警察官たちが現れて男を取り押さえた。男が「何だ、いったい俺に何の罪があるんだ!」と抗議すると、警官らが「国家機密漏洩罪だ」と答えたという。
笑うに笑えないアネクドートがこれからの日本で生まれないことを切に願う。
◇
金平茂紀(かねひら・しげのり)
TBSテレビ執行役員(報道局担当)。
1953年北海道生まれ。77年TBS入社。モスクワ支局長、「筑紫哲也NEWS23」編集長、報道局長、アメリカ総局長などを経て2010年9月から現職。著書に『テレビニュースは終わらない』『沖縄ワジワジー通信』など。
※本論考は朝日新聞の専門誌『Journalism』12月号(11月26日校了)から収録しています。同号の特集は「国による情報統制が復活しようとしている 国家・報道・自由」です
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください