星野智幸 著
2018年02月28日
“短篇集”ではなく“小説集”と見出しに書いた。
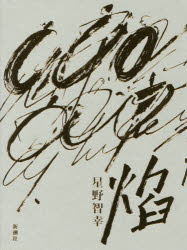 『焔』(星野智幸 著 新潮社) 定価:本体1600円+税
『焔』(星野智幸 著 新潮社) 定価:本体1600円+税あたかも幕間のナレーションのように流れる「しくみ」は、火を囲んで座っている語り手たちが、時期が到来すると「自らの物語」を語り始め、それが終わると闇に消えていく、というものだが、その「しくみ」自体が置かれた時空は、未来とも過去とも、また現在ともとれる。
いずれにしてもそこに確としてあるリアリティーは、たとえばふいに訪れる次のような文章によって保証されている。
〈……けれど、目を背けることはもうできないのだった。目を背けて、何も語らないでいれば、生き残り続けるのだ。知らないことにして、覆い隠すような物語を呟いたところで、ここを去ることはできない。ここを出て行くことができるのは、自分だけなのだ。自分になれない者には、去るべき自分もいないから〉
おそらくこの文章は、どんな文脈に置かれようとも、たちまち読み手にそのリアルを伝えてくるにちがいない。
それがシンクロニシティというものなのだろう。ここにあるどの物語も、たとえそれがどれほど荒唐無稽に思えても、どこかに「いま、ここ」でしかありえないリアルを備えている。
たとえば「ピンク」。猛暑のなかクルクル体を回す行為にのめり込んでいく女の子が、後半3分の1で、1行につき数年分の時間が流れるというめくるめく物語のなかで、徴兵され破滅していくさまは、もはや冗談ではなくすぐそこにある未来なのだ。
または「木星」の主人公・丸子の周囲に対する違和感。
〈魂を売り渡した者は、魂を自分のもとにとどめている人のことを、「あいつは変わってしまった」と非難する。動いているのは電車のほうなのに、ホームに残っている側こそが離れていっているのだ、と主張する〉
このところ、久しぶりに会った昔の同級生などと飲んだりしていると、しばしば訪れる既視感である。
そして「クエルボ」と妻に渾名されている初老の男は、ハンガーを拾ってきて巣を作ってしまう都会のカラスよろしく、自らも鉄塔に登ってハンガーで巣を作るという奇行に走るのだが、そのクエルボは、もしかしたら今朝乗ってきた通勤電車で向かいに座っていた彼かもしれないのだ。
「マジックリアリズム」というのは、日常と非日常の間の皮膜が溶けて無くなるような感覚をもたらす技巧をいうはずである。けれどもわれわれが生きているのは、もはやその前提となる「皮膜」さえもなくなってしまった世界なのではないか。
そう思わせるのは、まさに「星野マジック」としか言いようのない作者の手腕であり、またその作者によって切り取られた「いま、ここ」の過酷さに違いない。
実はこの本を読みながら並行して野間易通氏の『実録・レイシストをしばき隊』(河出書房新社)を読んでいた。この5年、たったの5年である。その間にわれわれの考えていた「人間」という存在の輪郭が、かくも変わろうとは! ポストモダニズムがもたらした「方向を問わない等価性」が、ネット空間が生んだ「遠慮ない至近距離」と化合すれば、かくも醜く人間の〈憎悪〉を増幅するのだとは、誰もが想像だにできなかったに違いない。
その点で、まさに生きている現実が「マジックリアリズム」であると実感した次第。これもまたシンクロニシティというものだろうか。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
*三省堂書店×WEBRONZA 「神保町の匠」とは?
年間8万点近く出る新刊のうち何を読めばいいのか。日々、本の街・神保町に出没し、会えば侃侃諤諤、飲めば喧々囂々。実際に本をつくり、書き、読んできた「匠」たちが、本文のみならず、装幀、まえがき、あとがきから、図版の入れ方、小見出しのつけ方までをチェック。面白い本、タメになる本、感動させる本、考えさせる本を毎週2冊紹介します。目利きがイチオシで推薦し、料理する、鮮度抜群の読書案内。
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください