浜矩子
2012年05月19日
「ユーロが世界経済を消滅させる日」。このタイトルの拙著がある。2010年3月の刊行だった。あれから2年あまりが経過した今、いよいよその日が迫っている感が深まる。
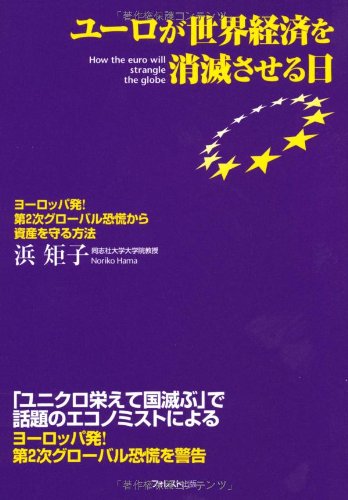
こんな風にいえば、いかにも我田引水丸出しの雰囲気だ。その魂胆が無いわけでもない。だが、そもそも、このタイトルは筆者ではなくてご担当頂いた編集者の考案になるものだ。その慧眼にこそ、喝采である。全くもって、グローバル経済は今、ユーロに引きずられて消滅という名の竜巻に呑みこまれそうになっている。
今、一番怖いのが「感染」という言葉だ。ユーロ危機に、誰がどこでどこまで感染するか。感染経路はどうなり、行く先々でどのような症状を発症することになるのか。これが極めて見えにくい。
そもそも、ユーロ病そのものが、今後どのような経過をたどるかが解らない。ギリシャがついにデフォルトに陥るのか。その場合、ギリシャはユーロ圏に止まるのか、止まらないのか。あるいは、デフォルトはしないがユーロ圏からは出て行くのか。はたまた、ユーロ圏そのものの崩壊か。ユーロ圏内で次に病に倒れるのはスペインなのか、ポルトガルなのか、イタリアなのか。予期せざる別の誰かであるのか。ドイツは、どこまで当面の患者たちへの輸血役を果たし続ける覚悟があるか。
筋書が読めないまま、ユーロ危機の感染力が日増しに高まりつつあるようにみる。筋書が読めないからこそ、そうなる。感染を防ごうにも、次にどうなるかが解らないのであるから、どうしようもない。こういう時にはどうするか。何はともあれ、考えられるあらゆる面での最悪のシナリオを想定して、みずからの耐性を診断することだ。今時はやりのストレス・テストである。
日本の場合、ストレス・テストの中に組み込むべき要因は何か。大括りなところからいけば、まずは為替レートの行方がある。ユーロ暴落・円激騰は当然の想定だ。次に実体経済への影響だ。ユーロ圏が事実上の機能マヒ状態に陥ることで、日本にどこまでデフレ効果が及ぶか。それをマクロ的な観点からざっくりとらえる必要がある。
この辺りまでは、さほど複雑な話ではない。ポイントは、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください