労働分配率が安定しているという「自明のテーゼ」に正面から挑戦
2014年05月22日
43歳の無名のフランス人経済学者トマ・ピケティ(Thomas Piketty) が、アメリカで一大センセーションを巻き起こしている。
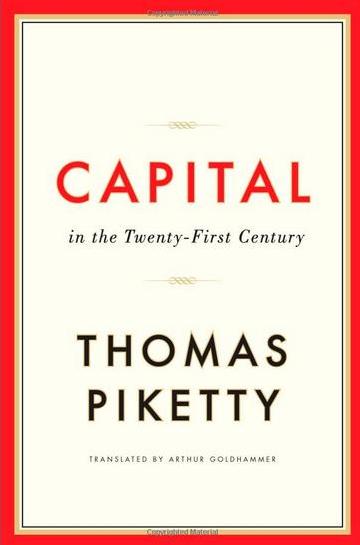 Amazon.co.jpより
Amazon.co.jpよりこの3月に、この人の著書の英語版が出版され(”Capital in the Twenty-First Century”)、これをポール・クルーグマンやジョセフ・スティグリッツ、さらには経済成長論の大御所、ロバート・ソローといったノーベル賞クラスの著名な経済学者がこぞって絶賛して、今や大ベストセラーとなっている。辛辣な批評で知られるクルーグマンが、「彼の知性が羨ましい」とまで書いたのだから、大騒ぎになるのも当然かもしれない。
なお、この3人の経済学者は政治的には明らかに民主党系のリベラル派だが、共和党系の経済学者、例えばグレゴリー・マンキューやケネス・ロゴフ(ともにハーバード大学教授)もこの本の経済分析を高く評価している。
何がそんなに凄いのか? ここでは、主にポール・クルーグマンの書評に依拠しながら説明したい。
(“Why We’re in a New Gilded Age” by Paul Krugman, The New York Review of Books, May 8, 2014)
http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/may/08/thomas-piketty-new-gilded-age/
現代の経済学で、ほとんどの学者が自明であると考えていることの一つに「労働分配率が長期的に安定している」というテーゼがある。例えば、ある国の経済活動が生む全付加価値(GDPとして計測される)に対する生産要素ごと、つまり、資本と労働の各々への分配率を見ると、殆どの国では「資本の取り分が1/3、労働の取り分が2/3、となっておりこれが長期にわたり安定している」というものだ。
事実、GDP統計が整備されて以来、この労働と資本の間の2対1という付加価値の分配率は安定して観測されてきたように見える。但し、GDP統計が整備されて多くの先進国で同じ基準の統計が作られるようになったのは第二次世界大戦のあとである。つまり、この自明であるとみなされて来たテーゼの観測期間は、せいぜい20世紀後半以降ということになる。
ピケティのこの本が凄いのは、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください