ロボットや人口知能で進む二極化、「大格差」社会は到来するのか
2015年02月03日
私は、前稿「トマ・ピケティ『21世紀の資本』をどう読むか?」(1月1日)で、このピケティの大著が、資本の蓄積とこれがもたらす格差については非常に詳しく説明しているものの、労働者間の労働報酬の格差については、スーパー経営者の報酬の天井知らずの上昇という現象を除いては、あまり語っていない(強調していない)ことを指摘した。
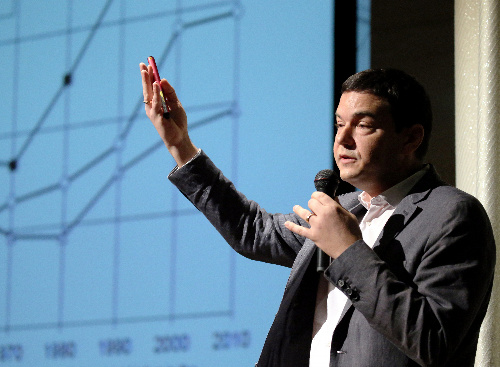 講演するトマ・ピケティ氏=2015年1月25日、東京・有楽町
講演するトマ・ピケティ氏=2015年1月25日、東京・有楽町先進国における労働者間の賃金格差を説明するのに、「技術と教育の競争」ということが良く言われる。つまり、十分な教育を受け技術革新について行ける労働者と、これに取り残される労働者では限界生産性が大きく異なり、これが大きな賃金格差となるという仮説である。
実際、アメリカでは、大学進学率が頭打ちになった1980年ごろから大卒労働者と高卒労働者の賃金格差が大きく拡大したという実証研究がある。この頃から大学の学費が大きく上昇して、多くの人が必要な教育を受けられなくなった。このために、労働市場で需給のミスマッチが起きて、超過需要の発生しているセクターで賃金が高騰し、需要の少ないセクターの賃金が下落したという説明である。
「長い目で見れば、労働に関する格差を是正する最良の方法が教育への投資であるのは間違いない。」「賃金格差が小さいスカンジナビア諸国でのあらゆる証拠を見ると、賃金格差の小ささは主に教育システムが比較的平等で包括的であるおかげが大きいようだ。」(『21世紀の資本』日本語版319頁)
ピケティも、教育の機会均等が労働所得の格差是正のための最も重要なファクターであることには異論がないようだ。だが、ピケティにとって最も目を引く労働所得の格差は、アングロサクソン諸国で顕著な、トップ1%の人々の所得シェアである。例えば、アメリカのトップ1%の労働所得のシェアは、1980年の8%から2010年には18%に上昇している。同じ期間にイギリスでは6%から15%に上昇している。
(同328頁、図9-2)
ピケティは「スーパー経営者の所得シェアが10%も高まってしまえば、その他の労働者の所得格差の問題を強調してもしょうがない」と考えたのかも知れない。
更にピケティの主要な関心は、労働所得の格差から離れて、資本所有の格差に向かう。資本の収益率(r)>経済成長率(g)という関係式が、資本主義に持続不可能な富の格差を生み出す、という「ピケティ・テーゼ」は今やあまりにも有名である。
最近、ピケティは、彼が参加した討論会で(1月3日、ボストンにおける、アメリカ経済学会の『21世紀の資本』を巡るパネル・ディスカッション)、「今後予想されるロボットや人工知能のような技術の著しい発達によって、資本と労働の力関係が資本の側に圧倒的に有利になっていく」と発言している。
ピケティの将来予測は、現在のトレンドの延長というだけではなく、技術の変化も視野に入れた考えのようだ。
ロボットや人工知能が職場に大量に投入された未来の世界で、我々の仕事はどう変わって行くのだろうか?
この問題に興味深い見方を示しているのが、タイラー・コーエン『大格差』(NTT出版、2014年)である。コーエンはリバタリアンの経済学者で、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください