バラ色ではない人民主権国家、個人は国家に従属する〈朝日カル連携講座〉
2015年06月19日
WEBRONZAは朝日カルチャーセンターの協力を得て、同センターでの連携講座にご契約者のみなさんを招待しています。それぞれの連携講座の内容は連載記事としてWEBRONZAでご紹介します。今回は慶応大学の坂本達哉教授による「民主主義か資本主義か」です。フランスの経済学者ピケティ氏が『21世紀の資本』で現代の資本主義社会における格差問題を分析し、注目を集めました。しかし、この問題は、古くて新しいテーマだと坂本教授は解説します。ルソーからロールズまで、6人の思想家の考えをたどりながら、改めて問題の本質を見つめます。2015年3月24日、東京・新宿の朝日カルチャーセンター新宿教室での講座です。
坂本達哉(さかもと・たつや)1955年東京生まれ。1979年慶應義塾大学経済学部卒業。同大学院経済学研究科をへて、1989年慶應義塾大学経済学部助教授。1996年同教授。博士(経済学)。主要著作に『ヒュームの文明社会』(創文社、1995年)、『ヒューム希望の懐疑主義』(慶應義塾大学出版会、2011年)、『社会思想の歴史』(名古屋大学出版会、2014年)がある。
....................................
今日は「民主主義か資本主義か」という、やや大げさなタイトルですが、私が最も言いたいことは、この問題はすでに少なくとも200年以上前から、ヨーロッパにおいてはもう散々論じられてきた問題なのだということです。つまり、スミス、ルソーから、最近、『21世紀の資本』で話題を集めたピケティまで、実は繰り返し論じられてきているのです。
 坂本達哉教授
坂本達哉教授この本に書かれていることというのは、私の見るところ、実は、もうスミスやルソーの時代から散々論じられてきていることだというようにしか、私には読めません。彼はもともと数理経済学者で、数学が天才的にできる人だそうです。この格差問題や民主主義と資本主義などというテーマが、数理経済学の分野では比較的珍しいというか、新しいというような側面があるようです。私は数理経済学は素人ですが、社会思想の歴史をやっている立場からすると、「ピケティさん、あなたのやっていることはもう200年前からみんなが論じていることなんですよ」と言いたいわけです。
ピケティという人は、例えばマルクスの『資本論』というのをほとんどまったく読んだことがないとインタビューに答えています。だから私はそれは逆に信頼できると思っているんですね。つまりマルクスとは関係ないところで、こういう問題を独自に展開しているということですね。しかし、やっぱり私から見れば、マルクスも含めて、さらにさかのぼって250年前、300年前の思想家の知恵を借りない手はないだろうと、こういう問題を考えていくときに思っているんです。
これは決してピケティを批判しているわけではありません。彼の功績は専門的なところではもちろん高く評価されております。これだけこういう格差の問題を世界的に注目の的にしたのは、大変な功績であるということは認めないわけにはいきません。そのうえで、私は、ルソーとスミス、マルクスとミル、ケインズとロールズ、この3組の人たちが、いずれもいわば「ピケティ問題」といいますか、つまり資本主義における格差の問題を、そもそも200年前から議論していたんだということを、ぜひ、皆さんにお伝えしたいと考えているのです。
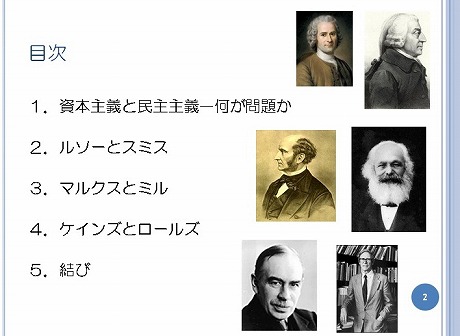 講座で使われたパワーポイントから
講座で使われたパワーポイントから上はルソーとスミスですね。真ん中がミルとマルクス、一番下がケインズとロールズで、ルソーとスミスの時代はまだ写真がございません。だからエッチングとか肖像画なんですね。ところがミルとマルクスでは、これ、写真です。こういうところにも時代の変化がよく分かると思います。簡単に言えば上の2人は18世紀の人、真ん中の2人は19世紀の人、一番下の2人は20世紀の人で、ロールズに至ってはつい最近、21世紀まで生きておりました。
さて何が問題なのかということで、簡単にまずポイントをまとめてみましょう。
基本的には1989年から1991年にかけての、いわゆるベルリンの壁の崩壊から東ヨーロッパ、ソビエト連邦の崩壊。これが基本的に、依然として決定的な事実であるというのが私の見方です。冷戦体制の崩壊とよく言いますが、より正確に言えば、社会主義体制の崩壊ですね。
 熱心に耳を傾ける参加者ら
熱心に耳を傾ける参加者ら当時、社会主義と資本主義、どちらが勝ったのかというような、勝ち負けみたいな話がずいぶんマスコミでもにぎわされましたけど、そういう勝ち負けの問題ではありません。やはり社会主義体制、少なくともソ連や東ヨーロッパがそれまで70年、80年にわたって築き上げてきたものが、一挙にガラガラと音を立てて崩れた。しかもそれは資本主義諸国からの干渉などよって崩れたのではなく、本当に内部的に自らの矛盾によって崩壊しました。
その最後、崩壊する直前にはレーガン政権とかアメリカの政権は、食料援助などをして必死にゴルバチョフを助けようとしました。それらもむなしく自ら崩壊していったということです。これは無血革命であって、1滴の血も流さずにベルリンの壁が崩壊し、東ヨーロッパが雪崩を打って崩れ、最後、ソ連が崩壊したのです。これは驚くべきことで、当時は、もう本当に信じられないことでしたね。しかし、これは紛れもない現実であります。
それを受けて、今日は詳しくはお話しする時間はありませんが、アメリカの学者、日系米人のフランシス・フクヤマという人が、もうこれで歴史は終わったと言いました。ロシア革命からソビエト連邦崩壊までの70年、80年というのは、いわば歴史の一脱線部分だった、脱線だったんだ、と。これは本来の、要するに市場経済と自由民主主義という、人間社会にとって唯一の選択肢に戻ったんだ、と。それとはまったく別の社会、理想社会があり得るかのように70年、80年、人類は思わされてきたが、これはソ連や東欧の人々だけではなく、何より西側世界、資本主義世界の特に知識人がそう思わされてきていたが、それはすべて幻想だったんだということを言ったんです。
これに対し、ハンティントンというハーバードの政治学の先生は、別の見方を示します。確かにそれはその通りだが、だからといってこれから市場経済と自由民主主義の、ばら色の世界が開けるかのように思うのは大間違いだ。まさに冷戦構造によって覆い隠されていた人類社会の矛盾が、冷戦構造が崩壊したことによって一気に吹き出てくるんだ、と。これを彼は諸文明の衝突。「諸」というのがポイントで、要するにキリスト教文明とイスラム文明と儒教文明ですね、中国とイスラム諸国とヨーロッパ、アメリカ、この3つの陣営がまさに正面から、宗教という最高のイデオロギーを軸に対立する時代が来るのだ、との展望を語りました。そのイデオロギー的対立を軸に、また実際の戦争も起こるんだということを予言しているのです。
現在の世界の情勢を見てみると、フクヤマよりはむしろハンティントンの方が当たっているのではないかと思わせるような大変厳しい現実があります。我々は日夜、世界各地からの報道でそれらを知らされています。ただ、やっぱり諸文明の衝突で終わっていたのでは我々、救いがない。この状況を、どういうふうに突破するか、この人類社会にとっての危機をどうやって突破するかということを、やはり考えないといけない。それが今日のお話のきっかけです。
社会主義体制、いわゆるソ連、東欧型の社会主義が崩壊した後、残った資本主義体制というのはどういうものであったのか。それは実は社会民主主義なんですね。社会民主主義というのはソーシャルデモクラシーと言います。1960年代ぐらいはイギリスとかフランスとかで普通にそれはソーシャリズムといわれていたのです。つまり社会主義という、ソーシャリズムという言葉は、イギリスとかフランスとかでは社会民主主義のことを言うのです。
ソ連や東欧の社会主義のことはソーシャリズムとは呼ばず、コミュニズム、共産主義といいます。あるいはもっとよく使われたのは、コレクティビズム、集産主義と言いますが、そういう名前で呼ばれていたんです。自分たちの方こそが社会主義の本当の姿であって、それはつまり市場経済を捨て去らないんだけれども、それを民主主義的にコントロールして、ゆりかごから墓場までの福祉国家をつくるんだということですね。これは修正資本主義という言葉で長く呼ばれたこともあります。
ですから重要なことは、ソ連、東欧の社会主義は崩壊しましたが、現実には資本主義体制の中での社会民主主義が残っていたということです。それが危機にひんしたのが、この1980年代以降です。具体的にはイギリスのサッチャー首相、アメリカのレーガン大統領、日本の、あまり同列に並べるのは適切かどうか分かりませんが、中曽根首相ですね。こういう人々をシンボルにする、いわゆるネオリベラリズム、新自由主義の政策が採られてきました。
この新自由主義というのは結局、福祉国家というのが膨大な財政赤字を生み出すということに対して、富裕層が起こした反乱と言えます。結局、福祉国家というのは、所得再分配の政策です。分かりやすく言うと金持ちから多くの税金を取って、相対的に貧しい人々に分け与えるわけです。悪い言葉を使えば、ばらまくわけです。例えばイギリスなどは福祉国家のピークのころ、労働党政権が一番強かったときには、82%の最高税率が所得税にかかっていた時代がありました。
これをサッチャー首相は壊したかった。サッチャー首相自身は決して豊かな生まれではない、むしろ貧しい出身、質素な出身ですが、そういうことをやっていたら社会がモラルハザードを起こすと考えました。一生懸命働けば働くほど税金が多くなる、働くことが何か罪悪であるかのように見なされる社会というのは、決していい社会ではないと。それはそれ自体、傾聴に値する考えかもしれません。そういう考えに基づいて、しかし現実的には80%以上の高税率に耐えかねた富裕層の利害を代表しながら、サッチャー政権というのが出てきたわけです。
同じような流れの中にあったのが米国のレーガン大統領とか日本の中曽根首相です。みんな形は違いますけど、特に日本の場合は非常に特殊な要因があり、これは一緒に論じるのは抵抗がありますが、いわゆる新自由主義というものが台頭してきて、現在もなお基本的にはその路線は維持されているということです。ただイギリスでもサッチャー首相の最良の継承者は、労働党のブレア首相だと言われているように、新自由主義になっても実は福祉国家の路線というのは基本的に捨てられてはいないということです。
イギリスでは5月に総選挙が予定されています。その一番の争点はNHSという、ナショナル・ヘルス・サービス、日本のまさに健康保険制度、国民皆保険制度ですね。こういう制度を抜本的に見直すことが、今度のイギリスの5月の総選挙の第1争点になっています。保守党はそれをできるだけ軽減して民営化させようとして、労働党はそれを絶対守るといっているわけです。
ですから依然として、新自由主義が台頭してはいますが、福祉国家は完全には壊れていないわけです。それをどうするかというのが今の最大の問題です。日本についても、先進国の中でも超高齢社会ですから、健康保険、社会保障、年金、この3つの福祉国家の基本的な柱をどうするかというのが大問題になっているということは、もう皆さん、よくご承知の通りです。
ただ、欧米では、特にヨーロッパではその論争は日本とは比較にならないほど厳しく激しいものです。日本では小泉さんが出てきて新自由主義的な政策を取ったといっても、サッチャー首相がやったことと比べたら本当に生ぬるい。中途半端な新自由主義で、あれを新自由主義なんてとても呼べないわけですね。それだけでも日本では格差が増えた、小泉さんの政策でこれだけ格差が広がったと野党はいっているわけですけど、それは本当にまだまだ周回遅れの格差問題でしかないということです。
ピケティが問題にしたのは、まさにヨーロッパやアメリカの格差です。特に彼の問題にしたのはアメリカですが、最先端の格差問題だと。しかし、そういう問題こそ、まさに200年前、300年前から実は思想家たちによって論じられてきたんだということになります。
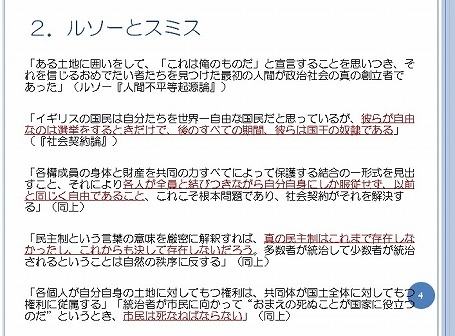 同。ルソーの引用
同。ルソーの引用思想家たちの説明については、ここに用意しました引用を中心に見ていきたいと思っています。
ルソーというのはもうご説明するまでもない、フランスの思想家というよりは、厳密にはスイス、ジュネーブの生まれの思想家です。フランスに渡って大活躍しました。特に『社会契約論』という書物が、世界中で読まれました。人類の中で最も読まれた本が三つあるという話があるらしいんのですが、その3冊というのは、『聖書』と『社会契約論』、そしてマルクスの『共産党宣言』だと言われています。
事実かどうかは分かりません。ただ、そんなことをいわれるぐらい『社会契約論』は読まれたということです。それは、フランス革命の導火線にもなり、アメリカ植民地の独立の導火線にもなり、そして日本でいえば中江兆民によって翻訳されて、明治維新、特に自由民権運動なんかの支えになっています。そのようなルソーですから、いわば民主主義思想の父であるというふうに言って、それほどの間違いはないと思います。
しかし、ルソーが言っている民主主義というのは、我々が普通に民主主義という言葉を使っているそれとは、まったく違うものだということは確認しなければなりません。当時はまだ資本主義という言葉はありません。文明社会といわれていました。ただ、資本主義のさまざまな要素がすでにイギリスではかなりはっきりと出ていました。産業革命以前ではありますが、資本主義に直接先行する段階に来ていたのです。
一方、フランスはブルボン王朝の絶対王制の時代、封建社会でしたので、資本主義社会とはとてもいえません。しかし、それでも商業活動、経済活動、投機などは、たくさんなされていました。商人や裕福な人々が金もうけにうつつを抜かしていることは、もうフランスでも行われていたのです。フランスではそこに封建社会の身分制が乗っかるので、貧富の格差は大変なものだったんですね。
ルソーは自由、平等の共和国であるジュネーブからフランスに来ました。自分の祖国ではまったくの自由、平等、みんなが独立生産者で、みんなが選挙権を持って、毎週のように広場に集まって政治決定をしています。いわゆる直接民主主義といわれる国からフランスに来たわけですが、そうすると、貧富の格差が激しいフランスはもう別世界のようです。この世の地獄のような光景だというふうにルソーは感じたのです。
文明といわれながら、こんな野蛮な社会はどうして生まれてきたか――。ルソーは基本的に私有財産制度が諸悪の根源だと言うわけです。特に土地の所有というのは問題だということです。「ある土地に囲いをして、これは俺のものだと宣言することを思いついて、それを信じるおめでたい人を見つけた最初の人が、政治社会の真の設立者」だと。
それまでは土地というのは共有であって、狩猟、採集、牧畜という、移動生活をしているわけです。ところが農業という段階に入ったときに、農業は移動していては農業ができませんから、どうしても定住しなきゃいけない。定住するだけじゃなくて、かなりの土地を私有化しなければならない。私有した者がたくさんの労働力を支配して、畑を耕させたり、種をまかせたりしているわけです。ですから土地所有、農業、そして政治的支配というのが、ルソーにおいてはまさに三位一体なのです。つまり私有財産制度の確立と政治的支配の確立、これが同じことだということをルソーは言っているわけです。
こういう考え方というのはマルクスに似ています。ですから、ルソーとマルクスを非常に重ねて見る見方というのは、十分に理由のあることです。ただ、ルソーはある意味ではマルクスよりももっと徹底して、その土地所有というものを攻撃しているところに特徴があります。それは、当時のフランスの貴族、王侯貴族というのは基本的に大土地所有者ですから、それを攻撃するという意味がありました。
では、どうすればいいのか。そのときに当時の啓蒙思想家たちが一番のモデルにしたのがイギリスです。
イギリスはもう当時、17世紀の終わりに名誉革命という革命をしまして、いわゆる立憲君主制の国になっていました。現代のイギリスは原形は、すでにその時代にはできていたのです。国民の自由と権利が基本的に守られており、国民の代表者である国会議員が議会で法律をつくる、国王はいますけれども、あくまでも議会のつくった法律にほとんど拘束される。自由にできるのは王族の結婚ぐらいという、そういう現在と同じような体制が、1688年という大昔にもうできていました。
ヨーロッパで最も自由な国です。もちろんジュネーブとかオランダとか、規模の小さい自由な共和国はあります。しかし、大国で君主制の国でこれだけの自由が実現している国というのは、イギリスしかないというふうに思われていたんです。ところがルソーはそれを、有名な言葉ですが、「イギリスの国民は自分たちを世界一自由な国民だと思っているが、彼らが自由なのは選挙をするときだけで、あとのすべての時間、彼らは国王の奴隷なのだ」という意味の言葉を、『社会契約論』で述べています。
つまり、いわゆる間接民主制や議会制民主主義といわれるもの、あるいは代議制民主主義といわれるものを、彼は痛烈に皮肉っているわけです。これは私たちにとっても人ごとではありませんね。現代の日本でも数年に1度は国政選挙があります。その時は1票を投じることができますが、そのときだけいわば主権者としての権利を行使しているにすぎないのではないか。それ以外の時はすべては「国王の奴隷」だと。日本には国王はいませんけれども。
私たちは実際、政治に直接関与していないわけですから、普通の市民は政治に関与していないので、本当に清き1票を投ずることしかできないわけですね。それ以外は結局、議員の政治家が国会や内閣で行っていること、それから決定したことに従うしかない。それがどんなに不満でもそれに従わなければ、場合によっては逮捕されかねないですね、法律に違反すれば。そういうことをルソーは奴隷だと言っているわけです。
では、どうすればいいのか。それを解き明かそうとするのが『社会契約論』です。その主張は要するに、「各構成員の身体や財産を共同の力すべてによって保護する一形式を見いだし、それにより各人が全員と結び付きながら自分自身にしか服従せず」、つまり自由だということですね。「以前と同じく自由であること」、こういう政治体制をつくることが根本的な問題ではないかということです。思想史の教科書などはこれをそのまま直接民主制の教え、勧めというふうにいっているわけです。
ただ、私はこの直接、間接という言葉は近年使わないようにしています。これは非常に誤解を招く表現だからです。というのはルソーが次にこう言っているのです。「民主制という言葉の意味を厳密に解釈すれば、真の民主制はこれまで存在しなかったし、これからも決して存在しないだろう。多数者が統治して少数者が統治されるということは自然の秩序に反する」
つまりルソーは立法権は代表されないということを言っているのです。立法権こそが最高の権力。国家の骨格となる法をつくるわけです。日本でいえば日本国憲法に当たる最高法規の制定や改正には、国民が直接参加すべきだと言っている。しかし日常的な行政に関する法律や条令などは無限にありますから、こういうものの制定にすべて住民、市民が関わっていたら、仕事になりません。
ルソーもそれは百も承知です。彼の『社会契約論』は、すごく観念的でユートピア的だといわれることもありますが、しっかり読んでみると決してそんなことはありません。きちんとその辺は考えられている。つまり日常的な行政は、王侯貴族、官僚政治家、そういうプロに任せておけばいいということを大前提にしているのです。彼の言っている人民主権というのは、立法権だけは代表させてはいけないという意味です。
ルソーの場合、暗黙のうちに女性は排除されています。それから市民といっても貧しい市民が本当にルソーが有権者として考えていたかどうかも、やや怪しいところがあります。しかし、基本的には、当時の観念における市民は、直接参加して憲法のレベルでの立法に参加しなければならないということです。逆に言うと、そういうポイント、ポイントだけを押さえていけば、それ以外のところはプロの政治家や官僚に任せておけばいいというのが、実は彼の本音でした。だからこれを直接民主制と言うことは、非常に誤解があるわけです。
同時にルソーの人民主権論というのは、決してバラ色のものではありませんでした。次の文章はルソーを民主主義者として持ち上げる人はあまり引用したくない文章ですが、私は必ず引用します。これは決定的に重要なのです。
「各個人が自分自身の土地に対して持つ権利は共同体が国土全体に対して持つ権利に従属する」。そう言っているわけですね。つまり土地の所有権というものが諸悪の根源だと言っているわけですから、土地の所有権というのはもともと絶対ではあり得ないわけです。普通の家族がちゃんとした生活をしていくために必要な最低限の土地、これはもちろん所有を認められますけど、その所有といっても絶対ではないですね。あくまで国家の権利が優越するのです。
実は今日の日本国憲法でも公共の福祉に従属する形で私有財産権が認められている、日本国憲法においてすら。我々、この社会というのは私有財産、絶対の社会だと思い込んでいますけど、憲法をよく読んでみれば、それは絶対ではないということがはっきりします。公共の福祉にあくまで従属する。ただ、日本は諸先進国の中では、最もこの私有財産権が守られている国だといわれているんですね。例えば、東京の環状道路がなかなか完成しないのは、土地・建物などの私的な所有権が尊重されるからです。大変な反対運動が展開された成田国際空港などの例を挙げることもできます。しかし、ルソーの言っているのは、実はそういう私有財産が絶対だという考え方では実はないんですね。
同じようにもっと深刻な言葉もあります。
「統治者が市民に向かって、お前の死ぬことは国家の役に立つのだと言うと、市民は死ななければならない」。これ、ルソーの言葉ですよ。これはもうぜひ肝に銘じておかなければいけないんですね。つまりルソーの言っている人民主権国家というのは、自分たちがつくった、自分たちの国なんだから、その自分たちの国が危機にひんしたら、場合によっては命を捧げても仕方がないということを言っているわけです。
どの人にその順番が回ってきて、その役割を担うのかは、運なのです。だからルソーもその辺はさらっと書いています。運悪く徴兵されたらみたいなことが書いてあるのです。運悪く徴兵された場合は仕方がないけれども、命をささげなければならない。誰かがその役を引き受けなければならないということを言っているわけです。
ですから彼の人民主権国家というのは、決してバラ色のものでもなければ、無責任でいられるようなものでもありません。この世の楽園のようなものではないということを、ここで確認しておきたいということです。そういう強力な、また強烈な論理と理念がなければ、現実の文明社会を批判することはできなかったということなのです。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください