BBCが先駆者となって90数年、メディアの立ち位置は市民の側に
2018年12月13日
英国には、放送業を「公共サービス」としてとらえる伝統がある。公共への奉仕として、つまり公益のために存在しているという考え方である。
「公のための放送業」とは何を目指し、具体的にはどんなことをするべきなのかについては、過去数十年にわたり議論が続いてきた。一方、公益を果たす意味からさまざまな規制が課されており、「規則でがんじがらめだ」と嘆く放送関係者が少なくない。
民放が大きな力を持つ日本の事情とは少々異なり、「公共のための放送」という概念が圧倒的な英国の放送事情を紹介してみたい。
英国で放送業が始まったのは、1920年代だ。
今でいうところのラジオ(当時は「無線機=ワイヤレス」と呼ばれた)を販売するために、無線機メーカーが集まって民間企業BBC(British Broadcasting Company)が発足した(1922年)。
BBCは、政府(郵政省)からラジオの販売と放送の事実上の独占権を与えられた。運営費はラジオの販売収入と聞き手が郵政省に払う「受信免許料」(ライセンス料)であった。
この頃、郵便体制、漁業、水道、電気が公共体として運営されており、放送業も公共体が提供する公的サービスであるべきという考え方が広がっていた。
英政府による米国視察では数千もの放送局が乱立しており、中央からの規制体制のもとに放送体が形成される道を政府は選択したようだ。
そこで独立調査委員会が立ち上げられ、識者による調査・議論の末に、公共放送としてのBBC(British Broadcasting Corporation)が1927年に組織化された。
その後、商業放送としてITV(1955年開局、以下同)、チャンネル4(1982年)、チャンネル5(1997年)が新たに開局していった。衛星放送の有料テレビ局「スカイ」の前身が生まれたのは1990年である。
現在、英国の主要放送局はBBC、ITV、チャンネル4、チャンネル5だ。いずれも、日本同様無料で視聴できる。(ただし、テレビ番組の視聴にはBBCのライセンス料を払う。これはNHKの受信料と同等の位置づけである。)
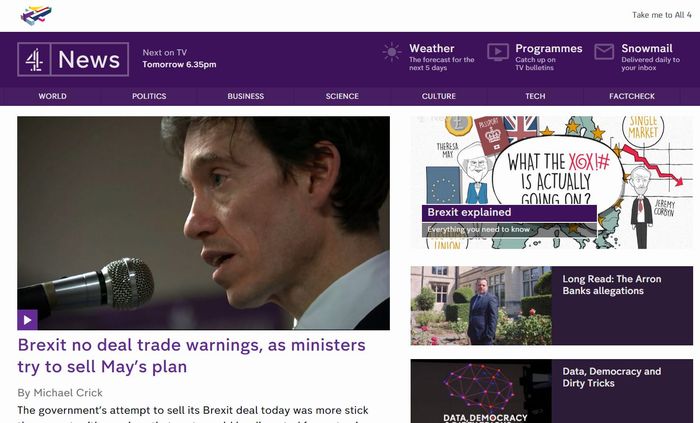 政府が所有し、運営費は広告収入となるチャンネル4のニュース・サイト(ウェブサイトより)
政府が所有し、運営費は広告収入となるチャンネル4のニュース・サイト(ウェブサイトより)改めて「公共放送」の定義を見ると、例えば「百科事典マイペディア」によれば、「放送事業体が営利を目的とせず、聴視者からの聴視料などをおもな財源として、公共の福祉と発展を事業目的として行う放送を商業放送と対比していう」とあり、具体例としてNHKやBBCが挙げられている。
日本で「公共放送」というとNHKになるため、財源に着目し、「公共のお金で運営される放送」という理解になるだろうと思う。
しかし、英国で「公共サービス放送(Public Service Broadcasting =PSB)」というと、その財源が公的な資金である必要は必ずしもない。
先に挙げた主要放送局であるBBC、ITV、チャンネル4、チャンネル5のすべてがこのカテゴリーに入る。
ITVとチャンネル5は、主として広告収入によって運営されている。ITVは民間企業ITVが所有し、チャンネル5は同じく民間企業のバイアコムが所有している。いわゆる、「民放」である。民間企業は、事業(放送業)を行うとともに最大限の利益を上げることが目的となる。
チャンネル4は政府が所有しているが、その運営費は主として広告収入だ。公なのか民なのか、区分けがしにくい放送局である。
こんな風になってしまったのは、最初にできた放送局がいわゆる「公共放送」(財源にもその目的にも「公」という要素が入る)のBBCであったことによる。
BBCの後にできた放送局は、財源がどうなっているかに関係なく、「BBCスタンダード」(公のために放送する)を順守する形で開局している。
英国で放送免許を与えるのは第三者機関「オフコム」だが、PSBの免許を与える条件として放送局はその番組内容に多様性があること、オリジナルの番組が一定数放送されること、リピート番組の放送回数を一定数に抑えることなどが義務化され、ニュース番組には不偏不党が求められる。
衛星放送スカイテレビのスカイニュースはPSBではないが、ほかのテレビ局同様にニュース報道では不偏不党を維持する方針をとっている。
例えば米国で保守系勢力に人気があるフォックス・ニュースを放送する局は、英国のPSBの枠の中には入ることができないだろう。
不偏不党は「中立(neutral)」とも言えるのかもしれないが、よく使われるのが「impartial」という言葉だ。対立する2つの意見があれば、その両方を入れる、ということである。どちらかに偏ることはない、と。
「中立(neutral)」という言葉には、「どちらの側にもコミットしない」というニュアンスを筆者は感じるのだが、どうだろうか。
英国のメディアは、どんなニュースのトピックにせよ、「真ん中の位置にいて、どちらの側にもコミットしない(関与しない)」という立場を、取らない。
どこに立ち位置を置くかというと、市民の側である。時の政府、大組織、富裕層などは「権力者」であり、メディアは市民のために、その権力者の嘘を暴くために存在している。
なぜそうなったのかを理解するには、BBCの誕生以前、もっと時代をさかのぼる必要がある。
英国に印刷業が伝わったのは15世紀末だ。権力者(王室)は危険な思想を広める可能性を秘めた印刷業を免許制度にした。免許を持った印刷業者のみが出版物を発行することができ、事前検閲もあった。
ところが、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください