神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(1)
2019年01月17日
本連載で著作権改革案を最初に提案させて頂く生貝直人です。
開幕の辞を執筆された福井健策先生が世話人を務める「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(think C)」の発足当初にスタッフとして参加したことをきっかけに、今日まで10年以上、延長問題をはじめとする著作権制度のあり方について勉強をさせて頂いてきました。
ご存じの通り、TPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の発効に伴い、日本の著作権保護期間は2018年12月30日をもって20年間の延長がなされました。
この影響は著作物の利用と創造を行う全ての人々にとって計り知れないものですが、目下最も直接的な打撃を受けるのが、過去の知の蓄積をオンライン公開し、誰もがアクセス可能な、情報社会の知のインフラを作り出すデジタルアーカイブ構築の取組です。
200万点以上のデジタル化資料を収録する国立国会図書館デジタルコレクション、日本中の博物館・美術館の所蔵作品を公開する文化遺産オンラインなどの公的な文化施設が担うもの、そして青空文庫のようなボランティアの取組など、さまざまな機関・団体がデジタルアーカイブの構築を進めてきていますが、これから20年間、日本では、保護期間が満了して新たにデジタルアーカイブで公開可能となる著作物は、ほぼ生まれてきません。
私自身、保護期間延長問題、そして産官学の様々な立場からデジタルアーカイブの構築と関連する法制度の研究に携わってきた立場から、今般の保護期間延長が情報社会の知のインフラ構築に与える影響を出来る限り軽減するための「非常に控えめな提案」と、そしてそれに加えて「少し野心的な+αの提案」を、今回はご紹介させて頂こうと思います。
米国は日本よりもちょうど20年早い1998年に保護期間を延長し、死後70年という異常に長い期間を世界的潮流としてきた震源地です。
今回のTPP11発効に伴う保護期間延長も、元々は米国の強い要請を受けてTPPの中に盛り込まれたものでした(ご存知の通り、その後米国自身がTPP自体から離脱してしまったわけですが)。20年前のソニー・ボノ米国保護期間延長法に対しては、クリエイティブ・コモンズの創設者としても著名なローレンス・レッシグ教授をはじめとする法学者らが中心となり、違憲訴訟を含む大規模な反対運動を行ったことを覚えていらっしゃる方も多いかもしれません。
実はこの1998年の保護期間延長法の中で、日本ではほとんど知られていませんが、米国著作権法には「108条(h)項」という条文が設けられ、保護期間最終20年に入った著作物は、絶版等の要件を満たす限り、図書館等のアーカイブ機関がオンライン公開を行うことができるとされました。
米国著作権法108条とは、図書館等に関わる権利制限を定めた条文で、(a)項から(g)項には日本の著作権法31条にあるような利用者のためのコピーなどが規定されていますが、問題の(h)項の条文は以下の通りです。
米国著作権法108条(h)項(山本隆司訳、公益社団法人著作権情報センター)
(1) 本条において、発行著作物に対する著作権の保護期間の最後の20年間に、図書館または文書資料館(図書館または文書資料館として機能する非営利的教育機関を含む)が、相当な調査に基づいて第(2)節(A)(B)および(C)に定める条件に該当しないと第一次的に判断した場合には、保存、学問または研究のために、かかる著作物またはその一部のコピーまたはレコードをファクシミリまたはデジタル形式にて複製、頒布、展示または実演することができる。
(2) 以下のいずれかの場合、複製、頒布、展示または実演は本条において認められない。
(A) 著作物が通常の商業的利用の対象である場合。
(B) 著作物のコピーまたはレコードが相当な金額で入手できる場合。
(C) 著作権者またはその代理人が、著作権局長が定める規則に従って、第(A)号または第(B)号に定める条件が適用される旨の通知を行う場合。
(3) 本項に定める免除は、図書館または文書資料館以外の利用者による、以後の使用には適用されない。
最近ではこの条項を使って、ウェブサイトのアーカイブで有名なインターネット・アーカイブという非営利団体が、保護期間最終20年に入った書籍等を対象とした、「ソニー・ボノ・メモリアル・コレクション」という、保護期間延長法(起案者)の名前を冠した、少し皮肉の効いた名称の素晴らしいデジタルアーカイブを公開しています。
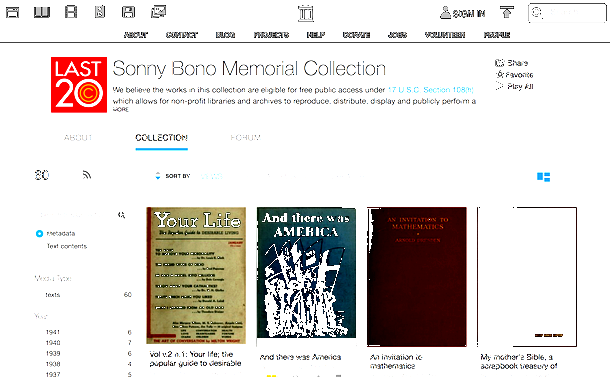 インターネット・アーカイブのウェブサイト『ソニー・ボノ・メモリアル・コレクション』
インターネット・アーカイブのウェブサイト『ソニー・ボノ・メモリアル・コレクション』
保護期間延長の震源地である米国においても、その副作用を少しでも軽減するために、20年前の延長と同時に、このような条項を設けていたのです。
現在のTPP11では保護期間延長は米国が戻るまでの凍結事項とされているものの、近く発効する日EU経済連携協定にも保護期間延長が含まれていますので、延長してしまった保護期間をもう一度短縮することは、今後極めて困難です。
しかし、ここで紹介した米国型の最終20年条項は、あくまで保護期間は延長したままで、部分的な権利制限規定を導入する形式ですから、それらの国際協定に矛盾することもありません。すでに米国も導入している内容ですから、ベルヌ条約等の著作権条約に抵触することもありません。
保護期間の延長は全ての著作物に及ぶものですが、著作者の死後50年を経ても商業的に利用されるごく一部の作品を除けば、大部分はインターネットで公開しても、まさに誰も損をしない、ただただ社会全体の利益を増大させるものです。せめて日本でも、このくらいの条項は、1日も早く導入してほしい。
これが第一の「非常に控えめな」私の提案です。
日本での導入を考えた場合、具体的には著作権法31条に「4項」を新しく設けて、同条の適用を受ける「図書館等」は、保護期間最終20年に入った「絶版等資料」を、デジタルアーカイブとしてインターネット公開することを認める方式が最もシンプルだと思います。すでに絶版等資料に関しては、同条31条3項に基づいて、国立国会図書館が全国の図書館等へのデジタル送信を行なっており、絶版の判断などはそれを準用できそうです。
なお31条の適用を受ける「図書館等」は、公立・大学図書館のみには限られず、著作権法施行令1条の3により、法令で設置された各種施設等が含まれ、特に2015年には、営利を目的としない法人が設置する博物館を広く含む指定がなされたところです。一点、108条の適用を受ける図書館等を柔軟に規定し、インターネット・アーカイブをも対象とすることができる米国と異なり、日本の施行令1条の3の範囲は限定的で、たとえば青空文庫のような民間のデジタル図書館を含むことは困難です。ただ、これは施行令の見直しで済みますから、さほどハードルは高くない問題だと考えて良いでしょう。
さて、ここまでの内容を、この連載の元となる骨董通りリンクのイベントで聞かれた参加者からは、「ちょっと控えめにすぎるんじゃないか」、「絶版、特に非営利アーカイブに限るのであれば、最終20年なんて限定する必要は無いんじゃないか」というご意見を多く頂きました。
実際に私も、神様からもらった「一ヵ所だけ」著作権法を変える力をこれだけで使うのは実に勿体ないと思います。そこでもう少し野心的な、「+α」の提案をします。
私は本業としては米国やEU(欧州連合)の情報政策を研究しているのですが、現在EUで、「デジタル単一市場における著作権指令」という、デジタル時代に対応したEU著作権法の大幅な改革を行うための新指令案が注目を集めています。この指令案はいわゆる「リンク税(11条)」や「フィルタリング義務付け(13条)」などの条項が物議を醸していますが、著作物の適切な利用を促進するための重要な規定も含まれています。
欧州委員会が2016年9月に公開した当初案の段階から、同指令案7条1項には「文化遺産機関による絶版(out-of-commerce)作品の利用」という条項が含まれており、ここではEU加盟国に対し、文化遺産機関(公衆に開かれた図書館、ミュージアム、文書館、フィルム・オーディオ遺産機関)が所蔵する絶版作品のデジタルアーカイブ公開を可能にするための、拡大集中許諾制度の仕組みを導入することを求めています。
拡大集中許諾制度とは、欧州の一部で導入されている、JASRACのようなある分野で相当程度の代表性を有する集中権利管理団体が、当該団体に加盟していない権利者の著作物についても、一定条件で利用許諾を行うことができるという制度です。
しかし拡大集中許諾制度には、そもそも相当程度の代表性を有する集中権利管理団体が存在する分野自体が限られているなどの課題があります。たとえば日本で導入したとしても、JASRACが高い加盟率を持つ音楽分野以外での運用は事実上困難なのではないかと考えられます。
この点について、2018年9月12日に欧州議会が採択した修正提案7条1a・1b項では、拡大集中許諾等のライセンス手段が機能しない分野について、そうした仕組みなしで、文化遺産機関が絶版作品をオンライン公開することを可能とするための権利制限規定を導入する旨の提案を行っています。
デジタル単一市場における著作権指令案 7条(議会修正提案、邦訳筆者)
1a項:加盟国は、以下を要件に、文化遺産機関が、そのコレクションに非営利目的で恒久的に所蔵する作品の複製を、オンラインで利用可能とできるよう、(※EUの各種著作権指令に規定される)権利の例外又は制限を規定するものとする 。
(a) 不可能でない限り、作者の氏名その他識別可能な権利者を表示する
(b) 全ての権利者は、いつでも絶版であるとみなされている作品に異議を申し立てることができ、作品への権利制限適用を除外することができる
1b項:加盟国は、1a項に従って採択された権利制限が、1項に規定された解決策(※拡大集中許諾制度)を含むがこれに限定されない適切なライセンスに基づく解決策が利用可能な分野または種類には適用されないことを規定するものとする。加盟国は、著作者、その他の権利者、集中権利管理団体、文化遺産機関と協議して、特定の分野または種類の作品に対する拡大集中許諾に基づく解決策の利用可能性を決定するものとする。
「最終20年」にも限定されない、米国の108条(h)項と比しても相当程度広範な絶版作品のデジタルアーカイブ促進条項であり、Europeanaを中心とした全欧州でのデジタルアーカイブ推進に力を注いでいるEUらしい提案です。
同指令案は現在審議中の段階であり(議会単独で立法を行える日本と異なり、EUでは欧州委員会・欧州議会・加盟国代表の閣僚理事会が三者共同で立法を行います)、最終的な実現の可否は今後の審議を見守る必要がありますが、世界でも影響力の強いEU28カ国がこのような方向に進もうとしていることは、非常に注目すべき国際動向であると言えます。
以上をまとめますと、私が「神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら」、著作権法31条を改正して、せめて米国型の108条(h)項相当の「最終20年条項」を導入する、いやそのような控えめなことは言わず、EU型のより広く絶版作品全体のデジタルアーカイブ公開を可能とする条項を導入したい、ということになります。
本提案は、あくまで非営利のデジタルアーカイブを念頭に置いたものであって、保護期間延長がもたらす創造のサイクル全体へのダメージに対応できるものではありません。それに米国やEUがすでに実現している(しようとしている)施策をほとんどそのまま導入しようという、いかにもクリエイティビティに乏しい提案です。
しかしそれだけに、誰も損をしない、そして実現性の高い内容だと思っています。本連載の錚々たる執筆陣の先鋒として、地味でも手堅い提案をお届けできていれば幸いです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください