2019年03月27日
 Den Rise/shutterstock.com
Den Rise/shutterstock.com現在のような大衆向けの新聞が定着した19世紀。かつてニューヨークで発行されていた新聞「ニューヨーク・トリビューン」紙の記者ジュリアス・チェンバースが、同じくニューヨークにあったブルーミングデール精神病院の実態を暴露し、12人の「患者」(実際には精神疾患ではなかった)が解放されるという出来事があった。彼は1872年に、ニューヨーク・トリビューン紙副編集長の力を借り、患者として同病院に潜入。10日間で退院すると、その体験を紙面で発表したのである。記事は大きな反響を呼び、患者を解放しただけでなく、最終的には関連法が改正されるまでに至った。この一件は、いわゆる調査報道のもっとも古い例のひとつとして知られている。
それから150年近く経とうとしている現在も、調査報道はジャーナリズムの花形として位置付けられている。とはいえチェンバースの例が象徴するように、調査報道は決して楽ではない。優秀な記者の工数を文字通り「拘束」しなければならず、しかも書き上げられた記事がビジネス上の成果(売上部数のアップなど)をもたらすとは限らない。そのため報道機関の一部は、調査報道を縮小する動きを見せており、そうでない報道機関も、売上が伸び悩む中でどう調査の予算を捻出するかに頭を悩ませている。
最近注目されているのは、お馴染みのAIだ。さすがにAIを病院に潜入させることはできないが、既に一定のフォーマットに従って記事を書く程度の作業はできるようになっており、記者の負荷を減らすという取り組みが行われている。たとえばテクノロジー系ニュースサイトDigidayの記事によれば、ワシントンポスト紙は自社開発したAI「ヘリオグラフ」を使い、前回のリオデジャネイロ・オリンピックの際に約300本の関連記事を自動生成したそうである。さらに2016年の米大統領選の際には、選挙関連の記事を約500本生成したそうだ。
 米大統領選の集会で演説するトランプ氏=2016年11月、ミシガン州グランドラピッズ
米大統領選の集会で演説するトランプ氏=2016年11月、ミシガン州グランドラピッズこうしたAIによる記事生成は、事実をあらかじめ用意されたテンプレートに機械的に割り振ることに近く、調査報道とは程遠い。とはいえそうした記事も、これまでは記者が貴重な時間を使って書き上げていたものであり、それがAI化されることで記者は他の(人間にしかできない)作業に時間を割り振ることができる。実際に前述の記事では、AP通信が企業収益の報道にAIを活用した結果、この報道に費やされていた記者の時間を20%解放することができたと伝えている。
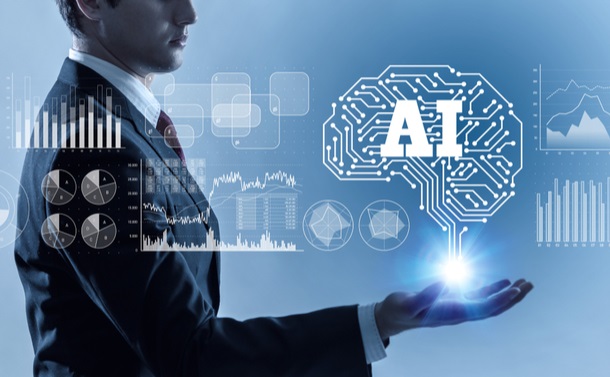 metamorworks/shutterstock.com
metamorworks/shutterstock.comこうした「AIに簡単な仕事を任せて、人間は空いた時間でより創造的な仕事をする」という考え方は、ジャーナリズムに限った話ではなく、多くの企業が似たような取り組みを行っている。ただ最近、そのように間接的な形ではなく、より直接的な形でAIを創造的行為に役立てようという動きが出ている。たとえばAIに過去にヒットした曲を解析させ、人間も気づいていなかったような「ヒットの法則」を割り出し、それに沿って新曲を作るといった具合である。
前述のヘリオグラフも、選挙結果が予想されていた結果と異なることが検知されると、記者にアラートを上げる機能を実装していたそうだ。予想は予想でしかないが、最近はデータ分析の高度化などによって、選挙結果の予測精度は飛躍的に高まっている。それでも予想が外れるということは、そこに何らかの(人間が気づいていなかった)特別な要因があるはずだ。それを人間の記者が取材しに行くというわけである。
これは調査報道そのものではないが、調査報道のきっかけをAIが生み出している、と言えるだろう。蓋を開けてみればたいした理由ではなかった、という結果になるかもしれない。それでも闇雲に問題を探しにいくより、はるかに効率的だろう。
同じように、AIが間接的に関与した調査報道によって、書き上げられた記事が賞を獲得するという例も生まれている。
米国における優れた報道に対して贈られる「ピューリッツァー賞」。2016年、同賞の公益(Public Service)部門を受賞したのが、東南アジア地域での漁船の奴隷的労働に関するAP通信の報道だった(対象となった記事をこちらから確認できる)。この報道は水産業界の闇を暴くことで、関係する国の政府や企業を動かし、奴隷的な境遇にあった船員2000人以上が解放されることとなった。
AP通信は1年かけてこの問題の調査を行ったが、その際に活用されたのが、コンピュータービジョンと呼ばれるAI技術のひとつである。これはコンピューターに画像を解析させ、そこに隠れた情報や意味を読み取らせるというもの。クルマが写っている写真を見せ、「ここに映っているのはクルマだ」と判断させるといった具合である。簡単に感じられるかもしれないが、それは人間にとって簡単だというだけであり、機械にそうした判断をさせるのは難しかった。それが近年のAI関連技術の発達により、実用化される例が増えているのだ。
AP通信のケースでは、このコンピュータービジョンが、違法な労働を行わせている可能性のある漁船を割り出すことに役立てられた。彼らはデジタル・グローブ(Digital Globe)という企業に協力を仰ぎ、疑わしい漁船の特徴をAIに学習させた。そしてそのAIに、人工衛星が撮影した画像をAIに読み込ませ、似たような漁船を探らせたのである。その結果、彼らは実際に違法操業中の漁船の衛星画像を捉えることに成功した。
こうしたAIによる調査報道の進化の可能性に、メディア関連の研究機関も注目し、後押ししようとしている。
ハーバード大学内の研究所のひとつであり、インターネットとその社会への影響を研究テーマとしているバークマン・センターと、マサチューセッツ工科大学(MIT)のメディアラボが2017年に立ち上げた、The Ethics and Governance of Artificial Intelligence Initiative(人工知能の取り組みにおける倫理とガバナンス)という共同プロジェクトがある。これはAI関連技術が公平性や社会正義などを守った形で開発・利用されることを促そうというもので、AIとジャーナリズムの関係を探る取り組みについて、合計75万ドルの資金提供することを発表していた。
 Songquan Deng/shutterstock.com
Songquan Deng/shutterstock.comその選定結果が今年3月に発表されたのだが、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください