「T」マークの「信頼」構築プロジェクトに取り組む人々も
2019年05月13日
 「コレスポンデント」のウェブサイト画面。同社の姿勢を象徴する言葉、「Unbreaking news」(最新ではないニュース)が掲げられている=同社のウェブサイトから
「コレスポンデント」のウェブサイト画面。同社の姿勢を象徴する言葉、「Unbreaking news」(最新ではないニュース)が掲げられている=同社のウェブサイトから「ニュースの速報競争から離れて深い解説を重視します」「取材過程も公開してユーザーと共有していきます」――。
オランダ発のメディア「コレスポンデント」(The Correspondent)は、これまでのメディアやジャーナリズムが「常識」とみなしてきたいくつかの基本姿勢に「NO」を突きつけ、新たな試みを始めている。
オランダではすでに2013年から活動を開始している「コレスポンデント」だが、今年夏ごろにもニューヨークを拠点に米国でローンチし、英語版のニュースを発信しようとしている新媒体だ。その資金を集めるためにクラウドファンディングの手法を導入したところ、わずか30日~40日の間に4万5千人の賛同者から260万ドルを集めることができたという。
同社のエンゲージメント・エディター、ジェシカ・ベスト(31)は「従来のジャーナリズムに飽き飽きしていた人たちにはぜひ『コレスポンデント』に参加していただき、その上でその怒りを推進力に、読者参加型の私たちと一緒に戦うことでジャーナリズムを共に変革していけたらうれしい」と話している。
 「コレスポンデント」のエンゲージメント・エディター、ジェシカ・ベスト=photographer as:On A Hazy Morning, Amsterdam.
「コレスポンデント」のエンゲージメント・エディター、ジェシカ・ベスト=photographer as:On A Hazy Morning, Amsterdam.ジャーナリズムが「当然の前提」とみなしてきたことに真っ向から異議を唱える「コレスポンデント」を象徴するような言葉が「unbreaking news」(最新ではないニュース)だ。
テレビ番組などの途中でキャスターやアナウンサーが「Breaking News」(「いま入ったニュースです」)と断って流れを一時中断し、センセーショナルに伝えるこれまでの報道スタイルを否定。その代わりに、物事の背景にあるものや歴史的経緯などそのニュース本来の意味に着目して深い解説を加えることで内容を充実させ、「日々押し寄せるニュースから置いてけぼりになりかけている読者を救済しよう」というチャレンジでもある。
「これまでのニュース報道のあり方には非常に危機感を抱いています」
そう話すベストは「従来のニュースでは『単発的なイベント』のような報道が多く、なぜそういう事態に立ち至ったのかといった歴史的背景を十分扱ってこなかった」と指摘。加えてニュース番組の背後にいるスポンサーを意識するあまり、「スポンサーにとっての有益性」を考慮してしまう帰結として「ニュースが粉飾されたり、事実以上にドラマチックに描かれたりする傾向があった」と話す。また、例えば権力を持った側の人たちの発言を右から左に伝えるような報道も目立ち、「その結果、権力者の思う通りの報道に成り下がる危険性があった」という。
では、「コレスポンデント」は具体的にどのような報道を展開していくのか。
「ただ単に『こういうことが起きている』という現実だけを提示するのではなく、『なぜそれが起きているのか』という部分も合わせて読者に伝え、情報に深みを持たせたい。それがポイントです」とベストはいう。「例えば『今日の天気がどうか』ということではなく、その裏にある『どうして今日のような気候になっているのか?』という大きな流れを説明すること。それとともに『なぜそうなっているのか』という点を解説することによって、『今後私たちはどのように対応していけばいいのか?』といった点も読者に考えてもらうことができるようになると思っています」
「コレスポンデント」の方から読者に何か直接指示をするわけではないにしても、「課題や問題をめぐる将来の解決方法や、指針となるような素材を私たちが提供する、そういう形の報道も心がけたいと思っていますし、それが私たちの責任でもあると考えています」とベスト。
そしてこう強調する。
「これこそが、私たちがフェイクニュースに対抗するやり方だと考えているのです」
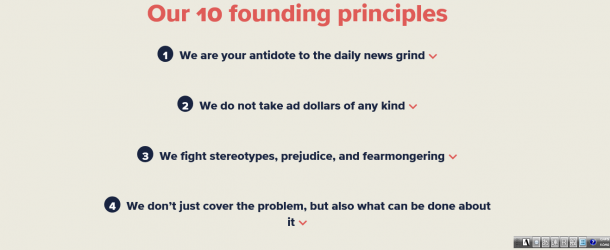 「コレスポンデント」が掲げる10の創立理念=同社のウェブサイトから
「コレスポンデント」が掲げる10の創立理念=同社のウェブサイトから「コレスポンデント」はウェブサイトに「10の創立理念」を打ち出している。その中の5番目にはこう書かれている。
「私たちの読者は、私たちがカバーするストーリーの大半について、私たちよりもよくご存じです。あなた方がよくご存じの何かについて私たちがカバーする時は、あなた方の専門知識で貢献していただき、経験も共有していただけるよう、みなさんをお招きします」
この下りは、読者を「物事に精通している聡明なメンバー」とみなし、「ともに新しいジャーナリズムを作っていこう」という姿勢を打ち出したものということができるだろう。
この点について、ベストは「公開ノートブック」というコンセプトと、「記者が学びの過程を読者と共有する」というコンセプトがあると説明する。
「記者がこれから取材しようとする内容について、むしろ読者の方がエキスパートだということがままありますよね。例えば、子育てについての記事を書こうと思った時、子どもを現在育てている読者の方が経験が豊かでその問題の根幹部分をよくご存じだということがあります」
「そんな時は、経験豊富な読者の方からいろいろな知識や情報を記者がいただくことによって、『これから具体的にどんなふうに取材を進めていこうか』とか『どういうアプローチで取材に入ろうか』と考えることができ、記者にとってプラスになります。同時にそういう経緯を経ることで、私の言葉でいえば読者が参加する『参加型レポート』を作っていくことが可能になるというわけです。またそれを実行することによって報道の幅や深さがいっそう深まっていくということもあると思います」
その際、記者はウェブ上に記事のアイデアや取材計画などを書き込んだ「公開ノート」をオープンにし、それをもとに、ソーシャルメディアなどを通じて読者と具体的に「対話」をしながらその内容をアップデートしていくやり方を採用するという。
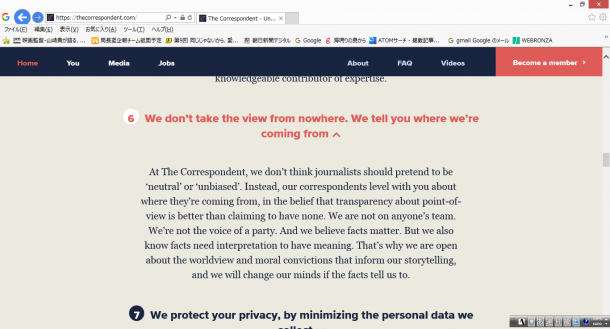 「コレスポンデント」が掲げる6番目の理念=同社のウェブサイトから
「コレスポンデント」が掲げる6番目の理念=同社のウェブサイトから「10の創立理念」の6番目はこうだ。
「ジャーナリストは『中立的』だとか『偏見を持たない』などと装うべきではないと私たちは考えています。それとは反対に、コレスポンデントの記者たちは、自分たちのものの見方を透明にする方が、そんなものはないと言い張ることよりましだという信念に基づき、自分たちがどこから来たかを明らかにします」
「不偏不党」「公正中立」「客観報道」などの理念を掲げてこれまでメディアやジャーナリズムが行ってきた基本的な姿勢や考え方に根本的ともいえる疑問を投げかけ、新たな方向性を示そうとする試みといえるだろう。
こうした考えに基づき、「コレスポンデント」は「透明性のある主観」(Transparent Subjectivity)という新たなコンセプトも打ち出している。
一見するとわかりにくいが、ベストはこう話す。
「記者が政治的な立ち位置を明らかにするというよりもむしろ、例えば『どういう子ども時代を過ごしたか』とか、『自分の今の考え方を左右するような大きな事件として過去にどんなことがあったか』など、その記者が人として成長する過程で出会ったことや影響を受けたことなどを、包み隠さず、透明度を持って表現する。そしてそのことを通して、それを読んだ読者に『なるほど、そういう背景を持った人がこの記事を書いているのか』と納得してもらう。それが大事だと私たちは考えているのです」
「ただし」とベストは断った上で、付け加えた。「そうした『透明性のある主観』を打ち出すことよりも、もちろんまずは『事実を伝える』ことに重きを置いてはいます。そのスタンスに変わりはありません」
ベストの説明は続く。
「ある特定のテーマをずっと追いかけている記者がいるとして、そのテーマに対する自分の考えが取材する過程でどんどん変わっていくというケースもありえますよね。その場合、そういうことも包み隠さずに書いていくということです」
一般的に、ジャーナリストがあるテーマに基づいて取材をする場合、事前準備の段階で取材対象の様々な情報を集める。例えば相手の個人的なデータや、これから訪れる組織や場所をめぐる過去の報道など、可能な限りの情報を収集しつつ「この問題はおおよそこういうことではないか」と自分の中で一定の「見立て」を持つのはごくふつうのことだ。
それを持ちながら現場に行った際、当初の予見が目の前の現実によって覆されたり、事前の知識がまったく役に立たなくなったりする中で「新たな発見」や「それまで気がつかなかった見方」が新鮮に立ち上がってくることも多い。またそれこそが「取材の醍醐味」でもある。
 ルポルタージュ「父よ母よ!」を語る斎藤茂男=1990年
ルポルタージュ「父よ母よ!」を語る斎藤茂男=1990年この点について、元共同通信編集委員の斎藤茂男はかつてこう述べた(注1)。ジャーナリズムの核心を突いた重要な指摘だが、メディアを目指す学生や若い記者、研究者の中には今や知らない者も少なくないというのが実態のようなので、少し長くなるがここで紹介しておきたい。
「私にとって、現場を歩き、直接、人びとに接する作業のなかには、明らかにそれら活字やヒアリングを超えるべつの因子が潜んでいるように思う」
「つまり、私は現場を歩くたびに、その取材対象についての私の予見がかならずひっくり返り、改めて現実というもののみずみずしく動いているさまや、複雑さに驚かされてしまう。すると昨日までの私の現実を見る視点、世界観がチンプに見えるようになり、昨日よりいささかは高い視点を獲得することができるように思われる。取材とはつまり、事実を発見することによって一種の自己変革を起こさせる性質のものだ、と私は思うのだ」
「このような自己変革は、一つには視点をたえず更新することによって、より深く『本質』に接近することを保障するはずであり、もう一つの面でいえば、記者自身に本来の意味でのこの仕事の『面白さ』を、確かな手ごたえをそえて保障してくれるはずである。昨日よりは今日、今日よりは明日と、より深く状況が見えてくる、新しい事実を発見する。その見えてきたもの、発見したものを書く。そのような作業があってこそ、記者の労働は本来の労働としての尊厳をとり戻すことができるのではないだろうか。いってみれば、取材は記者にとって『自己再生装置』でもあるはずなのだ」
そして斎藤はここからさらに一歩踏み込む。
「もう一つ、私の体験的な素朴な実感で言うならば、現場を歩き、自分の予見がひっくり返されるような取材、つまりより深く本質に迫るような取材をするということは、当然のことながら取材課題と深くかかわることなしにはあり得ないだろう」
「そうなると、そこに生きるナマ身の人間と、その人間のかかえている問題に対して、記者自身が『他人ごと』ですまされなくなるような切実感を呼び醒まされるに違いない。記者自身が職業としての『記者』である以前に、まず、『人間』として対応せざるをえない羽目に私たちを追いこんでいくだろう」
「このようなかかわりのなかで取材が進行するということは、取材課題を人間である自分の問題として見ることになり、自分の問題であるだけに『より深く考える』という過程へ進むはずだ。『取材』とは新聞記者にとってこのようなものでありたいというのが、私の自分に課す課題なのである」
逆にいえば、斎藤が目指したものとは逆に、それまでの「現実を見る視点」がひっくり返される驚きもなく、当初の「予見」をただ単になぞるだけで終わったような取材は「ほんとうの取材」に到達していないといえるかもしれない。
話を「コレスポンデント」に戻せば、こういえるだろう。
これまでのジャーナリズムでは、斎藤が書いたような長行のルポなどのケースを除き、そうした「自己変革」の過程そのものを書くというよりはむしろ、「自分が変わった」という実感や経験は明示化せずに原稿を書いたりリポートをしたりするスタイルが多かったといえるだろう。その意味でも、「自己変革」の過程を包み隠さずオープンにするという「コレスポンデント」の姿勢は、以前から一部で取り組まれてきたこととはいえ「画期的」と評することもできるのではないだろうか。
 「コレスポンデント」のフェイスブックの画面
「コレスポンデント」のフェイスブックの画面「コレスポンデント」はビジネスモデルもまた斬新だ。
5年ほど先行してスタートしているオランダでの場合、ベストの説明によると、「コレスポンデント」の収入の7割以上は購読者からの購読収入でまかなっていて、それ以外の収入としては、所属する記者が書いた本の出版に伴う収益などが同社の経営を支えているのだという。
では、ニューヨークを拠点に始める米国でのビジネスはどうなるのか。
まず、昨年11月から12月にかけての約1カ月間余で、クラウドファンディングの手法でお金を集めたところ260万ドルの資金が集まったことは先に述べた。ベストはこう話す。
「今回集まったお金は、この英語版のウェブサイトを1年間運営するための資金として使われます。それ以降のものは、メンバーシップとして集められてくるお金でつないでいこうと考えています」
ただ、米国の英語版では「オランダとは少し違ったお金の集め方のモデル」を採用するという。
「オランダでは年間70ユーロと金額を固定しているのですが、米国でローンチする英語版では、参加してくれる読者の意思に応じて、つまり一人ひとりの『おさいふ』に合わせていくつか金額のカテゴリーを設定します。ですから『年間1ドルしか払いません』という人は購読料が1ドルでもいいし、『いや、もっと払いますよ』という人はもういくらでも払ってくださって一向にかまいません(笑い)」
何ともユニークな「ビジネスモデル」だが、なぜ英語版ではそうするのだろうか。
ベストの答えはこうだ。
「英語版の場合、読者の住んでいる地域によって経済状況が違いますよね。例えばニューヨークに住む人にとっての25ドルが、南アフリカのヨハネスブルグの住人にしたらどれだけ高額かということもあるわけでしょう。いずれにしても、『コレスポンデント』にとっては『読み手のアクセスが非常に自由』な状態を目指してこの『誰でも好きな金額で読める』という設定を考えました」
「オランダ版の場合、年間70ユーロと決めた時点でその金額を払えない人が出てくるわけで、その人たちはいくら『コレスポンデント』を読みたくても読めません。そういう『障害』をこの英語版ではなるべく取り払いたい。そんな思いからこの『払いたい人が払える金額を払う』という設定にしたわけです」
米国ではトランプ大統領の登場以来、メディアと大統領の確執が続いてる。「だが」とベストはいう。
「この間、ニューヨーク・タイムズにしてもワシントン・ポストにしてもネットなどで購読者数を増やしていて、購読者との関係をそれ以前より深めているという現実もあると思います。私たちも読者の参加を通して読者が望んでいるものを提供したい。読者の参加によってさらにジャーナリズムの質を高めていこうと思っています」
最後に、自身はなぜジャーナリズムを目指したのか、そして今なぜ「コレスポンデント」で働くのかをベストに聞いてみた。
「子どもの時から私は本当にジャーナリストだったと思いますよ。なにしろ家族の中で新聞を作って書いていたのですから」。そういってベストは朗らかに笑った。「『エンゲージメント・エディター』という肩書は、要するに『何でも屋』ということです。オランダで成功したこの事業を、どのようにしたらうまく英語版に持ってこられるか。また英語版を読んで下さる読者の人たちに対し、どうしたらオランダでやっているようなやり方と同じメッセージをうまく伝えることができるか。日々試行錯誤しているというのが今の私の仕事です」
 ニュースの読み手にとって参考となるような八つの指針を策定した「信頼」構築プロジェクトに取り組むサリー・ラーマン=サンフランシスコ
ニュースの読み手にとって参考となるような八つの指針を策定した「信頼」構築プロジェクトに取り組むサリー・ラーマン=サンフランシスコサンフランシスコで会ったジャーナリストで、サンタクララ大学「トラストプロジェクト」のシニアディレクターでもあるサリー・ラーマン(59)も「ジャーナリズムに透明性をもたらすことで報道への信頼を取り戻そう」と積極的に活動している一人だ。
ラーマンは、ワシントン・ポストやエコノミストなど80近くの国際報道機関の幹部らとの協議を重ねながら、報道機関の倫理基準や執筆者の経歴など、「この記事は信頼するに足るか?」とユーザーが判断する際に参考となるような八つの指針(Trust Indicator)を策定。そして、それに沿った取り組みを実際に実行しているニュースサイトなどに対し、「信頼(Trust)」を意味する「T」マークを与える「信頼」構築プロジェクトに取り組んでいる。
「このプロジェクトに参加しているメディアのサイトなどにいくと、この『T』マークを見ることができます。こちらが掲げる基準をきちんとクリアしているか、私たちのスタッフが見極めてOKが出たらこのマークがつきます。ただし、マークは少し小さいのですが(笑)」とラーマンは話す。
「この『T』マークがあるということは、その会社は透明性の旗印のもと、いい情報を読者に提供できるように一生懸命頑張っていますということの証明になるわけです」
このプロジェクトの始まりは1990年にさかのぼるとラーマンはいう。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください