幻想をふりまくアベノミクスには戦前・戦中に似た危うさがある
2019年05月06日
*この記事で指摘している黒田日銀と日本軍のたどる時系列や組織論的な特色の驚くべき相似については、原真人著『日本銀行「失敗の本質」』で詳細に分析しています。
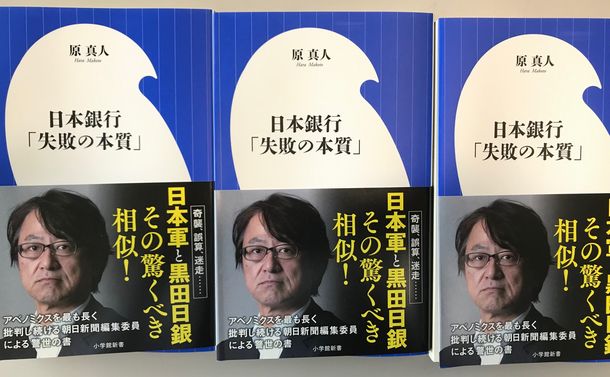
ここ数年、世界各国でポピュリズム政党が台頭している。
米国では共和党からドナルド・トランプ大統領という典型的なポピュリスト大統領が誕生した。民主党からも来年の大統領選に、バーニー・サンダース上院議員ら左派ポピュリストが名乗りをあげている。欧州でも中南米でも、ここ数年はポピュリズム政党の急進が目立っている。
理由ははっきりしている。先進国では経済がすっかり成熟し、かつてのような高成長が見込めなくなった。右肩上がりの経済のもとでは、黙っていても分配できた富が、原資がなくなり、簡単に国民に行き渡らなくなった。だからどの国でも国民に鬱積(うっせき)が広がり、ポピュリスト政治家が登場しやすい土壌ができている。
その嵐のなかで、比較的、安定しているのが日本の安倍政権といわれる。当然だろう。なぜなら最も早くポピュリズムを駆使した政権運営を始めたのが安倍政権だからだ。
最近、米民主党左派の間に広がり、経済学界でも話題となっている「MMT(現代貨幣理論)」。インフレにならない限り政府は中央銀行に紙幣を刷らせ、財政赤字を気にせずにどんどん財政支出できる、という驚くべきトンデモ経済理論だが、提唱者のステファニー・ケルトン・ニューヨーク州立大教授がこう言っている。
「日本が実例だ」(2019年4月17日「朝日新聞」インタビューより)
そう、MMTとはアベノミクスや日本銀行の異次元緩和がモデルなのである。日本では「リフレ論」がそれに該当する。
ちょっと考えれば持続可能性がないことがすぐわかるこれらの政策理論が、なぜ少なからぬ国民に支持されるのか。詳しい政策評価は別の機会に譲るとして、ここでは安倍首相や黒田東彦総裁の説明手法に焦点をあてて考えてみたい。
安倍政権はこの6年間に国政選挙を5回戦い、5連勝を遂げた。過日の衆院補選では2敗したものの、総じていえば、国政選挙でこれだけの強さを誇った政権はこれまでなかった。
連勝を支えた大きな力は憲法改正論でも安全保障政策や外交の成果でもなく、アベノミクスだったのではないか。「経済政策をうまくやっている」というイメージづくりに成功したことが、安定した経済を求める世論に受け入れられたのだと思う。
当初、安倍首相が「アベノミクスは成功」と言う根拠にしたのが円安と株高だった。円は1ドル=80円を割っていた水準から110円台で推移するようになり、政権発足時に8千円台だった日経平均株価は、2017年後半からはほぼ2万円以上の水準で推移している。
とはいえ、この円安・株高は米欧をはじめとする世界経済の好調さの波に乗った結果だ。
日銀が禁断の「株価底上げ策」で支えていることもある。日銀がとてつもない規模で国債を買い支え、長期金利をきわめて低水準に抑えていることも大きい。
消費増税が2回延期され、財政健全化目標はどんどん先送りされ、財政がひどく悪化しているにもかかわらず、長期金利はゼロ%。ひどく危険な政策を進めているのだが、おかげで投資家は超低コストで資金調達し、いとも簡単に株式投資でもうけられる環境となっている。株が下落しても、日銀のETF(上場株式で構成されている上場投資信託)買いが下落を防いでくれる。
これではマーケット機能は台無しだし、他にもさまざまな弊害や副作用を生んでいることに目を向ければ、いまの株価も額面どおりに評価できないはずだ。
それでも世論に成功イメージを広げたのは、安倍晋三首相が繰り返し呪文のように「成功」と唱え続けてきたが大きい。たとえデータが怪しくても、根拠らしき説明を添えて「成功」と繰り返し言い続ける。国会審議や記者会見など、首相のメディア露出度、発信力はきわめて高いから、そこで「アベノミクスによる株高」「アベノミクスによる雇用増」といったフレーズが繰り返されると、知らず知らずのうちに多くの国民にそう刷り込まれてしまう。
安倍首相による「成功の呪文」の例をいくつかあげよう。
◆「全国七つの県で有効求人倍率が過去最高になった。青森県、秋田県、高知県、徳島県、福岡県、熊本県、そして沖縄県だ。高度経済成長期、あるいはバブル期よりも、雇用条件はよくなった」(2015年11月29日、自民党の記念式典で)
◆「アベノミクスは、確実に結果を生み出しています。しかし、今、世界経済がリスクに直面しています。消費税率引き上げを2年半延期します。総合的かつ大胆な経済対策を講じ、アベノミクスのエンジンを最大限にふかすことで、デフレからの脱出速度を更に上げていきます」(2016年7月の参院選での自民党公約で)
◆「アベノミクスによって極めて短期間で、デフレではない状況を作り出した。私たちは結果を出している。果実は着実に生まれている」(2017年1月24日、参院代表質問で)
◆「この5年間、アベノミクス『改革の矢』を放ち続け、雇用は185万人増加しました。この春、大学を卒業した皆さんの就職率は過去最高です。この2年間で正規雇用は79万人増え、正社員の有効求人倍率は、調査開始以来、初めて、1倍を超えました」(2017年11月17日、所信表明演説で)
 地元・山口県でアベノミクスの効果を訴える安倍首相=2016年1月10日
地元・山口県でアベノミクスの効果を訴える安倍首相=2016年1月10日やがて、株高・土地高は持てる者には恩恵があるが、全体に広がっていないという「トリクルダウン」(富める者の富が次第に貧しい者にも滴り落ちてくること)批判が出てくると、今度は雇用環境の好転を「アベノミクスの果実」として宣伝するようになった。
有効求人倍率の上昇、完全失業率の低下はたしかに進んだ。ただ、その裏で非正規雇用の割合がどんどん増えている、という問題に首相は言及しない。なにより、この雇用環境の好転の主因はアベノミクスではなく、人口動態である。
日本の生産年齢(15~64歳)人口は1995年から減少に転じている。2010年に8103万人だった生産年齢人口は、2017年に7596万人になった。7年間で507万人も減少した。この減少分を埋めるように、女性と高齢者の就労が急速に増えた。それこそが雇用増加の主因だ。
こうした「事実」を説明することなしに、安倍首相はひたすら「アベノミクスの成果」と言い続ける。政権の功績だと演出できる都合のいいデータだけを選び出し、「成功した」と連呼する。いつのまにか人々に「アベノミクスは成功した」というイメージが植え付けられていく。
一方、日銀の黒田総裁の説明は、いわば「大本営発表」的だ。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください