「典型的なポピュリズムの国」、日本のメディアの現状は?
2019年05月02日
 ハンガリーのメディア状況を語るセッション(左からゲーゲリー氏、ドラゴミル氏、ペソ氏、スタイン氏。撮影Guendalina Ferri)
ハンガリーのメディア状況を語るセッション(左からゲーゲリー氏、ドラゴミル氏、ペソ氏、スタイン氏。撮影Guendalina Ferri)日本の国土の約4分の1に約1000万人が住むハンガリー。欧州では「鬼っ子」的存在である。
原因は、ハンガリーのオルバン首相による強権政治だ。オルバン氏は反移民・難民、「キリスト教文化の維持」を前面に掲げる、「ポピュリスト(大衆迎合)政治家」の一人。欧州連合(EU)のユンカー委員長とハンガリー出身で在米の投資家ジョージ・ソロス氏を「仮想敵」と見なし、国民感情に訴える政治を実践してきた。2015年、欧州が難民危機に見舞われたときには、流入を止めるために国境に鉄条網の防護柵を築くという荒療治で批判を浴びた。
同氏が率いる与党「フィデス・ハンガリー市民連盟」は下院議席の3分の2を占め、圧倒的存在だ。これを活用して司法権の縮小やメディア規制に力を注いできた。現在、ハンガリーのメディアの90%が直接あるいは間接的に与党の支配下にあると言われている。
一体、その現状はどのようなものか。4月上旬、イタリア・ペルージャで「ペルージャ国際ジャーナリズム祭」が開催され、「ハンガリー:非リベラルな民主主義のメディア」と題するセッションの中でハンガリーのジャーナリストたちが体験を語った。その時の様子を紹介してみたい。
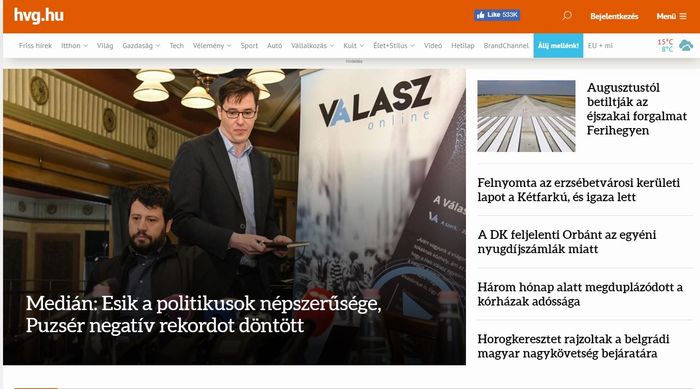 HVGのウェブサイト
HVGのウェブサイト言論組織「プロジェクト・シンジケート」のマネジング・エディターで司会役のジョナサン・スタイン氏が、セッションの口火を切った。「欧米でポピュリストの波が広がっている。英国のEUからの離脱の決定やトランプ米大統領の誕生、ハンガリーの強権政治が典型だ」
「オルバン首相は、ハンガリー国民の声を代弁していると言う。そうすることで、国を2つに分けている。支持者は『愛国者』で、支持しない人は『裏切り者』。徹底的な中央集権化を進め、中央銀行や憲法裁判所を攻撃している」。
オルバン氏は1998年から2002年まで、首相に就任。2002年の総選挙では社会党に敗れたが、2010年に返り咲き、2014年、2018年の総選挙で勝利。現在は第4次オルバン政権を率いる。10年の政権奪回後すぐに新憲法の制定を始め、選挙制度改革、憲法裁判所の権限縮小、報道に対する監督強化などを実施していった。
最初のパネリストは、3年前まで、左派系最大手の新聞「ネープサバッチャーグ」の元副編集長で、今は調査報道のサイト「HVG」のマートン・ゲーゲリー編集長であった。
同氏がハンガリー・メディアの大きな再編の一例として挙げたのが、ニュースサイト大手「オリゴ」の所有者交代事件(2013年)だった。前後して、外国資本や新興財閥が次々とメディアを買収する、閉鎖するなどの現象が起きていた。
2016年10月、ネープサバッチャーグ紙が突然廃刊された時、その理由は政権の強硬な移民政策を批判したため、と言われている。
ネープサバッチャーグが存在していた当時の主要紙は5つ。「3紙は政権に批判的で、2紙は政権寄りだった。今は3紙のみ。2紙は政権寄りで、1紙は批判的だが、部分的には政権に妥協している」。
政権批判を行うメディアが姿を消すことで、「メディアの生態圏が壊れた」とゲーゲリー氏は指摘する。「政権に批判的なメディアが存在し、調査報道が行われるからこそ、権力にプレッシャーを与えることができるが、ハンガリーのようにメディアの大部分が政権を支持していれば、国民は何がよくて何が悪いかを見極めることができなくなる」。
批判をいとわない新聞の規模がある程度大きく、十分な数の人々にリーチできる状態であることも重要だ。そうでないと「権力にプレッシャーを与えることができなくなる」。
「私たちがもし西洋のメディアほどの広告収入を持って、同じようなリーチ力を持っていたならば、おそらく20%人員を増やせると思う。人が20%少ないということは、ジャーナリストは雑務に時間を取られて、外に出て取材をする時間が少なくなることを意味する。市民の声を聞く機会が少なくなる。私たちは実際何が起きているかの感触を失ってしまうし、深みがある記事を連続して書くことができなくなる」。
「情報の欠落」もハンガリーのメディアにとって、大きな課題だという。「政治家ばかりではなく国の様々な組織が私たちと話をしない。必要な答えを得ることができない」。
例えば、ある大衆紙に掲載されたトピックのファクト・チェックをやったときのことだ。ドイツとハンガリーとの両国に関わる、犯罪の話だ。そこでゲーゲリー氏はまず、ドイツの警察に電話した。数分で広報担当者に連絡がつき、事情を検証できた。これをハンガリー側で確認しようとしたところ、ハンガリー警察は電子メールで問い合わせをするように言う。そこでメールを送ったが、返事のメールが来たのは3週間後。しかも、当初の質問への答えではなかった。
公の組織から情報が出て、メディア側がこれを検証できないのであれば、「政府が拡散する、事実に基づかない情報がまん延してしまう」。そして
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください