「不偏不党」求められるBBCの立ち位置は市民の側で「反権力」
2019年05月21日
 ロンドン中心部で、英国のEU残留を支持する人たちが国民投票をやり直すよう訴え、練り歩いた=2016年7月、ロンドン
ロンドン中心部で、英国のEU残留を支持する人たちが国民投票をやり直すよう訴え、練り歩いた=2016年7月、ロンドン英政府は4月8日、児童虐待に関する投稿や、国家の安全を脅かすテロリストグループによる宣伝など、インターネット上に氾濫(はんらん)する「有害情報」を監視するための独立した規制機関を今後新たに設置し、有害コンテンツに対する対策が不十分なプラットフォーム企業や経営者に対しては、その規制機関が罰金や閲覧禁止などを科すこともできるーーとする案を公開した。
ネット上の「有害投稿」を始めとする有害コンテンツについての白書「Online Harms White Paper」の中で明らかにしたもので、「英デジタル・文化・メディア・スポーツ(DCMS)省」と内務省が共同で作成した。英政府としては、ネット上でいま起きていることは健全な民主主義を維持していくとの観点からは到底看過できないとの厳しい態度を打ち出しており、7月1日まで国民の意見を聞くパブリック・コメント期間を経て、早々に最終案をまとめて法制化したい考えだ。
英国ではフェイクニュースを規制・監督するための一元的な組織や法律はこれまで作られては来なかった。その意味で、事実上野放しになってきたネット上の「有害情報」問題について英政府自らが本腰を入れようとしているといえ、フェイクニュースに抗(あらが)うための有効な規制策として注目される一方で、「有害」の定義が必ずしも明確ではないまま法制化に向かうことへの懸念や、「表現の自由を脅かしかねない」との批判もある。
この白書のポイントや、英国のジャーナリズムが取り組むフェイクニュース対策の実態などについて、ロンドン在住のフリージャーナリスト、小林恭子さんに聞いた。
 「きっぱりと離脱するべき」と熱弁をふるうナイジェル・ファラージ元英国独立党党首=2018年9月、「離脱は離脱」運動の集会。小林恭子撮影
「きっぱりと離脱するべき」と熱弁をふるうナイジェル・ファラージ元英国独立党党首=2018年9月、「離脱は離脱」運動の集会。小林恭子撮影――英政府がこのたび思い切った提案を出しましたが、まずはここに至る経緯についてご説明下さい。
「フェイクニュースにどう対抗すべきか。この問題をめぐる議論は、英国では2016年から本格化しました。そのきっかけとなったのは同年6月、英国が欧州連合(EU)から離脱するかどうかを問う国民投票が行われて離脱支持派が勝利したこと、そして同年11月の米大統領選でトランプ大統領が選出されたことが挙げられます」
「とりわけ、EUからの離脱を決めた『ブレグジット』(Brexit)では、一方の残留派が「恐怖のキャンペーン」と呼ばれた宣伝活動を通じて『離脱すれば第3次世界大戦が起きる』などと国民の恐怖心を煽(あお)る作戦に出たのに対し、離脱派は『離脱すれば英国がEUに拠出している週3億5000万ポンド(約518億円)を国営医療制度へ回せる』と繰り返しアピールして対抗、双方が白熱した闘いを繰り広げました」
「ところが、離脱派のアピールが後に事実を誇張した『離脱派のフェイクニュース』だったことが判明し、大騒ぎになったのです。離脱の旗振り役を務めていた英国独立党(UKIP)のファラージ党首(当時)も投票後、『3億5000万ポンド』は間違いであったことを事実上認めるという一幕もあり、離脱派のキャンペーン自体が『フェイクニュース』の様相を呈することになってしまいました。他方、『EU官僚の手から英国を国民の手に取り戻す』という愛国心にダイレクトに訴えた離脱派のフレーズは多くの英国民の心を揺さぶり、『エリート層』だとレッテル張りされた残留陣営が苦戦する一因になりました」
 国民投票の結果を伝える英国の新聞の1面=2016年6月25日、小林恭子撮影
国民投票の結果を伝える英国の新聞の1面=2016年6月25日、小林恭子撮影――英国内の保守系の新聞は、移民受け入れ問題についてはかなり否定的な紙面を作っていました。
「国民投票の少し前の『デイリーメール』を読むと、7500万人ぐらいの人口を抱えるトルコから、150万人ほどのイスラム教徒が英国にどっとやって来るという見出しをつけるわけです。『反移民』というか、移民に対して反感を招かせるようなセンセーショナルな見出しですよね。ただ別にそうした論調が必ずしも人種差別的とはいえない側面もあるという点が大事ではないかと思います」
――といいますと。
「同じ『EU市民』になると、例えば英国内では、移民の人たちも英国民とまったく同じように扱われます。その結果、学校の教室が急にいっぱいになって先生が足りなくなってしまったり、病院の待ち時間が長くなったり、店のウエイターが急に『新欧州人』になったりといった変化が自分たちの暮らす地域で制限なく起きるのです」
「そうした変化が、自分たちの知らないうちに、ブリュッセルにあるEUの官僚たちによって決められていって、それに対して『ノー』ということができない。その意味で、人種差別的な感情による反対というよりも、移民が際限なく入ってきて『自分の人生を自分で決められなくなっていく』ことへの不安が大きいのです。特に英国人はみんなすごく独立心が強いので、そういうことはちょっと我慢がならないという気分があるわけです」
――英国は大混乱の末に「EU離脱」を決めたとはいえ、世界が注目する中、その後は離脱の期限を最大で10月31日まで延ばそうと英国議会内外でドタバタ劇を繰り返す羽目に陥りました。「議会制民主主義の元祖」ともいわれる英国がここまで右往左往する姿は衝撃的でもあります。
「国民投票後、英国民の間には『誤った情報が投票結果をゆがめたのではないか』との疑念が根深く残り、世論の分断がさらに深まってしまったということがあります。これは本当に深刻な事態です。『事実を歪(ゆが)めたフェイクニュースを氾濫(はんらん)させることで英国政治の行方が直接的に左右された』のだとすれば、これはまさに民主主義の根幹にもかかわることです。英国におけるフェイクニュースに対する危機感はこんな経緯があって生まれたという点を押さえておく必要があると思います」
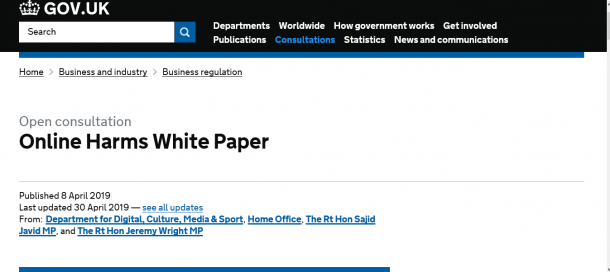 英政府が公開した白書「Online Harms White Paper」
英政府が公開した白書「Online Harms White Paper」――白書「Online Harms White Paper」は、ネットを利用する人々がオンライン上で日々「重大な被害を受けている」事実を「無視できなくなった」と指摘しました。「英国の安全保障や子どもたちの安全を物理的に脅かす違法なコンテンツや行動」がオンラインのプラットフォームを通して拡散されることは到底受け入れがたく、民主主義の価値などを蝕(むしば)むものとして利用されかねないと警鐘を鳴らしてもいます。また、インターネット企業やその経営陣に罰金を科したり、違法コンテンツを掲載したサイトを閉鎖するようネットプロバイダーに命じたりする権限を持った強力な独立規制機関の設置を提案していますね。
「白書の『Executive summary』では、『オンラインをめぐって英国は世界で最も安全な場所であるとともに、デジタルビジネスを起業して成長させる場所としても最適であってほしいと英政府は願っている』とし、だからこそ『デジタル経済はオンライン上の市民の安全を改善するため、新たな取り締まりのフレームワークを早急に必要としている』との考えを打ち出しています」
「ネット上の『自由、オープン性』は維持しつつという点は英政府も押さえていますが、それにしてもかなり踏み込んだ内容です。対策の目玉として提案したのが、ソーシャルメディアやネット企業に倫理規定を課す独立規制組織の設置で、その運営費については規制対象となる企業側が負担するとしています。英国ではこれまで、国境を越えて情報が行き来するネットの世界を一元的に規制・監督する組織はなく、被害への対処はインターネット企業に委ねられてきました。でも、ジェレミー・ライトDCMS相は4月8日のBBCの番組の中で、こうした企業による『自主規制の時代は終わった』と明確に述べました」
――白書が指摘する「有害投稿」を始めとする有害情報や有害コンテンツの具体的な中身はどんなものでしょうか。
「白書が挙げているのは、国家の安全を脅かすテロについての情報や虚偽情報を拡散させること、子どもたちに対する性的虐待、リベンジポルノ(元配偶者や元交際相手らが、復讐(ふくしゅう)目的で相手の裸の画像などを投稿すること)、ヘイトクライム(憎悪感情に基づく犯罪)などです。また必ずしも法的に違法とまではいかなくとも、様々なハラスメント(いやがらせ)やいじめにつながる情報なども英政府としては問題視していることがわかります」
 英国のEU離脱をめぐる2度目の国民投票を求めてデモ行進する人たち=3月、ロンドン
英国のEU離脱をめぐる2度目の国民投票を求めてデモ行進する人たち=3月、ロンドン――これまでも「フェイクニュース対策が甘い」と批判されてきたフェイスブック社やツイッター社などのプラットフォーム企業は、この白書の提案内容に対しておおむね「好意的な声明」を出して評価しているようですが。
「そうですね、フェイスブック社は『新たな規制が必要』との考えを示しています。また、ツイッター社は『オープン、自由というネットの特徴を維持しながら利用者を安全にする適切なバランスが保てる』よう、政府と『ともに作業を進めたい』などとしています。これに対し、英ネット業界の組織『テックUK』は白書を『大きな前進』としながらも、経営陣個人の責任を問う『高圧的な』手法に疑問を投げかけています」
「さらに、シンクタンク『アダム・インスティテュート』のマシュー・レッシュ氏は『言論と報道の自由への攻撃だ』と非難しています。とはいえ、ネット界への規制導入はすでに『タブー』ではなくなっていることを理解する必要があります。フェイスブック社のザッカーバーグCEOが3月末、米ワシントン・ポスト紙への寄稿の中で、悪質な投稿に対し『政府や規制当局の活発な役割が必要だ』と書いていたのが象徴的でした」
――ところで昨年10月、英政府は、グーグルやアップル、フェイスブック、アマゾンの米4社を指す「GAFA」に対する「デジタル・サービス税」を導入する方針を打ち出しましたが、その後何らかの動きはありますか。
「ハモンド財務相が来年4月以降、大手テクノロジー企業を対象とするデジタル課税の導入を発表しましたが、英国では大手の米国企業による法人税の支払いが少なすぎることへの不満が高まっていたということが背景にあると思います。財務相は、世界の売上高が年間5億ポンド(約732億円)以上の事業部門に課税するとしていたのですが、その後、ブレグジットの先行きや英政権交代の可能性も浮上する中、その実現可能性については必ずしも確定しているわけではないと理解しています」
 英議会の下院DCMS委員会が公表した「ディスインフォメーションと『フェイクニュース』最終報告書」
英議会の下院DCMS委員会が公表した「ディスインフォメーションと『フェイクニュース』最終報告書」――他方、フェイクニュースを「民主主義や価値観に対する潜在的脅威の一つ」としてとらえる英議会の下院DCMS委員会(デジタル・文化、メディア・スポーツ委員会)は2017年1月から、フェイクニュースに関する調査を続けてきました。今年2月には、昨年7月の中間報告書に続く形で、「ディスインフォメーションと『フェイクニュース』最終報告書」を公表しましたが、この報告書のポイントはどこにあると考えますか。
「まず最初に、委員会の中間報告では『フェイクニュース』という呼び方を使わないよう提案したということがあります。なぜなら、このフェイクニュースという言葉は『様々な意味を持ち、ニュースの受け手が気に入らないニュースをそのように呼ぶことがある』からだと説明し、代わりに『ディスインフォメーション』(真実を隠すために故意に発信される偽情報)、あるいは『ミスインフォメーション』(誤報)という言葉を使うよう推奨しました。ただ煩わしくなるので、中間報告と最終報告について話す際は、『フェイクニュース』といった時はこの『ディスインフォメーション』を指すということを前提にしたいとお断りしておきます」
「また、委員会は、中間報告の中ですでに『民主主義は危機状態にある』との認識を示し、『共有する価値観や民主主義的な組織の品位を守る』ために、何らかの行動を起こすときが来たとの考えを明確に打ち出してきました。その上で、最終報告書のポイントは、フェイスブックなどのテクノロジー企業がこれまで自分たちは『プラットフォーム』であり、コンテンツ自体には責任がないとの姿勢を維持してきたことに対し、それを認めず、『コンテンツを載せるだけのプラットフォーム企業』か『コンテンツを制作して公(おおやけ)に出すパブリッシャー』なのかを明確にするよう求めた点にあります。さらに、倫理規定を定めるための独立した規制機関の設置も提唱しました」
――何か問題が起きると自分たちは「報道機関」ではなく情報の流れを促進する「プラットフォーム企業」にすぎないと言い逃れようとする企業に対し、「逃げ道」を断つよう迫ったともいえる内容ですね。また、最終報告書は「選挙におけるデジタル広告」という観点からも注目すべき内容があると聞きました。
「英国の選挙管理委員会の調査によると、選挙で使われた広告費の中に占めるデジタル広告の比率は年々増えていき、2017年は42.8%にも達しているということがあるのです。そしてその中で特に大きな位置を占めるのがフェイスブック社です。DCMS委員会は、市場の独占化を監視する英政府の『競争・市場局』に対し、現在は規制がかからないデジタル広告市場で、特定の企業が反競争的な振る舞いをしていないかどうかを調査する権限を与えることを求めました」
「今回の最終報告書は、これまでいろんな問題を指摘されているフェイスブック社に対し、『自分たちには法が適用されないかのように振舞う、デジタル時代のギャングのようになってはいけない』とクギを刺したのです。そうした意味で、ソーシャルメディア企業にとっては大変厳しい報告書となりました」
――ここで話題を変えて、BBCが打ち出している「スロージャーナリズム」というスローガンとその内容について考えたいと思います。これまでのような速報性を重視した報道スタイルではなく、もっと物事の背景や仕組み、歴史的経緯などを深く掘り下げた検証記事や解説、分析記事などを充実させていくというもので、フェイクニュースに抗う「フェイクニュース対策」の一環と受け止められています。
 フリージャーナリスト、小林恭子さん
フリージャーナリスト、小林恭子さん「まず、米国や英国では、ネットメディアやソーシャルメディア以外にもテレビで複数の24時間チャンネルがあり、ニュースが24時間、週に7日、途切れることなく報道されています。英語が国際語であることも手伝い、『1秒でも一瞬でも早くニュースを出す』という至上命題のために世界的な競争をしてきたという点を押さえる必要があります」
「英語で発信されるニュース報道はまさにあふれるほどの量になっているわけです。そんな中にあって、これまでのニュース報道では常識とみなされてきた、『速さや情報量の競争、24時間・週7日という絶え間ない報道体制』のあり方への反省から生まれたのが、BBCを筆頭に他の英メディアも実践している『スロージャーナリズム』という考え方です」
「例えば、BBCのラジオ部門を統括していたヘレン・ボーデンは2016年9月、あまりにも速く情報を出そうと急ぐあまり、『ほんとうは何が問題なのか』を不明瞭にしてしまっているのではないかと問いかけ、『スロージャーナリズム』を提唱しました。日々のニュースを追いかけるテレビは視聴者に対し十分な説明をしていないのではないかという問題意識で、『エンゲージングでダイナミック、かつ、不偏不党、正確さ、専門性、証拠が示された(スローな)ジャーナリズム』なのだとしています」(こちら参照)
「BBC流スロージャーナリズムの実践例としては、立ち止まって考える解説記事に重点を置く『リアリティーチェック』やいわゆる調査報道などが該当します。『何が起きたか』よりも『なぜ』を解明しようとするジャーナリズムということができるでしょう。他方、そんなスロージャーナリズムを実践するために、ニュース部門の統括者ジェームズ・ハーディングはBBCを辞め、会員制のニュースサイト『トータスメディア』を立ち上げました。日に数本、購読者に記事が送られてくる仕組みです」(こちら参照)
――ネット上を流れる様々な情報について、BBCはこれまでどうやってその真偽を確かめてきたのでしょうか。
「BBCは、自局内で受け継がれてきた伝統的なジャーナリズムのやり方で真偽を確かめてきました。例えば、ソーシャルメディア上で使いたい情報を発信している人がいたら、その『裏を取る』ために、当人に直接コンタクトを取ります。複数のBBCのジャーナリストによると、当人に対し、『どのようにしてその情報を得たか』を聞くのだそうです。直接話すというやり方を行うだけで、その情報が『ほんもの』かどうか、大体のところはわかるとしています」
「また、BBCにはロンドンの『報道センター』にニュースの本部があり、上の階には国際ラジオ放送『BBCワールド』のジャーナリストやリサーチャーがいます。それだけでなく、世界各国にいる特派員や現地スタッフとともに、こうした人材が国際的な情報の真偽を確認しているといわれています」
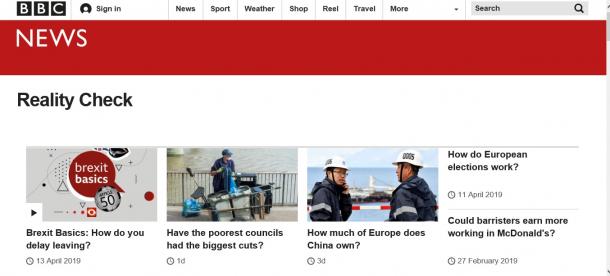 BBCの「リアリティーチェック」は、取り上げてほしいトピックを常時募集している(BBCのウェブサイトより)
BBCの「リアリティーチェック」は、取り上げてほしいトピックを常時募集している(BBCのウェブサイトより)――その一方で、スロージャーナリズムの実践として、またフェイクニュース対策の一環としてBBCが取り組んでいる「リアリティーチェック」とはどんなものでしょうか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください