未来は誰にも分からない。未来を予測するよりは、何か起きた時の対策を考えた方がいい
2019年06月29日

尾崎 裕(おざき・ひろし)
大阪ガス会長
兵庫県宝塚市出身。大阪府立北野高校卒、東京大学工学部計数工学科を卒業して、1972年大阪ガス入社。企画部国際室長、原料部長などを経て、2005年に常務取締役、2008年4月に代表取締役社長、2015年4月から代表取締役会長。2015年12月に大阪商工会議所会頭に就任したほか、2025日本国際博覧会協会副会長、文楽協会理事長を務める。
毎年10月19日の創業記念日に、社長が1時間ばかり話すことになっています。2008年に社長になってから何を話すかを考えていましたが、毎回自分で考えてもあんまりおもしろいことも言えないから、何か本のトピックスをテーマに話をしたらどうかと思うようになったのが、東日本大震災のあった2011年でした。
アマゾンでいい本がないかと探していたら、「ブラック・スワン 不確実性とリスクの本質」(ナシーム・ニコラス・タレブ著、邦訳はダイヤモンド社刊)の英語の原書(「The Black Swan」)を偶然見つけたんです。
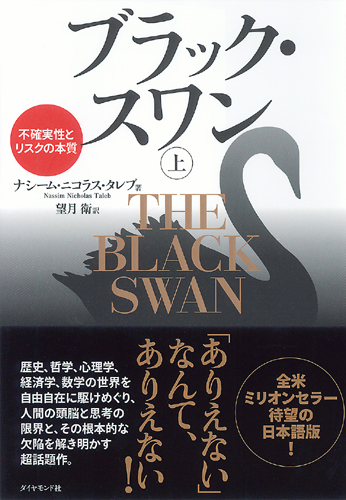
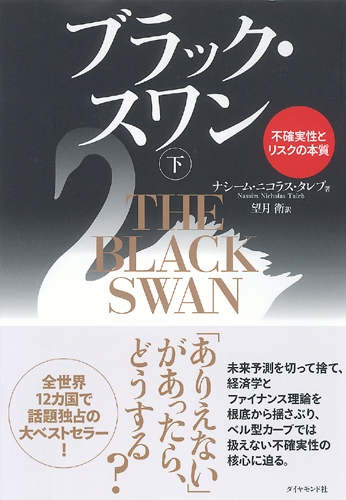
大震災にも触れられそうだし、おもしろそうだなと思ってちょっと読んでみたら、本当におもしろい。でも、ものすごく難しい。難しいというのは、内容もそうだけど、文章がめちゃめちゃ難しい。知らない単語が山ほど出てくる。
この人、哲学的やからね。辞書を引きながら読みました。日本語訳もあるけれど、こんな読みにくい本は、日本語訳で読んだらもっと混乱すると思って、原書で読むことにしました。同じ著者の本がほかに3冊ほどあって、買ってはいるけれど、この本と同じで読むのがしんどいから、まだ読んでいません。
書いてあることを一言で言えば、「未来はわからない」。それに尽きると思う。そこまで人間の知恵が及ばないということ。5月に、「ケ・セラ・セラ」で有名なアメリカの歌手、ドリス・デイが亡くなりましたが、その歌詞の「The future’s not ours to see」(先のことはわからない)。未来は見えない、ということです。
この本をもとにして、2011年の創業記念日に「Be a Game Changer」という話をしました。本に出てくる話を紹介しながら、やはり世の中は何が起こるかわからないし、わからないことをわかろうとするのは、無駄だろうという話をしました。
「未来がわからない」という例には、この本に出てくるアメリカの七面鳥の話をしました。
七面鳥の側から見れば、飼い主はひなのときからえさを与えてくれて、運動をさせて、きれいにして、3年弱一生懸命育ててくれた。飼い主はなんて優しいんだ、自分はなんて幸せなんだと千日間思い続けるわけです。
ところが、七面鳥を食べる感謝祭の前の日に殺されてしまう。それが、七面鳥にとっては「ブラックスワン」です。そんなことになるとは思ってもいませんから。
スワンは、日本語で「白鳥」と訳してるように、ヨーロッパ人にとっても白い鳥に決まっているというのが鉄板の常識だったのですが、オーストラリアに行ったら、黒いスワンがいました。その鳥はオーストラリアに人間が来る前からずっといたのですが、ヨーロッパ人には初めて目にする鳥だったのでびっくりです。これがもとで、いない、起こらない、と思っていたものが急にあらわれることをブラックスワンと呼ぶようになりました。
滅多に起こらないが、それが起こるとものすごいインパクトがある。東日本大震災もブラックスワンでしょう。まさか津波が堤防を越えることはないと思っていたのですから。
七面鳥からすれば、本来なら自分でえさを探さないといけないし、野原を歩いていたら天敵に襲われるかも知れない、それに比べたらなんと幸せなことか。そうした幸せが、ひなのときから、995日、996日と続いているから、その後も続くと思っていたのでしょう。感謝祭で食べられるとは知らないまま。
これは人間も同じで、あしたも生きていると思って毎日生きているけれど、いつ死ぬかわからない。人間が七面鳥と違うのは、自分はいずれ死ぬと知っていることです。そこは、人間には知識があるということであって、七面鳥とは違う対応ができるはずですよね。
急に明日がなくなることは、会社にも起こります。それは3.11のような大災害で会社がつぶれることもあるだろうし、まったく違うことでつぶれるかも知れません。
自分のことで考えてみたら、分かりやすいかも知れない。あなたはきょう生きているよね、きっとあしたも生きているよね、きょうは楽しいことがいっぱいあるよね、あしたもきっと楽しい1日だよねって、思っているでしょう。でも、いつまで続くんでしょう。だって、人間は必ず死ぬんですから。
今度は会社に置き換えて、会社は今儲かっているよね、従業員はハッピーだし、お客さんもハッピーだよね、たぶん、あしたもそうだよねと。じゃあ、太陽が東から昇るのと同じようにずっとこのまま続くんでしょうか。「人間は100年生きられるから、そのくらいは」なんて考えていると……。
たぶん、人間は本質的に未来のことは考えられない。人間はわからないし、考えられないんだと思うんですね。
だから、たとえば、私が「30年先の君は」って聞かれたら、どこの墓で眠っているかなんてわからない。でも、それは本当にわからないんだから、考えても仕方ない。きょうもあしたも元気、でも、1週間後は元気じゃなくなるかも知れないし、3年後には病気になるかもわからないというときに、では、今何をすればいいか。たくさん貯金をして、3年後に病気になっても治せるようにしましょうという考え方もあるし、きょうからお酒をやめます、たばこをやめます、食べ過ぎをやめますとか、いろんなやり方があるでしょう。それをやってみたら、ひょっとしたら、ポジティブなことになるかも知れない。人間にできることはこんなことしかないんです。
でも、この本によると、理屈としては、3年後の世界は今やっている、ものすごくちっちゃなことが影響する、と言うんです。
本の中では、チョウがインドで羽ばたいたら、3年後にアメリカでハリケーンが起こるというほかの人の論文をひいています。要するに、ものすごく小さなパラメーターの変化、この場合、インドのチョウの羽ばたきが、ずっと因果律で巡っていくと、3年後のアメリカのハリケーンになるというわけです。それはチョウの羽ばたきなのか、カエルのげっぷなのか、だれかのおならなのかも知れないわけです。
物事の因果は複雑系だから、たとえ物理の法則が厳密に成立しても、圧倒的にパラメーターが多いし、そのパラメーターの数字が正確には把握できない。そうなると、予測はできないというのとほとんど一緒でしょう。そうであれば、ハリケーンを防ぐには、チョウの羽ばたきをやめさせるのではなくて、ハリケーンが襲って来たときに被害を減らすために避難するとか、暴風雨へ備えておくとか、何らかの対策をとる方が現実的だということです。
著者は、ハリケーンが発生するメカニズムを詳しく知って、正確に3年後を予測しようなんてことはやめるべきで、やっても無駄だと言うのです。こんな感じで結構哲学的だし、数学に関する話もしているんですね。
ずっと続くと思っていた会社がつぶれたケースとして一番印象に残っているのは、銀塩写真のフィルムを作っていたアメリカのコダックです。
コダックは2012年に倒産しました。今は別の事業をする会社に生まれ変わっています。この話は、本に出ていたのではなくて、日本のコダックにいた人に聞いたのですが、「コダックほどいい会社はなかった」と言うのです。
要するに、従業員の待遇がめちゃくちゃ良かった。写真フィルムの世界ではずっとリーディングカンパニーで、少しずつフィルムの性能を上げていったとしても同じ技術ですから、儲かってしょうがなかったと言うんですね。フィルムは、写真を1回撮るごとに確実に消費されるし、現像しない限り写真が見られないから、必ず現像するでしょう。それも自分たちのところで現像サービスをするというビジネスモデルだったんです。
そこに、フィルムを使わないデジタルカメラが出てきた。初めはコダックも取り組もうと考えたんだけれど、出始めのころのデジカメは値段は高いのに性能がそんなに良くなくて、色の再現性はいまいちだし、撮影するときの反応はよくないし、記録するメモリーの容量も限られている。性能もコストもフィルムの方が圧倒的にいいから、こんなものは役に立たない、研究する意味がない、と考えたんですね。
もっと身近なケースもあります。大阪の十三(じゅうそう)にあった手回し計算機メーカーのタイガー計算機。その手回し式の計算機は、うちの父親が若いころ、仕事で平均を出したり、分散を出したり、そんなことを計算するのに使っていました。僕が入る前の大阪ガスでもみんな使っていたはずです。それが電卓が出てきて、手回しの計算機はなくなっちゃった。歯車の塊のようなもので、機械的にはすばらしい。とはいえ、計算するなら、電卓の方が圧倒的に速い。
世の中というのは、こういうふうに動くんです。写真を撮る道具としては、フィルムやカメラの性能を上げてきたけれど、デジカメにとって代わられた。計算する道具は、手回し式の計算機から電卓に置き換わった。今では、スマホでできるようになった。グーグルなどが自動運転を実用化しようとしていますが、車の性能を上げるというよりは、運転しなくていいという別のサービスになるでしょう。
世の中、このビジネスさえやっていたら、未来永劫儲かってしょうがないと思うようなビジネスであっても、新規参入者が来て、しかも今までなかったモノ、商品なのか、やり方なのか、それとも全然違うもの、今までの商品の魅力をまったくなくしてしまうようなものが出てきて、不滅だと思っていたビジネスがころっと変わってしまうことがあるのです。
大阪ガスは都市ガスという事業を110年以上続けてきて、やればやるほど事業としては進化していくのですが、つまりは性能を上げてきたのですが、それだけで本当に大丈夫か、ということです。
うまくいっているときでも、惰性に流されることなく、世の中をよく見て、何か新しい動きがあったときにはちょっと想像を膨らませて、こういうふうになったら脅威だねっていうのをきちんと意識しておく。仮に脅威が現実になったときは一体どういうことが我々に起こり、どうすればいいんだということをある程度は考えておかなきゃいけないと思うんです。そうしないと、実際に起こったときにパニックになってしまう。
都市ガス事業はどっちかといえば、すでに事業としては確立されているけれど、環境の変化に対応するだけではなくて、自分から変化を起こさないといけません。そう考えていかないと、未来はしんどくなる。阪神・淡路大震災でも、東日本大震災でも、あの時の経験をもとに新たな備えをしていますから、今なら、あれだけ大きな被害にはならないと思います。だから受け身ではなくて、自ら変えていくという意味で「Be a Game Changer」と呼びかけたんですね。一人一人がゲームチェンジャーになるように頑張ろうという話をしたんです。
大阪ガスの中で、いろんなことにチャレンジする動きもあったから、そういうのを抑えるんじゃなくて、もっともっと伸ばしていかなきゃいけないという意識もありました。
「未来はわからない」という話をしてきましたが、一方で経済学者は世の中のことが説明できる、予測できると言います。本当なのでしょうか。僕がこの本の中で最も気に入っているのは、「経済学者はうそをつく」と書いているところです。
なぜうそつきか。経済学では、経済活動を説明したり、予測したりするためにモデルを作りますよね。それは、確率を使って考えていますが、いくつかの欠陥があって、まず、経済学とか社会科学のモデルに出てくる人間は合理的でシンプルに行動するという前提になっていますが、実際はそうではないでしょう。
経済学の世界では、人間が合理的な行動をすると決めて、正規分布をもとに方程式を作って、確率を使って予測します。正規分布は、人の身長とか、テストの点数などの分布を示すもので、真ん中あたりが多くなるので、分布は左右対称の山のような形になります。ほとんどのケースが、真ん中から一定の幅の中に納まるから、「この投資は95%安全」などと言っているわけです。
しかし、現実には地震とか、マーケットのクラッシュとか、正規分布からはみ出したことが起こります。正規分布なら、1億回に1回起きることの期待値は100、つまり想定の範囲内なのですが、地震とかマーケットのクラッシュのような正規分布を外れるものは起こったときの影響が桁違いに大きいので、期待値が1000とか1万とかになる。想定外に大きなことが起きるのです。著者は、それが世の中じゃないか、経済学者がいっぱいモデルを作っても役に立たない、それどころか、害になると言うのです。
モデル作りは、エコノミストや証券や債券などのアナリストが得意げにやっているけれども、それは本当に大丈夫なのか、と著者は言います。投資判断などで、問題はまず起きない、起きても大丈夫、「99%セーフ」というのは、実は何か起こったときに一番危ない、とも。著者はニューヨークのウォール街で、長くデリバティブのトレーダーをしていて、思いもしないクラッシュを目の当たりにしているからです。
そういう意味で、経済学者はうそつきだと筆者は言い、サミュエルソンなんて最悪だとか、サミュエルソンにノーベル経済学賞を与えたスウェーデンの科学アカデミーもとんでもないと、言っているのです。
では、なぜ経済学者はモデルを作って予測をするのか。それがビジネスになるからですね。
ビジネスになって、それが家元制度みたいになって、宗家がこうやったらみんなそれに従わなければいけないとか。だいたい社会科学に自然科学の理屈をあてはめるのが思い上がりだとか、無知がなせるわざだとか筆者は言っています。要するに、経済学者はもっともらしく説明するために自然科学の理屈を持ち込んで、合理的だと思わせていると悪口を言っているわけです。
最近、この本を読み返して思ったのは、もし、経済モデルが正しかったら、アメリカは中国と貿易紛争を起こさなかっただろうということです。その方が双方の利益が大きくなるはずですから。でも、実際に紛争は起きたし、ここまで大きくなるとはだれも予測していなかったんじゃないでしょうか。そういう点では、トランプ大統領はブラックスワンだったんですね。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください