津田大介が七つの提案「スロージャーナリズム」機能高めて生き残れ
2019年07月18日
 ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さん=撮影・吉永考宏
ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さん=撮影・吉永考宏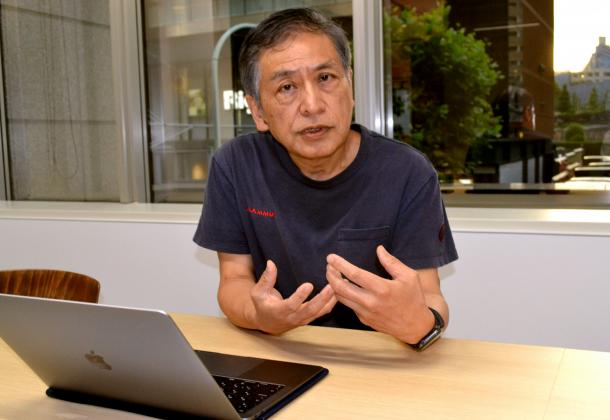 スマートニュースフェローの藤村厚夫さん
スマートニュースフェローの藤村厚夫さんジャーナリズム活動をめぐる様々なフェイズでAI(人工知能)を導入する動きが活発化している。
ネット上の膨大な情報の中から、災害や事故などニュースの端緒となる情報を人間に代わってAIが見つけ出す→定型があるジャンルについて記事生成を「AI記者」が行う→出来上がった記事をAIが校正・校閲する→記事に見出しをつけるなどの編成作業をAIが担当する→「AIアナウンサー」がラジオ番組などで原稿を読み上げる→読者コメント欄についてAIが事実上の危機管理を行いながら運営する→事実かどうかを検証するファクトチェック作業をまずはAIが行って人間に引き継ぐ……。作業工程の始まりから終わりまで、AIを積極活用した「報道の機械化」はもはや不可逆の流れだ。
新聞やテレビなど既存メディアの経営が悪化する中、「AIに任せられる部分はすべてAIに任せてコスト削減を図り、その分負担が軽くなった記者は取材を深めて本来ヒトにしかできない『より創造的な仕事』に集中しよう」――。「AI時代のジャーナリズム」を考える際のコンセプトを表現すればこんな感じになるだろう。
そして「報道の機械化」が進めば進むほど、「一人のジャーナリストとして今何をすべきか」「メディアとしてどうあるべきか」が今まで以上に鋭く問われることになるのは必至だ。
ジャーナリズム活動にAIを採り入れることと、フェイクニュースに抗うことは直接的には関係がない。とはいえ、大量の情報の中から「フェイクの疑いがある情報」を機械的にピックアップしていくという点ではフェイクニュース対策としてもすでに有効に活用され始めている。
また、フェイクニュースを無批判に信じ込む結果として社会の分断が進み、自分が見たい情報しか見えなくなる状態に陥る人々が増えるなど事態が深刻化する昨今、「アルゴリズム」(コンピューターで計算を行う時の計算方法)を使ってそうした人々を何とか「多様な言論」に触れさせ、分断解消に一役買おうといった取り組みも始まっている。
スマートニュースフェローの藤村厚夫は「AIがジャーナリズムのあり方に全方位的に影響を与えることはもはや間違いのない段階に入った。私たちを『メディア大航海時代』へと導く巨大な原動力がテクノロジーだ」と強調する。
また、ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介は、メディアが新たに「スロージャーナリズム」的機能を打ち出していくべきだと提言。「AI時代のジャーナリズム」として今のメディアが生き残りをかけて新たに挑戦すべきこととして七項目の提案をする。
ジャーナリズムとAIの「蜜月」関係が今後さらに深まり進展することが確実視される中、今のジャーナリズムは2050年までにどんな変容を遂げるだろうか。
「AI時代のジャーナリズム」をめぐる具体的な動きをみていく前に、まずは日本でも認知度が上がってきた「ファクトチェックとは何か」という点を押さえておこう。
政治家の発言やメディアの報道をはじめ、ソーシャルメディア上にあふれる真偽不明の情報を検証してその結果を社会に公表する「ファクトチェック」(真偽検証)。日本では2017年6月、弁護士の楊井人文(ひとふみ)や藤村らが各界の識者に呼びかける形で初の本格的なファクトチェックを行う個人や組織をネットワークする団体「ファクトチェック・イニシアティブ」(FIJ)を仲間とともに旗揚げし、18年1月にNPO法人化された。
「私たちは、事実と異なる言説・情報に惑わされ、分断や拒絶が深まるような社会を望んでいません。そうならないためにも、ファクトチェックをジャーナリズムの重要な役割の一つと位置づけて推進し、社会に誤った情報が拡がるのを防ぐ仕組みを作っていく必要があると考えました」。FIJは設立の趣旨にそううたい、「真偽を検証する活動の量的・質的な向上が、誤った情報に対する人々や社会の免疫力を高め、ひいては言論の自由を守り、民主主義を強くすることにつながる」とアピールした。
FIJの発起人の一人で理事兼事務局長を務める楊井はこう強調する。
「ファクトチェックはそもそも『フェイクニュースを暴く』ことを目的としたものではなく、あくまで情報や言説が『事実と根拠に基づいているかどうか』をチェックするためのものです。情報や言説の中に含まれる『客観的に検証可能な事実のみを対象に検証作業を行う』のであり、その情報を発信している個人の意見や見解の是非を評価するのではないということがポイントです」
 FIJ理事兼事務局長で弁護士の楊井人文さん=撮影・吉永考宏
FIJ理事兼事務局長で弁護士の楊井人文さん=撮影・吉永考宏楊井がファクトチェックに関わるようになったきっかけは2011年3月11日に起きた東日本大震災だ。直後に大混乱が続く中、楊井は放射性物質の拡散を予測する「SPEEDI」(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)をめぐる大手メディアの報道を見ていて「これはおかしい」と強い疑問を持った。100億円以上の国費を投入して開発された予測システムのSPEEDIは、運用機関の原子力安全技術センターが実際には文部科学省などからの依頼を受けて稼働させて様々な予測計算を行っていたにもかかわらず、そうした情報が迅速・的確に国民に知らされることはなく、情報の混乱に輪をかける形となっていたからだ。
3.11をめぐってネット上の真偽不明の情報に人々が翻弄(ほんろう)される様子を目の当たりにした楊井は「はたしてメディアはこれまでも正確な報道をしてきたのか」との疑問を深め、日本報道検証機構を設立。マスコミ誤報検証・報道被害救済サイト「GoHoo」を開設した際もこのSPEEDIに関する報道を真っ先に検証した。
その後、楊井はFIJ設立に向けて動き、2017年6月の立ち上げとともに理事兼事務局長に就任。同年秋の衆議院解散に伴う総選挙では4つのウェブメディアとともにファクトチェックを実施したほか、2018秋の沖縄県知事選では6つのウェブメディアと琉球新報が参加する形でファクトチェックを行った。
「ファクトチェックの課題の一つは『足の速い』ニセのニュースの拡散をいかに早期に食い止めるか」「その点、人の力だけに頼ったファクトチェックには量的な限界がある」――。ファクトチェックにAIを導入する必要性を当初から指摘していた一人が、FIJ理事でもあるスマートニュースフェローの藤村だ。
FIJでは東北大学大学院の乾研究室や日本報道検証機構、スマートニュースと協力し、AIを使ってフェイクニュースの疑いがある「疑義言説」を検知するシステム「Fact-Checking-Console」(FCC)の共同開発を進めた。そして2018年9月にはファクトチェック・プロジェクトでの運用開始にこぎつけ、同年9月の沖縄県知事選プロジェクトでは実践的な運用に取り組んで成果を上げた。
この時、運用されたのがFCCだ。
FCCの仕組みとはーー。楊井や藤村によると、ネット上にあふれる玉石混淆(こんこう)の情報や言説の中で、例えば「この情報はデマではないか?」との疑問を持った人がツイッターでそうつぶやいた場合、そのつぶやき情報をAIが「自然言語処理技術」を使って検知して自動収集。そうして集められた情報の中から「より疑わしい可能性が高い情報」(端緒情報)を絞り込み、上位から点数をつけてスコア化して表示する。
つまり、インターネット上の膨大なニュースの中から信憑(しんぴょう)性が疑われる情報を抽出する「前処理」作業はAIを使ったシステムに任せ、その後はファクトチェックを担当する人間の力で「ファクトチェックの対象とすべき情報」だけを抽出、それらを徹底検証していくというハイブリッドな流れだ。
こうした作業を繰り返すことで、AIは「専門的にファクトチェックすべき価値のある端緒情報とは何か」を機械学習し、データを蓄積しながら精度を高めていく。その結果、ファクトチェックを担当するファクトチェッカーにとっては作業の大幅な効率化が図れるため、絞り込まれた個別案件についてより深く調べたり記事化したりすることができるというメリットが生まれる。また、これらのワークフローや情報データベースを整備していく計画で、ファクトチェックカーが取り組む作業のさらなる効率化が図られると期待されるという。
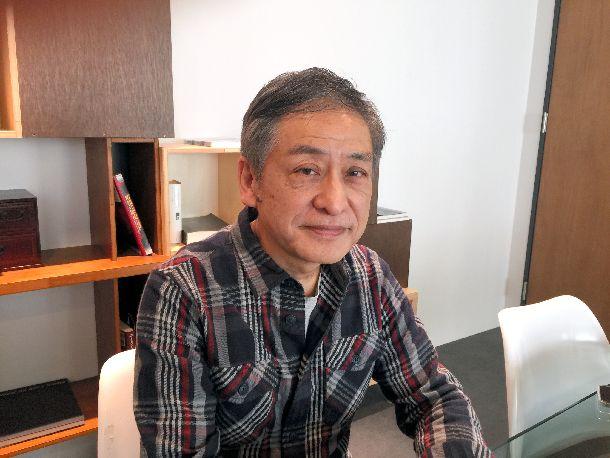 スマートニュースフェローの藤村厚夫さん
スマートニュースフェローの藤村厚夫さん「ファクトチェックされた情報をその後どうするかが大きな課題」。藤村はそう力説する。そんな問題意識のもと、得られたファクトチェック情報がそのまま埋没しないようにと、FIJでは現在、スマートニュースが中心になって「オープンに活用可能なシステム向けのデータベース」の整備と、フェイクにまつわる様々な情報を収納したデータベースから外部のプログラム(例えば検索エンジン)などが自動的にデータを取り出せるようにするための「API」(Application Programming Interface)の整備を進めている。これが進めば、人間が読むファクトチェック情報だけでなく、検索エンジンなどへの反映も自動化されたりするという(すでにグーグルは、ファクトチェック済み情報が検索結果に反映される手順を公開している)。
「ファクトチェッカーがていねいに調べた結果を誰も使わないというのでは価値がない。私たちはファクトチェックされた結果をなるべく多くの人に公共性の高い情報として提供していく必要があると考えている」と藤村は話す。
「現時点ではFCCのほうが先に動いていてデータベースのほうはまだできていないが、技術的な問題があって遅れているのではなく、データベースを運用して使ってくれる人を見つける作業が追いついていないだけ。このデータベースはスマートニュースが主導して構築するつもりだが、別にスマートニュースのものにする必要もなく、あるいは『ファクトチェック・イニシアティブ』のものでもなく、広く社会のものにしたい。その意味で、ゴールはあくまで『オープンなスキーム作り』です。グーグルやフェイスブックなど様々なところで情報提供に携わる企業の参加を求めつつ、誰が使ってもいいようなデータベースとしてどのような形で運用できるかという課題を今後解決していきたい」
 Media×Techのホームページ
Media×Techのホームページ藤村の責任編集で、スマートニュースはメディアをめぐる様々なテクノロジーを紹介しながら「テクノロジーを活用した次世代のメディアをどうやって創りだしていくか」を考えていくブログサイト「Media×Tech」を開設した。
1990年代を株式会社アスキー(当時)の書籍および雑誌編集者として、またロータス(現日本アイ・ビー・エム)ではマーケティング責任者として過ごし、その後はアイティメディア代表取締役会長として同社をマザーズ上場に導くなど「紙媒体とウェブメディアの先頭」を走り続けてきた藤村。そんな藤村はブログ開設にあたり「メディア大航海時代に向けて」と題したメッセージを公開。「オールドメディアであろうと、スタートアップであろうと、テクノロジーを味方に引き寄せることで『大航海時代』へと乗り出せるはず」だと強調した。
例えば2050年、メディアやジャーナリズムはどうなっているだろうか。藤村はいう。
「ジャーナリズムが例えば30年後にどうなっているかという問題は、そもそもメディアやジャーナリズムが30年後に人々から何を求められているかという話でもあります。最低限、世の中にいま何が起きているかを伝えていく役割が今後もジャーナリズムに求められ続けていくのであれば、AIができることでいうと、『そもそもどれが信用できる情報であるか』をめぐるサポートについて、今後はより大変重要な役割をはたしていくでしょう」
「もっと本質的なところで『この情報をどう考えるべきか』といった、人間のセンスや能力や深い知識を駆動させなければできないことについてはやはり人間が行うべきですが、その手前で、ニュースの妥当性や信頼性を判断する一人ひとりのジャーナリストをいわば下支えしていく役割はAIが担うべきだし、前処理をするためにAIは非常に有効だと考えます」
そしてこう付け加える。
「情報を見つけて記事を生成し、それを人に伝えていくプロセスについていえば、大きな設備や大きな組織、ビルとか輪転機とかはどんどん要らなくなっていくと思いますので、いい意味でも悪い意味でも、情報の発信者は〝個人〟に近づいていくでしょう。ただ同時に、良質なコンテンツを生み出せる人というのはどこまでいっても少ない。その力にはやはり希少性があって、そういう人たちを食べさせていけるような仕組みをAIが裏支えするという感じだと思います」
 ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さん=撮影・吉永考宏
ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さん=撮影・吉永考宏「AI時代のジャーナリズム」として今のメディアが生き残りをかけて新たに挑戦すべきことは何だろうか。ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介は七つの提案をする。
順不同ではあるが、まず一つ目は「ツイッターの短い文面から抜け落ちた文脈をリアルタイムで解説できる記者を育てる」という提案だ。
ここ数年、フェイクニュースの盛り上がりに対抗する形で事実かどうかを調べるファクトチェックが注目を集めているのは先述した通りだが、津田はそのファクトチェックのフェイズをある意味で今より一段上に押し上げる必要性を指摘する。
「例えば大事件が起きて話題になるといったことは、今では新聞やテレビではなく、ソーシャルメディアから火がつくといった流れにほぼなっています。SNS上のそうした話題を新聞などが取り上げるころには、すでにかなりの数の専門家がツイッターなどを通して議論をし尽くしているといった感じがあります。その際、『フェイクニュース』とまではいわないにしても、SNS上で誰かが何かを問題提起した時点で、『その内容はミスリーディングで誤解を与えるよね』といいたくなるケースもたくさんあるのが実情です」
そんな時に、ネット上のフェイクまがいの言説に対抗してファクトチェックを行った上で、リアルタイムでエビデンス(論拠)を出しながら議論を補正していくという役割が新聞社にとって今後新たに必要になってくるのではないかーー。それが津田の提案だ。
「何かの問題をめぐって一定の世論が形成されてしまう前に、『この問題を考える場合はその前提としてこういう知識が必要だよ』ということをできるだけ早くネットに出していく作業が大事ですが、それはやっぱりAIだけでは無理で、人じゃないとできない。だからこそ、そういうことができる人材を社内で育てていく必要があると思う」と津田。新聞社の組織として「このジャンルだったらこの記者に聞け」といった深い専門知識を持つ専門記者の割合を今よりもっと増やしていけばそういうニーズにも対応しやすくなるのではないかという。
いわば「アクティブなファクトチェック」として、専門記者がファクトに基づいてリアルタイムでネット上の様々な情報を解説していくような組織を新たにメディアの中に作り、若手でネット情報の流れに長(た)けた人を積極的にその組織に配置していく試み。そうした組織は今のどの新聞社にも見当たらないので、そういった人材の育成と組織再編を具体的に進められるかがカギだと津田はみる。
「何しろツイッターは140字しか書けませんから、何か問題提起したとしても、例えばその問題の裏側や歴史的経緯などいろいろな文脈が抜け落ちてしまう。その抜け落ちる文脈を新聞社側がリアルタイムで補正して適切に解説していく。ただ単に事実関係を確認するというファクトチェックの一段上を行くような、そんな『スロージャーナリズム』的な機能というのは今後さらにニーズが高まっていく気がします」
 ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さん=撮影・吉永考宏
ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さん=撮影・吉永考宏二つ目は、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください