全国へ広がりを見せる「ワインツーリズム」。キーマンが語る地域ビジネスの興し方
2019年10月01日
 大木貴之さん提供
大木貴之さん提供「山梨といえばワイン」というイメージをお持ちの方ならば、山梨県民は日常的に地元のワインをよく飲み、たくさんの方がワインを求めて来県するのが当たり前だと思われているでしょう。特に、ぶどうの収穫やワインの醸造が行われる今の時期であれば多くの来県者がワインを求め、ワイナリーをめぐり、ワイン三昧な週末を楽しむ……。
確かにここ数年、山梨ではこうした光景を目にします。山梨県の県庁所在地である甲府駅周辺には、山梨県産ワインを飲める飲食店が立ち並び、ワイナリーが集積する甲州市勝沼では、週末たくさんの人が訪れ、飲食店をはじめ、酒販店、宿泊施設、タクシー会社など地域のお店が潤っています。しかし、ほんの10年程前までこの光景は日常的ではなく、地域の人たちが連携して、こうした新たな人の流れをつくり上げていったということをご存知でしょうか?
 大木貴之さん提供
大木貴之さん提供 この地域における新たな消費の行動を起こし、定着させるきっかけとなった一つが、私たちが始めた「ワインツーリズム(R)」という民間の活動です。2008年,
地域資源であるワインを活用したイベント「ワインツーリズムやまなし」を官民連携で立ち上げ、ワイナリーや地域住民ら多様なステークホルダーを巻き込みながら10年間、民間運営で持続させてきました。
これ以前のワイン関連のイベントは、一つの場所にワイナリーが集まり、ワインを飲むことを重視したものでした。またツアーとなると参加者であるゲスト側の満足を追求したものが多く、ツアーに組み込まれない限り、ホスト側となる地域の人たちに大きなメリットとなるものではありませんでした。
「ワインツーリズムやまなし」は、ワインの試飲に加えて、ワインづくりの現場に足を運ぶ機会を設け、ワインを取り巻く環境や、ワインがボトルに入るまでの過程を自ら体感して理解を深めてもらう場を提供してきました。
 大木貴之さん提供
大木貴之さん提供具体的には、ワインを醸造する人やぶどうを栽培する人たちとの会話、ぶどう畑のある風景とワイン産地の歴史や風土、そして地域の食文化などといった体験です。
ホスト側である地域住民には、イベントによってワイナリーのある地域に行って楽しむという観光を促すことで地域への人の流れを生みだし、自分たちの生業が持続しやすいような、稼げる地域に変化させていくきっかけづくりをしてきました。
それでは、なぜこうした活動が始まり、ワインツーリズムとはどのようなイベントで、結果的に地域に何が起こってきたのでしょうか。
2004年、仲間とともに「ワインツーリズム」の活動を始めたのですが、私自身は2000年に東京都内から地元山梨に戻り、当時シャッター街化していた甲府駅周辺で、「まずは人が集まる場をつくろう」と飲食店をオープンさせました。当時の甲府駅周辺は、郊外の大型店に人の流れを奪われ、著しく疲弊していました。勝沼などのワイナリーを巡ることも一般的ではなく、ワイナリーはワインを製造することが仕事であって、週末の土曜日曜はお休みというところがたくさんありました。
こうした状況下で、誰かが何か変化を起こしてくれるのを待つのではなく、自身が学んできたことを地域に還元することで、地域の環境を少しでも変えていこうと始めた私の店には、デザイン、写真、イラスト、編集など様々なスキルを持った人や、現状を変えて山梨をよくしたいと考える人たちが出入りするようになってきました。彼らとともに「日常的に山梨県産ワインを楽しめる街」にしていこうと「ワインツーリズム」という活動をスタートさせ、私のお店では「山梨県産のワインしか飲めない」ことを徹底しました。
「山梨県で山梨県産ワインを日常的に飲むのは当たり前じゃないか?」
そう思われるかもしれませんが、必ずしも地域の名産品が地域で楽しまれているとは限りません。山梨県産ワインはお土産としては有名でしたが、つい数年前までは地元山梨でもワイン醸造に関わる地域を除けば、なかなか日常的に地域住民が飲むものではありませんでした。それゆえ山梨県産ワインを提供する飲食店も、積極的に販売する酒販店も多くはありませんでした。
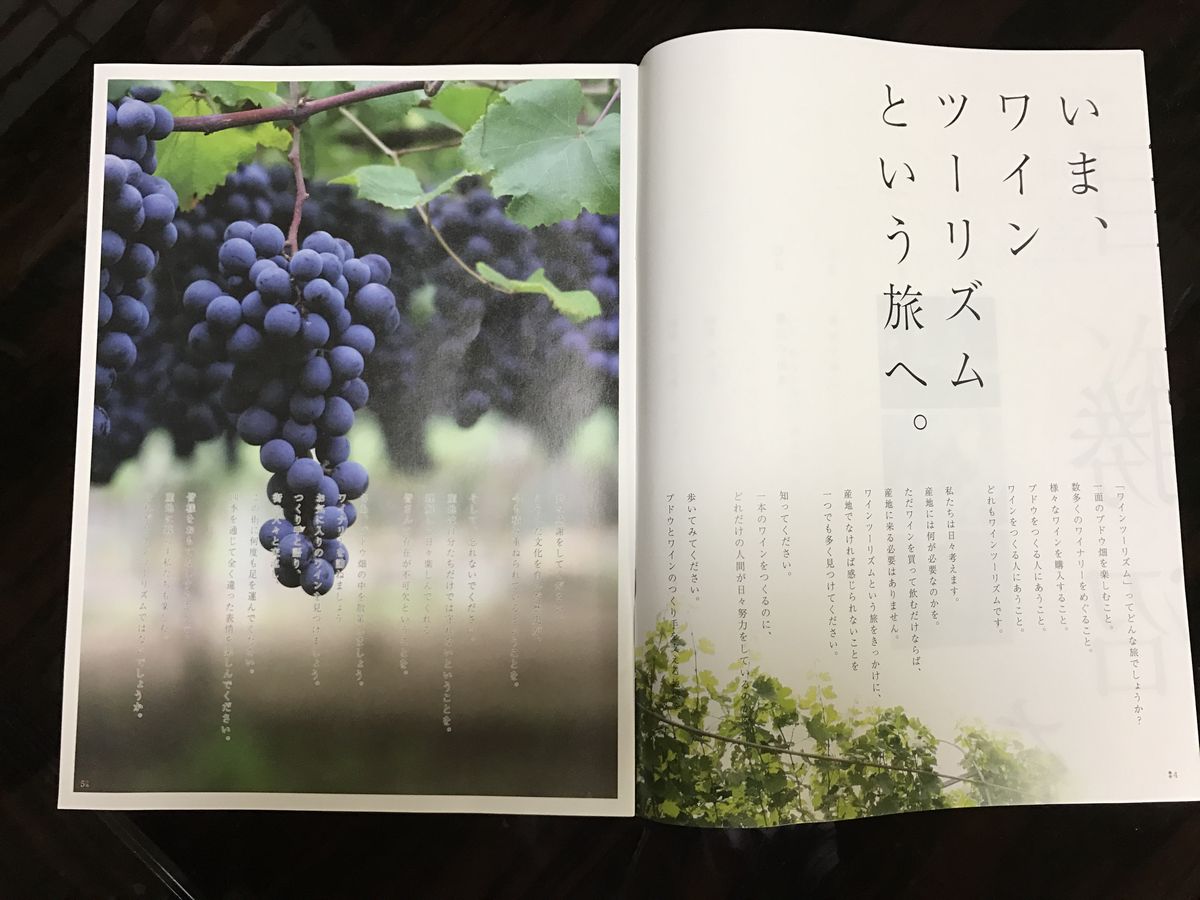 大木貴之さん提供
大木貴之さん提供私たちがやっているのは、地域資源であるワインの販売促進事業ではなく、「地場産業の三次産業化」です。ものづくりで止まってしまっている地場産業を、地域の他の業種に取り込むことによって、「ここならでは」のサービスをつくることです。それとともに、ものづくりの現場に消費の現場から情報をフィードバックし、洗練させていくことで、地場産業であるワインのものづくりの側面だけでなく、食文化のなど地域住民が日常消費する側面からもワイン産地を形成していこうという取り組みです。
具体的には、山梨県産ワインがたくさんそろっている酒販店や飲食店、ワイナリー巡りに適したホテル、ワイナリーツアーに特化した旅行会社、ワイナリーの立ち上げを得意とする建築家、日本一ワインやぶどう関係の蔵書を誇る図書館などです。これらは今現実のものとなって地域に存在しています。
 大木貴之さん提供
大木貴之さん提供「ワインツーリズム」の活動の中で、代表的なのが2008年に「理想のワイン産地をつくろう」とスタートさせた、ワイナリーのある地域をめぐる「ワインツーリズムやまなし」というイベントです。山梨県内ではワイナリーを巡ることが一般的ではありませんでした。そこでワイナリーのある地域をテーマパークと見立てて丸ごと楽しんでしまおうというイベントを立ち上げました。
具体的には、山梨県内の六つの市にまたがるワイナリーをエリア分けし、週末の2〜3日にそれぞれのエリアを割り当て、各エリア内にイベント限定の専用巡回バスのバス停を設置します。JR勝沼ぶどう郷駅、塩山駅、山梨市駅、石和温泉駅、甲府駅、竜王駅などを起点として、複数のワイナリーを1日で巡りやすいように循環するバスルートを設定し、当日限定で運行させます。
イベント参加希望者は、事前にインターネットから申し込んでいただきます。これまでの参加者は全国全ての都道府県から、最近は海外からのお客様も参加されるようになってきています。楽しみ方は、参加申し込みをすると送られてくる「ガイドブック」などをもとに、地域を「予習」しながらワイナリー巡りやランチ、宿泊などといった現地での行動プランを自ら考えていただいています。
当日は、受付で渡されるおそろいのワイングラスホルダーに記念テイスティンググラスを入れ、それぞれが考えたプランに沿って地域を散策しながら思い思いのワイナリーに足を運んでもらっています。そこで提供される有料・無料のワインテイスティングをして、お気に入りのワインを見つけて購入してもらうというものです。
 大木貴之さん提供
大木貴之さん提供コンセプトは「至らず尽くさず」。自由度が高く少しわかりにくいですが、その分楽しみ方は多様でワイナリーだけでなく、地域の人たちとのコミュニケーションや、自然、歴史、食なども楽しむ「大人の遠足」です。
このイベントの特徴は、これまで「産地=ワイナリー」だったものを「産地=ワイナリーのある地域」に再定義することにあります。つまりワイナリーをピンポイントにめぐって終わりではなく、ワイナリーが点在するエリア周辺に存在する既存の「場所、サービス、人」をたくさん巻き込み、イベントを構成していることです。
 大木貴之さん提供
大木貴之さん提供例えば、場所でいえば、ワイナリーはもちろん、駅、公園、お寺、JA共選所、博物館、図書館などを使用して、受付、クローク、バス乗り場、飲食・物販会場などを整備します。サービスでいえば、バスやタクシーはもちろん旅館や飲食店、酒販店など地域でふだんから営業しているお店に協力をお願いします。
人でいえば、地域のまち歩きNPOの主催者にバス停から散策してワイナリーを巡れるコースをつくってもらったり、朝市を自ら立ち上げた人の協力を得て、既存のお店だけではまかないきれないイベント時のフードコートを設置してもらったりしています。地元の農家の方々やボランティアの方々が案内所を設置したり、巡回して道案内をしてくれたりしています。中には名物おじさんになった方もいます。
こうして地域の日常をイベントに内包することで、イベント以外の日にも同じような体験ができるよう再現性を高め、新たな消費の行動が定着し、地域が稼げる環境へと変化していくことを目的としてプランニングしています。
現在では、こうした取り組みの効果もあってワイナリーが30軒ほど密集する甲州市勝沼では、10年前およそ9000人だった人口が今では約8000人に減ってしまったものの、ワイナリーを目当てに散策する人が増え、飲食店がこの10年で10店舗以上増えています。
また甲府駅周辺は2000年ごろには大型店が郊外に出店し、街中の商店街のシャッター街化が進んで、山梨県産ワインを提供しているお店もほんの数軒しかありませんでした。今では、甲府駅周辺のビル1階の空き店舗はほぼなくなり、甲府駅周辺の70店舗以上で山梨県産ワインを提供している状況となっています。
ワイナリーの変化でいえば、来県者が増えることによって売り上げの向上はもちろん、来県者を迎えるために醸造設備以外への投資や、新規参入ワイナリーの増加、さらには首都圏で働いていたワイナリー経営者の子息らが、イベントを手伝うようになり、その数年後にワイナリーを継ぐために仕事を辞めて山梨に戻ってくることが起きています。
このような地域の変化は歓迎できますが、過剰なブームを巻き起こし、コントロールを失って地域が疲弊してしまってはなんの意味もありません。あくまでも目的は、地域を次世代につないでいける環境をつくることにあります。
こうしたことを踏まえて現在「ワインツーリズム」という言葉は、一般社団法人ワインツーリズムの登録商標となっています。これは「ワインツーリズム」という言葉が乱用され、本来の目的とは真逆の格安ツアーなどによって、地域が消費されてしまうことを防ぐという狙いからです。
もちろん消費は悪ではありません。目的を見失った一過性の加熱した消費が地域を疲弊させます。多くの人を巻き込み、未来に繋げることに消費を活用し、ワイン産地を担う人たちやブドウ畑が育つような地域の時間の流れにあった「ムーブメント」として、産地形成の力にしていきたいと考えています。
 大木貴之さん提供
大木貴之さん提供地域に変化を起こしていくというのは、簡単なことではありません。いくつもの家族が代々暮らし、小さなコミュニティが集積した地域には、複雑な利害関係があり、それらを強制的に一つにしようとしても決してうまくはいきません。大切なのは、地域の人たち自らが当事者となって変化を起こしていくことです。
それには「ワインツーリズムやまなし」で掲げた「理想の産地をつくろう」というような、ざっくりとした未来を思い描き、地域の人たちが自分たちなりのイメージを持つことができて、同じ方向を向ける環境を整えることが重要です。
地域は急には変わりません。だからこそ地域の現状を内側の人間だけで変えるのではなく、地域外の人たちの消費やコミュニケーションの力を借りて、お互いに楽しみながら、少しずつ小さな成功体験を積み重ねていくことが大切です。地域の人の話を聞き、現状を見て、細心の注意を払いながら、地域の人たちへの利益と、地域全体にかかる公の利益の両方を鑑みながら仕組みをデザインすることで、自然と思い描いた未来へ近づけることができると考えています。
※ワインツーリズムは一般社団法人ワインツーリズムの登録商標です。
 大木貴之さん提供
大木貴之さん提供大木貴之(おおき・たかゆき)
LOCALSTANDARD株式会社代表、 一般社団法人ワインツーリズム代表理事
 大木貴之さん提供
大木貴之さん提供

「論座」では、セミナー「キーパーソンから学ぶ地域プロデュース」を開きます。山梨で「ワインツーリズム(R)」を始めた大木貴之さんと、有田焼の再生や星野リゾートの宿泊施設のプロデュースを行う南雲朋美さんからメソッドを学びましょう。
南雲朋美さん
地域ビジネスプロデューサー、慶應義塾大学・首都大学非常勤講師。1969年、広島県生まれ。「ヒューレット・パッカード」の日本法人で業務企画とマーケティングに携わる。34歳で退社後、慶應義塾大学総合政策学部に入学し、在学中に書いた論文「10年後の日本の広告を考える」で電通広告論文賞を受賞。卒業後は星野リゾートで広報とブランディングを約8年間担う。2014年に退職後、地域ビジネスのプロデューサーとして、有田焼の窯元の経営再生やブランディング、肥前吉田焼の産地活性化に携わる。現在は滋賀県甲賀市の特区プロジェクト委員、星野リゾートの宿泊施設のコンセプト。メイキングを担うほか、慶應義塾大学で「パブリック・リレーションズ戦略」、首都大学東京で「コンセプト・メイキング」を教える。【南雲さんの記事はここから】
大木貴之さん
LOCALSTANDARD株式会社代表、一般社団法人ワインツーリズム代表理事。1971年山梨県生まれ。マーケティング・コンサルタント会社を経て地元山梨へ。2000年に当時シャッター街だった山梨県甲府市に「FourHeartsCafe」を創業。この「場」に集まるイラストレーター、デザイナーや、ワイナリー、行政職員、民間による協働で「ワインツーリズムやまなし」(2013年グッドデザイン・地域づくりデザイン賞受賞)を立ち上げ、山梨にワインを飲む文化と、産地を散策する新たな消費行動を提唱。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科に入学しワインツーリズムを研究。卒業後は、山形、岩手と展開。ワインに限らず地場産業をツーリズムとして編集し直し、地域の日常を持続可能にしていく取り組みを続ける。【ワインツーリズム山梨のサイトはここから】
■第1部
南雲朋美さんの講演テーマ「地域の魅力の見つけ方」
地域の魅力を発見する方法とコンセプト化する考え方をお話しします。どんな地域でも、そこに人々が暮らしているのであれば、その経済を支える「何か」があります。それが魅力です。その魅力を人が納得できるコンセプトに昇華しますが、コンセプトはテーマと言ってもいいかもしれません。いずれにしても事業を行う上で、経営の礎(いしずえ)になる重要な概念です。厳しい競争の中で生き残ることができる核となる魅力を見つけましょう。
■第2部
大木貴之さんの講演のテーマ「地域の日常をつないでつくるツーリズム」
地域を使ったコミュニティベースのツーリズムの手法をお話しします。たくさんの人が来ても、その消費が外に漏れてしまっては効果が薄れてしまいます。人が地域のキャパシティを越えてまでたくさん来ればいいというわけでもありません。地域のファンになってもらいリピートしてもらうその仕組みづくりのお話をします。新たな産業をつくるのではなく、既存の産業や地域のイメージを活用し、サービスからの視点で捉え、地域を次世代に繋いでいくヒントになればと思います。
第3部
パネルディスカッション
・南雲朋美さん
・大木貴之さん
・岩崎賢一(ファシリテーター)
※第3部終了後、講師との名刺交換もできます。
10月22日(祝日)17時30分~20時30分(17時開場)
朝日新聞東京本社 本館2階読者ホール(地下鉄大江戸線築地市場駅すぐ上)
参加費 3000円、定員90人。申し込みが定員に達した時点で締め切ります。
Peatixに設けられた「論座」のイベントページから参加申し込みをお願いします(ここをクリックするとページが開きます)
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください