日米政府が正式に署名した日米貿易協定。国会での本格論戦を前に中身を考える
2019年10月19日
 日米貿易協定の署名式で演説するトランプ米大統領=2019年10月7日、ワシントン
日米貿易協定の署名式で演説するトランプ米大統領=2019年10月7日、ワシントン今月7日、ホワイトハウスで杉山晋輔駐米大使とライトハイザーUSTR(米通商代表部)代表が日米貿易協定に正式に署名した。内容は、9月25日にニューヨークで行われた日米首脳会談で「最終合意」されたものと基本的に同じようである。
すなわち、日本は豚肉や牛肉、オレンジ、チーズ、ワインなどの農産品の関税をTPPの範囲内で引き下げたが、コメやバター、木材、水産品は対象外とした。一方、米国は、しょうゆや切り花などの農産品のほか、工業製品では工具や楽器、自転車などの関税を撤廃ないしは引き下げることになる。ただ、日本が強く希望していた自動車および部品に対する関税は対象外とされた。
今後、日米両国はそれぞれ法的な手続きを進め、来年初の発効を目指すとしているが、米国は大統領権限で発効が可能で議会承認は不要につき、発効に向けてのハードルは日本側の手続きのみと言って良いだろう。
承認案は既に今月15日に閣議決定され、国会に提出されているが、一部の報道によると24日からの審議開始が予定されているようである。今後の国会における議論の行方が注目される。
その中で最大の論点となるのは、もちろんのこと、今回の合意内容の評価であろう。
野党は総じて、日本は米国に譲歩し過ぎであり、決して日米が「WIN-WIN」の結果とはなっていない、として批判を強めている。今回の合意を「最終」と表現することにも違和感があり、その点については後に詳述するとして、まずは本当に「WIN-WIN」と言えるのかどうか、合意内容を米国、日本、それぞれの視点から確認していきたい。
今回の合意内容を米国側から見た場合、日本が譲歩し過ぎだという指摘があるように、少なくともトランプ政権にとっては得るものが大きいことは間違いない。
米国は、トランプ大統領が自ら公約として掲げたTPP離脱により、TPP加盟国との取引において関税など条件面で不利になっていた。特に農産品は、TPP加盟国中で最大の市場となる日本向け輸出において、オーストラリアやニュージーランド、カナダなどにシェアを奪われる恐れがあり、再選を目指すトランプ大統領にとって重要な米国中西部の主力生産品だけに、看過できない状況であった。
代表的な例を挙げると、日本の牛肉の輸入量は、2019年上半期(1~6月)に米国からは前年同期比5%程度の増加にとどまっているが、カナダは93%、ニュージーランドは46%もの大幅増となっている。それでも米国からの輸入量はカナダの6.7倍、ニュージーランドの11.5倍と圧倒的な規模の違いはあるが、増加幅に着目すれば、米国は前年同期比で6000トン弱の増加に対して、カナダは8000トン強と米国を凌駕(りょうが)しており、ニュージーランドでも3000トン強と半分に達しているため、米国にとっては警戒すべき動きと言える。
農産品全体で見れば、今回の合意によって米国から日本への輸出141億ドル(約1兆5,200億円、2018年)のうち72億ドル(約7800億円)相当で関税が引き下げられ、そのうち13億ドル相当は関税が撤廃される。
これまで、全体の約4割にあたる52億ドルが既に非関税であったが、今回の合意分を加えると、日本への農産品輸出全体の半分近く(65億ドル)が非関税となり、税率引き下げを含めると9割弱が関税面での恩恵を受けることになる。TPPでの劣勢を挽回するには十分な成果であろう。
米国は、トランプ大統領就任後、NAFTA(北米自由貿易協定)の見直しや中国との貿易協議を進めてきたが、NAFTAは昨年11月にその後継となるUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)に署名したもののいまだ各国の批准待ち。米中の貿易協議も紆余曲折を経て、先日、ようやく合意に向けて一歩前進した程度である。
欧州との間では、ボーイング、エアバスへの補助金を巡り対立。米国はWTO(世界貿易機関)の承認を得て、エアバスへ補助金を出したEUに最大で年間75億ドル(約8,000億円)の報復関税を検討するなど、対立はむしろ激しさを増す方向にある。
そうした状況下、トランプ政権にとって、貿易交渉で具体的成果を初めて得たことは大きな収穫である。もともとTPPを離脱したことで生じたデメリットを取り返しただけ、ある意味で自作自演の成果ではあるが、本人も言う通りトランプ政権にとっては大きな勝利だと評価できよう。
 日米貿易協定の署名を終えた杉山晋輔駐米大使(前列左)とライトハイザー米通商代表(同中央)、それを見守るトランプ米大統領(同右)=2019年10月7日、ワシントン
日米貿易協定の署名を終えた杉山晋輔駐米大使(前列左)とライトハイザー米通商代表(同中央)、それを見守るトランプ米大統領(同右)=2019年10月7日、ワシントン
 日米貿易協定をめぐるライトハイザー米通商代表との会談を終え、取材に応じる茂木敏充外相=2019年9月23日、ニューヨーク
日米貿易協定をめぐるライトハイザー米通商代表との会談を終え、取材に応じる茂木敏充外相=2019年9月23日、ニューヨーク先述の通り、農産品や工業製品の一部で関税を撤廃・引き下げられるわけであり、勝ち取ったものは確かにある。しかしながら、それが十分な成果だったのかどうか、何らかの基準で測る必要があろう。
一つの基準となり得るのは、当初の目標である。交渉の初期段階において、日本政府からは、トランプ政権は具体的な成果を急いでいるため強気な交渉が可能であり、農産品関税についてTPPの範囲内とすることのほか、現在、乗用車に2.5%、トラックに25%、関連部品に2.5%課せられている関税の撤廃も目指せるのではないか、という声が聞かれた。
しかしながら、実際には後者はかなわず、協定文章の別紙に「さらなる交渉の対象となる」と記されるにとどまった。これは、継続協議とするかもしれないという程度であり、可能性がなくなったわけではないものの、勝算があるわけでもない。当初の目標に照らせば、勝利とは言い難いだろう。
自動車に関しては、トランプ大統領の伝家の宝刀と化しつつある「米国通商拡大法232条」の適用を回避できたことを勝利ととらえる向きもある。補足すると、同法は米国が安全保障上の問題があると判断する輸入に対して、高関税などによる制限を一方的に設けられるとするものであり、この法律に基づいてトランプ大統領は、自動車及び部品に最大25%の追加関税を課すかどうかの検討を今年2月に始めた。
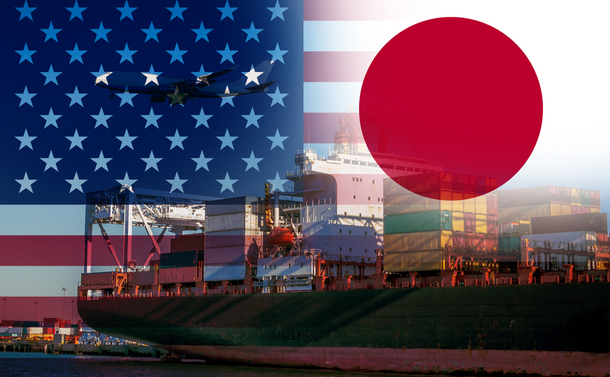 Raggedstone/shutterstock.com
Raggedstone/shutterstock.com仮にこの追加関税が実施されれば、米国を最大の輸出先とする日本の自動車産業にとって大きな打撃になるたけでなく、マクロ的にもその影響は無視できない。
日本の対米輸出は2018年で15.5兆円、輸出全体の19%を占めたが、そのうち部品を含めた自動車は5.5兆円、対米輸出全体の35%にも上る。この額はGDPの約1%に相当するため、仮に追加関税によって対米自動車輸出が2割落ち込むとすれば、それだけでGDPを0.2%押し下げることになる。
さらに、原材料調達や設備投資、雇用などを通じた波及効果を加えれば、その下押し圧力は倍増する。もし、米国の追加関税による影響が東京五輪後に見込まれる景気の足踏みと重なれば、日本経済は後退局面入りする可能性も否定できない。
先日の日米首脳会談における共同声明には、この米国通商拡大法232条に関して、今回の「協定が誠実な履行がなされている間」は「本共同声明の精神に反する行動を取らない」と明記されており、日本政府はこれを232条の適用除外を示すものとしている。
実際、担当閣僚であるライトハイザーUSTR(米国通商代表部)代表は首脳会談後、「我々もトランプ大統領も、現時点で日本車に追加関税を課すことは考えていない」と話しており、口頭では確認できている。とはいえ、今回署名された文章には記されておらず、「現時点で」という表現とともに、一抹の不安を残す。諸手を挙げての勝利とはとても言えない状況である。
少し視点を変え、今回の日米貿易協定の日本経済に対する影響を、やや計量的に考えてみよう。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください