日本出版者協議会相談役・緑風出版社長の高須次郎氏に聞く(上)
2019年12月04日
IT大手の米アマゾンが日本語サイトを開設し、ネット書店として日本に本格進出してから約20年。ネットの普及で進んだ活字離れを背景に街の本屋が次々と消えていくなか、「国内最大の本屋」となった。今日では一般消費者向けの大半の商品を扱い、売上高は1兆5000億円に及ぶ国内最大のインターネット通販業者に成長した。
「緑風出版」(東京都文京区)の高須次郎社長は、中小出版社でつくる「一般社団法人・日本出版者協議会」(出版協、旧出版流通対策協議会)の会長、そして現在は相談役として再販売価格維持制度(再販制度)の存続を訴え、本屋をのみ込む一人勝ちのアマゾン商法にも異議を唱え続けてきた。大幅なポイント還元という方法で値引き販売を続ける、アマゾンへの出荷を緑風出版が中止して今年で6年目に入った。
アマゾンとの闘いを描いた『出版の崩壊とアマゾン 出版再販制度<四〇年>の攻防』(論創社)というタイトルの著書がある、高須氏に話を聞いた。
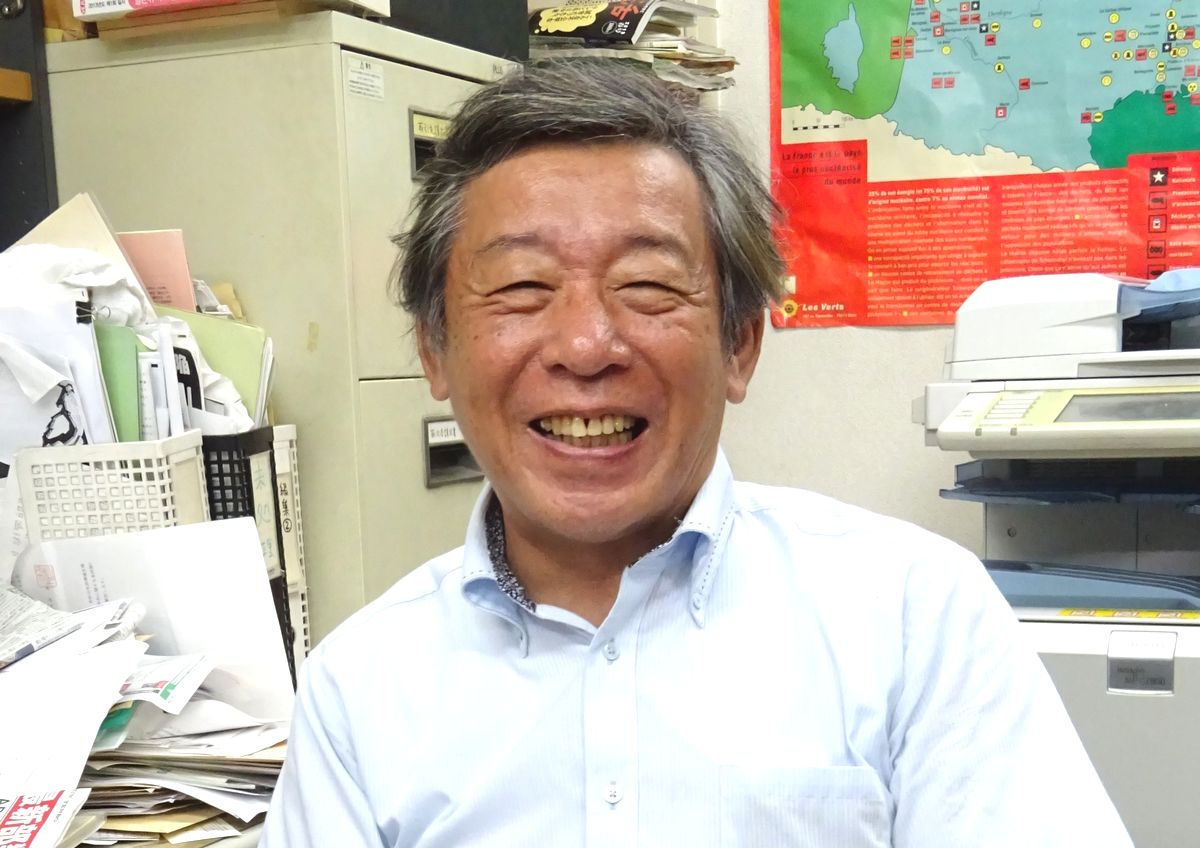 アマゾンに出荷を停止している緑風出版の高須次郎社長(日本出版者協議会相談役)=臺宏士撮影
アマゾンに出荷を停止している緑風出版の高須次郎社長(日本出版者協議会相談役)=臺宏士撮影――緑風出版の新聞広告には「現在アマゾンへは出荷停止中です」との記述があります。5年半ほど前になりますが、既に巨大書店に成長していたアマゾンに対して、緑風出版など3社が出荷を停止するとした発表は、多くのメディアが報道し、大きな話題になりました。
高須氏 アマゾンへは2014年5月から出荷を停止しています。直接の理由は、アマゾンが2012年8月から学生を対象に始めたポイント還元サービス「Amazon Student」に対抗するためです。
還元率は、消費税を含む注文価格の10%もの高率です。学生だけでなく、これがすべての人に広がると書店への影響は非常に大きい。一部の大手の書店はともかく、いわゆる街の本屋さんの利益率は1%にも満たないと言われていて、これではアマゾンにはとても太刀打ちできません。つぶれてしまいます。公正な競争とは言えないと思いました。私は再販制度に違反していると考えています。
当時、緑風出版だけでなく、出版協に加盟する51社(対象書籍は約41万点、アマゾンが当時扱う書籍の約6%)は、自社の書籍をサービス対象から除外するよう求めて交渉しました。
ところが、アマゾンは「書籍仕入れの契約をしているのは取次店だから、個別の出版社とは交渉する立場にはない」とか、「アマゾンの日本法人は、米アマゾンのアジア地域の販売子会社である『Amazon.com Int’l Sales,Inc.』(米シアトル)から委託を受けて販売しているだけだ」とか、いろんな理由をその都度持ち出してきて、らちがあきませんでした。
出版協は「Amazon Student」が始まった2カ月後の2012年10月、アマゾンに対して、(1)10%ポイント還元特典を速やかに中止すること(2)(再販売価格維持契約に基づき)再販対象書籍について表示を「定価」と変更すること――を求めたが、アマゾン側は「個別の契約内容に関して貴会に対しご回答する立場にない」と突っぱねた。2013年3月、アマゾンに代わって回答したのが日本出版販売(日販)。日販が契約しているのは米アマゾン(Amazon.com Int'l Sales,Inc.)で、この契約内容をアマゾンとの取引でも適用するという合意をしていることを明らかにした。
このためやむなく2014年5月から出荷停止をすることになったのです。緑風出版だけでなく、晩成書房、水声社の3社でそろって計1600点の書籍について、まずは6カ月間の期間限定として踏み切りました。
――3社のほか、三元社、批評社の2社も1カ月の出荷停止に追随したようですが、売り上げへの影響はありましたか。
高須氏 残念ながらアマゾン側は、期限とした半年経っても除外要請に応じてくれませんでした。最初の3社は、出荷停止のまま今日に至っています。
緑風出版で言えば、アマゾンへの当時の依存は取次売り上げの7%~8%ほどでした(平均は10~15%と言われていた)。一時的に売り上げは減少しましたが、後には徐々に回復しました。出荷を停止した出版社のブックフェアを行ってくれる書店もあり、支援してもらえました。
ネットでの購入が広がり、実店舗で見つけた本のタイトルを携帯カメラで撮影し、帰宅してからアマゾンで注文する人もいます。書店側には相当の危機感があったのだと思います。
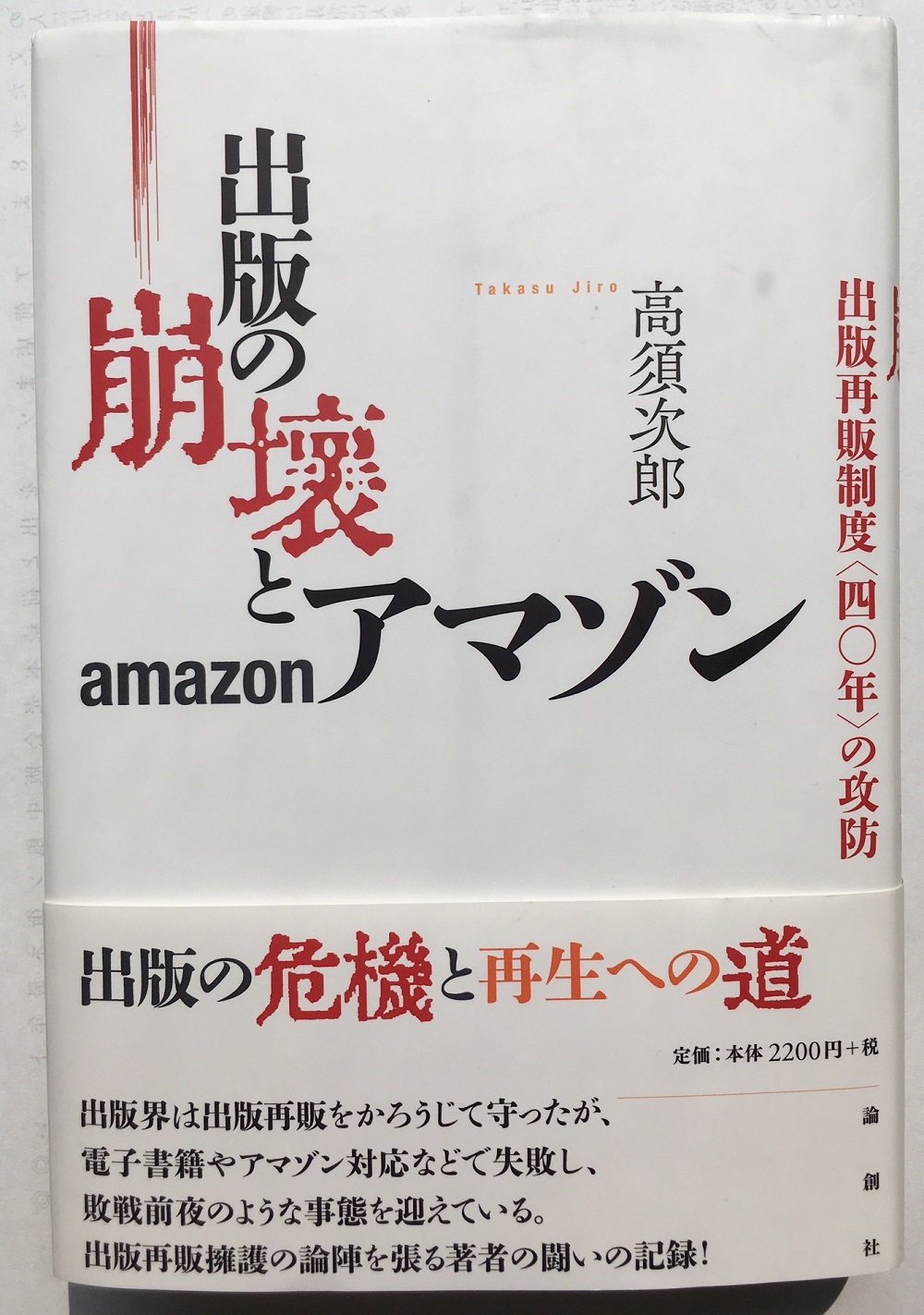 アマゾンとの闘いを執筆した高須氏の「出版の崩壊とアマゾン 出版再販制度<四〇年>の攻防」(論創社)
アマゾンとの闘いを執筆した高須氏の「出版の崩壊とアマゾン 出版再販制度<四〇年>の攻防」(論創社)高須氏 出版科学研究所の推計によると、米アマゾンが日本に上陸した2000年の書籍・雑誌の販売金額は、2兆3966億円でした。これが2017年には1兆3701億円と45%も減少しました。ピークは、米マイクロソフトの基本OS「ウィンドウズ95」の「日本語版」が発売された翌1996年の2兆6564億円で、この時からだと販売金額はなんと半減しています。
書店や出版社の数も減り続けています。2000年の書店の数は、2万1495店だったのが2017年には1万2026店と44%も減少しました。いまでは地方自治体の2割には書店がありません。出版社も同じように4391社から3382社になりました。
アマゾンは、2011年に日本での書店売り上げで1位になりました。「週刊東洋経済」の当時の推計では、アマゾンの販売額は1920億円。2位の丸善書店やジュンク堂書店を抱える大日本印刷グループの1569億円と大きな差をつけました。3位は紀伊國屋書店で1098億円でした。
アマゾンは、経営情報の開示に消極的な企業なのではっきりとした数字は言えませんが、現在の売り上げは、2000億円から3000億円ほどと推計されています。わずか1社で書籍・雑誌売り上げの10%以上、小売り書籍の20%以上を占めているとみられています。街の本屋が次々と廃業に追い込まれるなかでアマゾンの一人勝ちなのです。
――アマゾンでは緑風出版など出荷を停止したはずの出版社の新刊本も購入することができます。なぜでしょうか。
高須氏 書籍の扱いからスタートした米アマゾンですが、いまの理念には「エブリシングストア」というのがあります。正式な取引関係にないメーカーの商品であってもあの手この手を使って仕入れる専門の部門があり、日本でも同じようにしていると言われています。アマゾンの主要な取引先の取次店である日本出版販売(日販)からは「緑風出版の本をアマゾンに出荷しないシステムを整備した」と言われました。私たちにもアマゾンがどこから仕入れているのかは、はっきりとはわかりません。
――読者・消費者の立場から考えると、同じ商品であれば、少しでも定価から安く購入できるお店を選ぼうとするのは自然な行動ではないでしょうか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください