日米英3カ国の専門医資格を持つ矢野晴美医師に聞く
2020年02月03日
新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大。世界保健機関(WHO)がついに緊急事態を宣言、日本政府が「水際対策」を強化するなど、様々な動きが出ています。そんな中、中国や日本で、すでに無症状の感染者が見つかるなど、新しいフェーズに入っていると見る感染対策の専門家もいます。ドラッグストアでマスクが売り切れになるニュースが流れていますが、私たちは今、感染症の情報をどのように理解し、どう備えた方がいいのでしょうか。東京でもオーバーシュート、ロックダウンの可能性も危惧されます。
 成田空港でサーモグラフィーの前を通って入国する人たち(AP)
成田空港でサーモグラフィーの前を通って入国する人たち(AP)厚生労働省がメディア向けにアラートを出し始めたのは、2020年1月6日です。「中華人民共和国湖北省武漢市における原因不明肺炎の発生について」として、2019年12月12日~29日の間に59例の確定例があり、うち7例は重症で、死亡例はまだないとされていました。類似疾患のインフルエンザ、鳥インフルエンザ、アデノウイルス、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)は否定されている、として、武漢市の帰国者に、咳や発熱等の症状がある場合はマスクを着用して医療機関を受診するよう、協力を求める内容でした。
その後も患者は増え続け、WHOは緊急事態宣言について一度は見送ったものの、日本など中国以外の国々で感染が拡大していることなどから1月31日(日本時間)に宣言し、注意喚起を図りました。
日本政府も、「指定感染症」の施行を2月1日に繰り上げ、封鎖されている中国・武漢がある湖北省に滞在していた外国人の入国を拒否する対策を始めました。日本人の湖北省への渡航中止勧告も出されています。
こうした状況は刻々と変化していくうえ、テレビなどメディアを通じて様々な人がコメントし、SNSも含め、情報の洪水が起きています。私たちはどう判断し、行動したらいいのか。「インフェクションコントロールドクター」であり、アメリカ、イギリス、日本の感染症や熱帯医学の専門医資格を持ち、国際旅行学会認定医でもある、国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター・感染症学の矢野晴美教授に尋ねました。
 1月31日付の朝日新聞夕刊1面
1月31日付の朝日新聞夕刊1面――WHOの緊急事態宣言を、市民はどう理解すればいいのでしょうか。
2000年代に入り、SARSや新型インフルエンザなど何年かに一度、未知の感染症が起き、日本でも感染対策の強化が行われてきました。「今回が終息してもまた次が来る」ということで、ふだんから感染対策のレベルを上げておくということです。日本のレベルは、風疹が蔓延し、麻疹もぽろぽろ発生しており、まだ脆弱なところがあります。
WHOが2月2日に公表したリポートによると、感染が確認された患者数は世界で14557人で、亡くなった人は305人となっています。現時点での致死率は、鳥インフルエンザに比べると相対的にかなり低いです。論文に出ているもので推測すると2%程度です。ところが、感染症の専門家の間では今、無発症でウイルスの保有者が数十万人規模でいると予想されています。それが分母となると、致死率はかなり下がります。2009年の新型インフルエンザのパンデミックの致死率は1%を切り、世界的には0.2~0.4%程度でした。もしかしたら、それに近いか、それよりも低いのかも知れません。
――無症状で新型コロナウイルスを持つ人が現れました。WHOのテドロス事務局長は、記者会見で「これ以上の移動や貿易の制限が必要だとは考えていない」と述べています。一方で、航空機の運航を止める航空会社が出てきたり、入国やビザ発給を制限している国も出てきたりしています。市民は現在のフェーズをどう理解すればいいのでしょうか。
今は、不要不急な動きはやめた方がいいということです。優先順位からすると、患者が一番多く、症状のない微生物保有者が多いと考えられる中国、特に武漢への渡航は控えた方がいいレベルだと思います。
2月2日のWHOのリポートによると、中国の次に患者が多いのが日本やタイ、シンガポールになります。患者が多い日本で暮らす人たちは海外へ行かない方がいいのか、という話にもなります。現時点で、日本人の渡航を制限することは、武漢以外にはないと思います。ただし、日常生活では人と接触するので常にリスクがつきまといます。基本的な感染対策を個人が心がけることに尽きると思います。
――新型コロナウイルスの患者数に関する数字が毎日報道されていますが、どのように理解したらいいのでしょうか。
論文情報によると、中国で報告数が一番多かったのは1月8日です。報告数による疫学カーブは、それ以降下がってきています。SARSのときは、医療従事者の2次感染があったので二峰性にもう1回上がりました。今回はどうなっていくのか分かりませんが、感染対策の一つの目安にはなるでしょう。
 羽田空港国際線ターミナルの到着口には注意喚起を知らせるポスターがはられていた=2020年1月31日、岩崎撮影
羽田空港国際線ターミナルの到着口には注意喚起を知らせるポスターがはられていた=2020年1月31日、岩崎撮影――アウトブレイクした国を封じ込めればいいと考える人もいます。日本でも「水際対策」が強調されていますが、対策の力点はそこなのでしょうか。
武漢を封鎖したのは致し方ないことだと思います。どれぐらいの病原性があって、どれぐらいの感染力があるのか、分からなかったためです。情報が少ない中で、できることは感染経路を断つことが最重要で、人の動きに制限を加えることは仕方がなかったと思います。
一方で、少人数ではありますが、世界中に患者が広がっている状況でどうすればいいかということですが、いわゆる鎖国のようなことを日本がするのがいいかというと、クエスチョンマークが浮かびます。
恐らく日本国内でも、中国人旅行客の患者がバスツアーで移動していますし、新型コロナウイルスは潜伏期間が長い印象があります。多くの接触者がいるので、現実的には封じ込めるのがもう難しいフェーズに入っているのではないかと思います。
 閉鎖された中国・武漢市の市場(AP)
閉鎖された中国・武漢市の市場(AP)――新型コロナウイルスが国内でヒト-ヒト感染を起こし始めていることを想定したうえで、市民はどのような感染対策を心がければいいのでしょうか。
最も大事なことは手洗いです(アルコール消毒を含む)。マスク着用を勧める人がいますが、症状のない人が予防的にマスクを着用することに確かなエビデンスが少ない、というのが国内外の専門家の認識です。
医療機関でさえ医療従事者がマスクを適正使用していないケースがあります。鼻が出ていたり、皮膚に密着していなかったりすると感染を防ぐことはできません。マスクの着脱で触った手が最も汚れているので、その手で色々な環境表面を触ると、そこで2次感染が起きます。電車に乗るときにマスクは必要ですかという人がいますが、それより手洗いをきちんとする方が現実的な予防方法です。
一般市民の人たちは、マスクをしているつもりで守られていると思っている人が多いですが、効果は限定的であることを理解していただいた方がいいと思います。
――厚労省もマスク着用については、飛沫を飛ばさないための「咳エチケット」といっています。
咳エチケットの方法の一つはマスクですが、もう一つは咳をする際、ハンカチや肘で口をふさぐことです。手で押さえると手が汚染されてしまい、その手で色々なところを触って2次感染が起きます。人と触れない肘で口を押さえてくださいということです。
――マスクも汚染された部分に触れないで処理することが重要ですね。
冬場ではインフルエンザや他のかぜのウイルスも付着している可能性もあり、マスクの本体部分は触らないこと。そして鼻のところをワイヤーで密着させるわけですが、ずれてきたら取り換えましょう。取り外しはゴムのところを持って外し、捨てます。
マスクは長時間しているほど表も裏もウイルスだらけになります。例えば、食事のときにマスクをテーブルに置けば、そこが汚れます。そういうところで感染が広がっていきます。
――手洗いが最重要ということですが、アルコール消毒でもいいのですか。
手洗いは、流水で洗うか、アルコール消毒薬で手を消毒するかです。家庭なら、手などは消毒用アルコール(70%)、環境表面をふく場合は、アルコール消毒薬や次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)などが有効とされています。
――乳幼児は幼稚園や保育園に通い、感染症にかかりやすい環境で暮らしています。保護者の中には子どものマスクがないと焦っている人がいます。どうアドバイスしますか。
今、子どもの外出を控えるというレベルではありません。子どもはマスクをしていても手で触ってしまいます。まずは手洗いがきちんとできるようにしましょう。
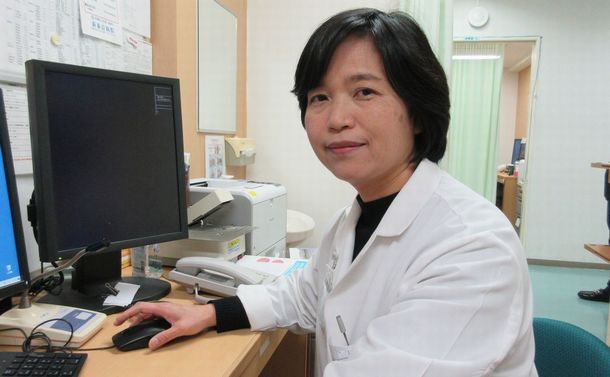 新たなフェーズに入っているのか。インタビューで解説してくれた矢野晴美教授=2020年1月31日
新たなフェーズに入っているのか。インタビューで解説してくれた矢野晴美教授=2020年1月31日――日常生活の中で人とまったく接触しないことは難しい。終息するまで在宅勤務というわけにも、ネット通販で暮らすわけにもいきません。幼い子どもを抱えた人たちは保育園も悩みの種です。身を守るためにどこまでしなくてはいけないか、悩む人が多いと思います。
多くの人が触るような電車やバスのつり革などに触れて帰宅したら、必ず手洗いをするということに尽きます。ベースとしての感染対策を高めるための「ステップゼロ」は、年齢ごとの標準的なワクチンを接種しておくということです。その次に手洗いと咳エチケットです。
免疫力を高めるという観点からアドバイスすると、規則正しい生活をする、十分な睡眠を確保する、バランスの取れた食事を取る、運動を適宜する、といった健康の維持・増進に必要なことを続けていくことに尽きます。
日ごろの健康に対する認識を一気に上げるのは大変です。100を基準とすると、標準的なワクチン接種で50をカバーして、手洗いや消毒を徹底することでそれが60に上がり、咳エチケットで80になるというようにベースを高めることが大切です。そこまでベースが高ければ、例えエボラ出血熱や新型コロナウイルスでも準備することは少なくなります。
さらに、自分が抱える疾患名、どの薬は何の病気のために飲んでいるかを知っておくこと。健康リテラシー、薬リテラシーを高めていきましょう。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください