中国、日本、欧米で異なる経済への影響。懸念される「負の連鎖」は避けられるか
2020年03月06日
 mantinov/shutterstock.com
mantinov/shutterstock.com2月末の米国株式市場では、NYダウ平均株価が一時、前日比1000ドル以上の大幅下落となったが、FRBパウエル議長の緊急声明で利下げが示唆されたことから、最終的には300ドル強まで下落幅を縮小した。そして、3月2日の東京市場では、日銀の黒田東彦総裁の緊急談話を受けて日経平均株価は若干反発、その夜のダウ平均株価は各国の中央銀行による政策協調への期待から1000ドルを超える上昇を見せるなど、金融市場は政策対応を催促するかのような動きを見せた。
それに応えるかたちで翌3日、FRBは緊急利下げを実施した。しかし、期待に反してダウ平均株価は785ドルも下落、4日は再び1000ドル超上昇したが、こうした相場の乱高下こそが、新型コロナウィルスの感染拡大という不透明要因による景気の先行き懸念を端的に示している。
実際、新型コロナウィルスの影響は中国からアジア、欧米と波及しつつあり、それが「時間差」をもって、アジアや欧米向けの輸出減などのかたちで中国経済を下押しするという「負の連鎖」が起きる公算が次第に大きくなってきている。
FRBの利下げで株価下落を止められなかったのは、こうした「その先」を見通したためだろう。換言すれば、金融緩和だけでは実体経済の悪化を食い止め、持ち直しに向かわせるには不十分だと金融市場はみたのであろう。
以下、新型コロナウイルスをめぐる世界の現況について、詳しく見ていこう。
震源地の中国では、当初1月24日から30日とされていた春節休暇を前に、新型コロナウィルス感染者拡大への対応が本格化し、その起点となった武漢市を含む湖北省は事実上封鎖されたほか、交通機関の利用を全国的に制限、団体の海外旅行も禁止するなど、感染拡大を食い止めるための思い切った措置が取られた。
その結果、春節期間中の個人消費は、旅行や外食、小売を中心に前年同期に比べ3~4割程度減少した。さらに政府は春節休暇期間を2月2日まで延長、大部分の地域で春節休暇明けの企業活動を1週間程度停止したため、この間、経済活動は幅広い分野で全国的に大きく落ち込んだ。
その後、湖北省を除いて企業活動再開の動きが広がっているが、まだ完全回復には至っていない。今年1~3月期の経済成長率は、昨年10~12月期の前年同期比6.0%から4%以下に減速する可能性が高いとみられる。
他方、明るい材料も出始めている。2月上旬には新規感染者数が3000人を超える日が続いていたが、2月半ば以降は1000人未満にとどまっており、感染拡大が“ピークアウト”する兆しがある。省を跨(また)ぐ長距離バスの運行も順次再開され、北京では人手が戻りつつあるとの声も聞かれる。
比較的感染者数が多かった広東省でも、対策レベルが中央政府から地方政府へ引き下げられ、前述の通り生産・営業活動を再開する企業が増えるなど、徐々にではあるが「正常化」に向けて歩を進めている。新型コロナウィルスの影響は最悪期を脱しつつあるように見える。
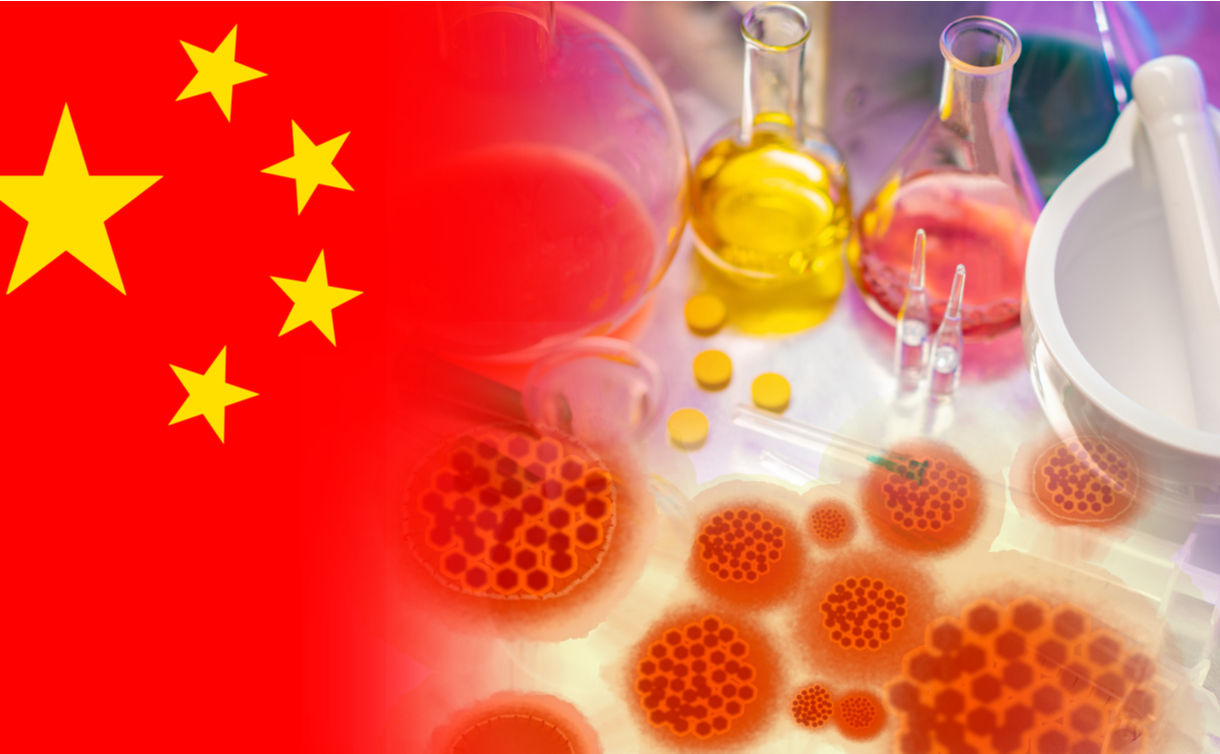 FOTOGRIN/shutterstock.com
FOTOGRIN/shutterstock.com中国とは対照的に、悪影響が深刻化しているのは、日本を含むアジア地域であろう。
日本においては、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください