声を上げることが国を動かす
2021年03月23日
キッズラインのわいせつ事件が起こった当初から、私は性犯罪の再犯防止等については国として取り組む必要性も感じていた。個社の問題もあるが、保育全体、シェアリングエコノミー全体、そして国の仕組みとしてもどうしていくのが最善かを考えたいと思っていた。
2020年7月頭にYahoo個人でどちらかというと規制緩和の方向に向かっていた国の動きに警鐘を鳴らし、海外の制度等について紹介する記事を書いた。
英国では、DBS(Disclosure & Barring Service)という仕組みがある。DBSというのは、事業者からの照会に応じて、犯罪歴がないことの証明書を発行してもらう仕組みだ。その証明書がないと、8歳未満の子どもに1日2時間以上接するサービスに関わるすべての人が義務付けられているOfsted(Office for Standards in Education=教育水準局)という政府機関への登録ができない。
記事公開の直後に、当時の加藤勝信厚生労働大臣が、キッズライン事件を踏まえた質疑に対し、犯罪歴を確認できるようにする法整備についてベビーシッターを届出制から免許や認可制にする必要性も含めて検討する趣旨の発言をした。山が動き始めたと考え、それも記事にしている
 加藤勝信厚労相(当時)=2020年2月20日、国会
加藤勝信厚労相(当時)=2020年2月20日、国会7月14日、病児保育等を手掛けるフローレンスとベビーシッター有志、そしてキッズラインの登録シッターによって長女がわいせつ被害にあったAさんら被害者の親が、保育・学校現場での性犯罪を防止するための記者会見を開いた。
これはキッズラインの事件を機にそれぞれ危機感を強めたフローレンスとシッターたちが連携し、さらに私がAさんを紹介したことで実現した会見だった。ベビーシッターに限らず子どもに関わる領域すべてを対象にすることができる英国型データベースの導入を目標にしたもので、学校で子どもが被害に遭ったという家族も登壇した。
ここまでに大手メディアもわいせつ事件については一部報道をしはじめていたが、厚生労働省で開かれたこの記者会見は多くの記者の関心を引いたのか、各メディアが大々的に報道した。
 保育や教育の現場に携わる人に証明書を発行する「日本版DBS」の導入を求めたNPO法人フローレンスの駒崎弘樹代表理事。別の事業者のシッターや教諭から子どもが性被害を受けたと訴える保護者2人もついたて越しに対策を訴えた=2020年7月14日、東京都千代田区の厚生労働省
保育や教育の現場に携わる人に証明書を発行する「日本版DBS」の導入を求めたNPO法人フローレンスの駒崎弘樹代表理事。別の事業者のシッターや教諭から子どもが性被害を受けたと訴える保護者2人もついたて越しに対策を訴えた=2020年7月14日、東京都千代田区の厚生労働省その後、この動きは8月28日に再開される厚生労働省の専門家会議、社会保障審議会の児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会に引き継がれた。厚労省は「報道を受けて対応」するために会議を立ち上げたとしており、報道と世論が沸き上がったことが国を動かすことにつながったことが分かる。
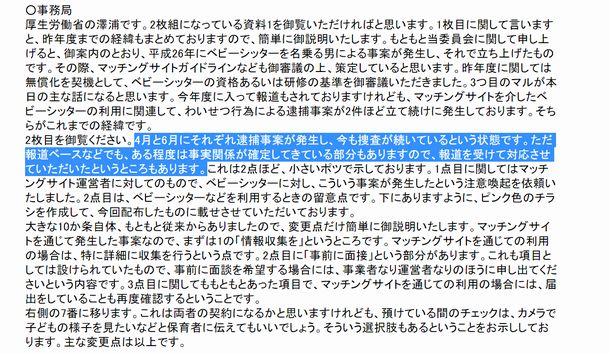 第11回社会保障審議会(児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会)議事録より
第11回社会保障審議会(児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会)議事録よりこの会議では、当初記者会見したメンバーらが目指していた「あらゆる子育て領域での」とはならなかったものの、わいせつ事件をおこしたベビーシッターについて、行政処分歴をデータベースに登録するという方向性が2020年末までに定まっていった。
また、厚労省が定めている、マッチング型事業者が遵守すべき「ガイドライン」に細かな注意事項が書き込まれるなど、キッズライン事件を踏まえて多くの文書や要綱が書き換えられた。データベース登録では初犯は防げないなどの課題はあれど、キッズライン事件で声を上げた人たちがいて、実際に仕組みを動かすまでに至ったのだ。
シッターがわいせつをはたらくという問題について議論が一気に進んだ一方、思うように大きな動きに接続できなかった課題もあった。それは
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください