「ポピュリズム化した野党も反省して出直しを」
2022年12月29日
「アベノミクス」とはいかなる政策思想でどんな社会現象を起こしたのかについて、さまざまは視点から探るインタビューシリーズ。今回はリベラル派の論客を代表して山口二郎・法政大教授にご登場いただく。
山口氏はかつて民主党政権の政策ブレーンであり、最近では立憲民主党や共産党など野党共闘のつなぎ役の一人でもあった。自民党政治には批判的な立場から、政権交代の起こりうる政治システムをめざして今も政治論争を続けている。その目から見て、長期政権化や官邸主導、1強体制づくりに成功した安倍政権はどう映っているのか。野党にくみ取るべき教訓はあったのか。アベノミクスが壊した政治の秩序を立て直すことはできるのか。意見を聞いた。
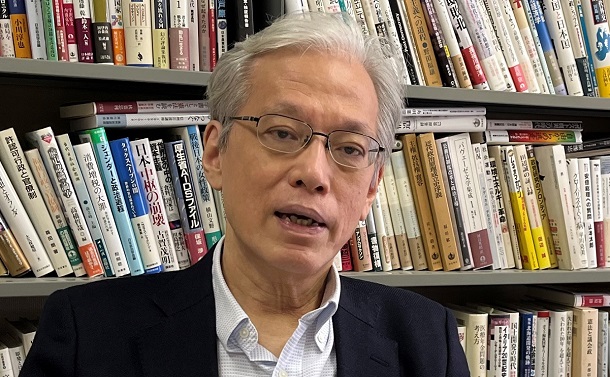 山口二郎氏
山口二郎氏〈やまぐち・じろう〉 法政大学法学部教授(政治学)。1958年生まれ。東京大学法学部卒。北海道大学法学部教授を経て現職。主な著書に『大蔵官僚支配の終焉』『政治改革』『ブレア時代のイギリス』『政権交代とは何だったのか』『若者のための政治マニュアル』など。
――民主党政権の失敗の顚末(てんまつ)を知る山口さんから見て、安倍政権が長期政権化に成功した理由はどこにあると思いますか。
「いくつかあると思います。まず文化的、社会的な面から話しましょう。2009年の政権交代までの民意は、よりよい未来とか別の社会像とかを求めてさまよっていました。たとえば民主党政権が掲げた『生活第一』は、僕の言葉でいえばリスクの社会化路線ですが、そういうものに期待する意識が国民にありました。80年代の中曽根改革、90年代の細川政権の政治改革、橋本政権の6大改革、そして2000年代の小泉改革と、オルタナティブを求めてそのときそのとき次々に魅力的にみえるものを民意は選んできました」
「しかし民主党政権の挫折と東日本大震災によって、より良い未来に対する決定的な絶望というかあきらめというか、それが日本人を覆ってしまいました。内閣府が毎年おこなっている社会意識に関する世論調査からも、2010年代前半に驚くべき民意の転換が起こっていたことがわかります。2000年代は『満足していない』が『満足している』を15~20ポイント上回っていましたが、2013年に逆転し、14年以降は『満足している』が上回る状態が続いています。物的豊かさや精神的充実感がそれほど大きくなくとも、平穏無事な生活を続けられることで満足するようになっていったと考えられます」
「より良い未来が構想できないなら政治には継続安定を求めるしかない。そういう声が安倍政権を支えたのだと思います。安倍政権が何かをしたから支持されたのではなく、より良い未来がないから、もうこのくらいでもいいという現状への満足とか、あきらめみたいなものに民意が転換したまさにその時に、その波の上を安倍政権がサーフィンしてきたようなものです」
「そこに加えて、過去への回帰というものもあったと思います。国民がみなナショナリズムに流れたとは思いませんが、経済的な発展とか技術的な進歩に期待できない時代になると、自分の国とか文化に誇りをもちたいという気分がだんだん高まってくるわけです。それも安倍政権を支えたものです」
――他にはどんな理由がありますか。
「政治要因で言えば、オルタナティブ(代替できる選択肢)を示す政治的プロジェクトが挫折してしまったことです。民主党政権だっていいことはいくつもやったのに、そういう記憶は全部流しさられてしまいました。大震災の衝撃の影響もあるが、民主党自身も政権の座にありながら党が分裂するなんていう、およそ政治家としてはありえない愚行をやったわけです。(自民党の)オルタナティブであることをみずから放棄しちゃった」
 政権交代を果たして発足した鳩山由紀夫内閣。首相官邸で記念撮影=2009年9月16日
政権交代を果たして発足した鳩山由紀夫内閣。首相官邸で記念撮影=2009年9月16日「最たるものが、小沢一郎氏が党を飛び出したことです。あれが最大の罪でした。政党政治というのはいつだって山あり谷ありで、浮き沈みがあります。世界中のどの政党だって冬の時代に耐えると、次には政権交代のチャンスがめぐってくる。そういうサイクルがあるわけです。そのためには、政党は逆境のときも我慢して人材を育て、政策を構想しておくことが必要です。ところが民主党政権は政権の座にありながら党が分裂してしまい、わざわざ権力を敵方に譲り渡すということをやってしまった。およそ政党政治の体を成していなかったということでしょう」
「経済的な理由をあげれば、安倍政権時代はそれなりに景気が良かったということでしょう。第二次安倍政権が発足して間もないころ、立命館大教授だった高橋伸彰さんを招いて研究会をやったとき、アベノミクス批判派でもある高橋さんがこう言っていました。『景気はこれからちょっとずつ上向きそうだ。小泉政権のときもそうだったが、景気が上向き始めたときにできた政権というのは長持ちするものだ』と。その予言は当たりました。好景気が安倍政権を支えたのはまちがいないでしょう」
――その意味では安倍政権はツイている政権でした。
「大震災の後で国民の期待水準がどん底まで落ちちゃっていたところから始まった政権でした。だから劇的に世の中を良くしなくとも、そこそこうまくやっている、という評価を受けることになったのでしょう」
――日本をもう一度元気な経済大国にする、という安倍政権のスローガンが国民受けした背景には、国内総生産(GDP)で2010年に日本が初めて中国に追い抜かれたことも大きかったのではないでしょうか。日本人のマインドセットからすると、経済力で格下だと思っていた中国に逆転されたことはかなりショックだっただろうと思います。
「米国を除けば、日本が経済的にはナンバーワンだという自意識は高度成長の時代以後、長い間、日本人にはありましたからね」
――「日本人はこんなにすごい」という類いの本が売れるようになったのはその後です。安倍政権がそういう空気にシンクロしたのではないですか。
「そうですね。日本経済の実態としては縮小していく一方で、意識においては夜郎自大というか、自己肯定が肥大化していくというか。そこの逆説がちょうど安倍政権の発足と重なったということでしょうか。『日本を取り戻す』というような安倍政権のキャッチフレーズは具体的な中身がなくても、ある部分の人々には届いたのでしょう」
――安倍政権の政治資産を蓄えた最大のエンジンはアベノミクスだったと言われます。
「私は経済学者ではないので、アベノミクスの政策的な中身に立ち入った分析はできませんが、やはり日銀の異次元金融緩和というのは安倍さんの狙いを実現させるのに有効だったのではないですか。どんどん日銀券を発行して国債を買いこんで、円安に誘導して、輸出企業をもうけさせる。株をもっている人は株高で恩恵に浴したし、そうじゃない人も毎日ニュースで日経平均が上がったというのを見ているわけです。株価は4けただったのがやがて1万数千円になり、2万円に上昇していった。こういうのを見ていると、何か国が豊かになったみたいな幻想をもつのでしょうね」
――安倍元首相が最も気にしていたのは支持率とともに株価だったそうです。株価が上がったことは政権にとって大きい意味があったでしょうね。
「政権の経済運営のシンボルですよね。所得がたいして良くなっていなくとも、株価さえ上がれば、世の中全体として豊かになっているような雰囲気になるのではないですか」
――実はアベノミクスというのは、体系があるようでない政策です。
「3本の矢(大胆な金融緩和、機動的な財政出動、成長戦略)の貼り合わせですからね。スローガンも、「一億総活躍」とか「女性が輝く」とか、取っ換えひっかえで、新しいものが出ては消えていく。その繰り返しでした。それで新機軸をいろいろ打ち出しているイメージは作れたのでしょう」
――アベノミクスの本質は、日銀が紙幣を刷って政府財政を支えた「財政ファイナンス」でした。
「伝統的には禁じ手とされたことですね」
――実は第2次安倍政権下で「アベノミクス」という呼び方で新聞に見出しをつけて記事を書いたのは私が初めてでした。「アベノミクス、高成長の幻を追うな」という記事です。かつてレーガン米大統領がやった経済政策が、矛盾した、ろくでもない政策という意味で「レーガノミクス」と揶揄(やゆ)されたのですが、私も安倍政権の経済政策をアベノミクスと呼んで揶揄しようとしたのです。ところが、安倍元首相が何百回、何千回と「アベノミクスの成功」「アベノミクスの果実」と繰り返しているうちに、国民には「アベノミクスはすばらしい政策だ」とすり込まれてしまいました。
「株価の上昇や企業収益の好調さが結果的にそれを支えることになったのですね」
――経済専門家の分析でも、アベノミクスと円安・株高の因果関係がどこまであるのかは実は微妙です。一方で、これだけ異常な財政ファイナンスがおこなわれていても、メディアも国民もたいして問題視してきませんでした。
「私は、日本国民に『正常性バイアス』が働くようになったためではないかと考えています。
――「正常性バイアス」とは?
「災害や事故が迫っていても自分だけは大丈夫だろうと思い込み、危機を回避する行動をとらない心理のことを心理学ではそう呼びます。よりよい未来はありえない、という意識が国民のなかに浸透してくると、こんどはうそでもいいからある種の安心感をもちたくなる。マインドのなかに秩序を作りたいと思うようになるのです。人は不安のなかで生き続けることはできません。現状肯定とか、自己正当化という心理が働くようになります。その結果、不都合な現実から目を背けることになるわけです」
――なるほど、以前、ある科学史の研究者から、日本でこれだけ地震が多いのに木造建築が多いのは、何十年に一度は倒壊することもありうるという前提で家を建てているからではないかと聞いたことがあります。日本人にはそういう諦めのようなものがあるのでしょうか。その傾向は海外諸国でもあることですか、日本特有の現象ですか。
「日本特有の現象です。他の国の政治をみれば、最近もそれなりに政権交代とか政治的な変化が起きていますからね。米国だって、トランプ大統領がムチャクチャをすれば、次はバイデン大統領のようにさえない候補でも担がれて、このままでいいのか、という現状に対する疑問や批判の受け皿になっています。それに対しては、偽の選択肢を示して一時的な人気を得ようというポピュリストやデマゴーグも出てきました」
「典型例が英国の欧州連合(EU)からの脱退、いわゆるブレグジット騒ぎです。一時的な人気取りのためにそう主張する政治家たちが出てきたのです。ただ、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください