聞き手:服部桂・朝日新聞ジャーナリスト学校シニア研究員
2011年12月02日
――エルヴィスの時代は、ごく少数のレコード会社とテレビ局があるだけで、そこを経由して音楽を広めるしかなかった。でも、今はインターネットの時代ですから、携帯音楽プレーヤーだけで新作を聴く人、「YouTube」でしか聴かない人など、様々な聴き方が可能になっています。つまり、メディアの激変によってロックやポップスの受容のされ方も産業構造も大きな変化にさらされています。こうしたネット世代以降のロックやポップカルチャーはどうなっていくのでしょうか。例えば、総クリエイター社会というか、プロとアマの区別がなくなって誰でもSNS経由でスターになる可能性が開かれるのか。あるいは、CDをメジャーな音楽会社から出すよりもインディーズだけで食べていけるようになるのか。
 サエキけんぞうさん
サエキけんぞうさんサエキ この本『ロックとメディア社会』(新泉社)でも少し触れていますが、人類史上、生演奏の音楽以外に音楽を伝えるメディアとして楽譜しかない時代が長く続きました。それが、ある時期からレコードの時代になった。それくらい大きな変化が今、起きているのではないか。著作権による秩序が構築された音楽業界のあり方が、大きく変わろうとしています。
もちろん、音楽関係者だからといって霞を食って生きるわけにはいかない。何らかの収入がなければ音楽を作り続けることはできないでしょう。親の遺産や路上で演奏するだけで音楽家が生きていける、という話にはならない。当面はコンサートやライブ、あるいはCDを一定の数で売る、あるいは音楽配信で収入を得るということをするしかない。ただ、私は音楽配信は失敗しつつあるのではないか、チャンスを逸したのではないかと思っています。
――「iTunes」以外は、ということですか。
サエキ いや、「iTunes」も成功したとは思えません。なぜなら、ビートルズの「アンソロジー」が「iTunes」限定で発売されたのですが、全く話題になっていない。新譜を「iTunes」だけで出すインパクトはあまりないのです。
――確かに、ライブにはお金を払うけれど、記録された作品には払いたくない、いくらでもネットに転がっている、という状況になっています。既存の音楽会社は、違法コピーにある程度目をつぶって、広がったところでライブをしたり、ノベルティーグッズを売ったりして、儲けようとしています。
サエキ 物販ですね。それはそれで大事ですが、グッズにならないような音楽も多い。現在普及しているインフラを既成事実として捉えてはいけないし、確実そうに見えるインフラも成功しているとは限らない。私は、今ネット業界で信じられているシステムの半分は、10年以内に瓦解、淘汰されてしまうと思っています。
◆「iTunes」ではなく「YouTube」が音楽文化を担う◆
――映画やテレビ、ラジオなどのジャンルにおいて、音楽という要素が大きな役割を果たしています。それが新しいメディアを普及させる原動力になっている。でも、「iTunes」が今後の音楽文化やネット社会をどのようにドライブしていくのか。音楽を自らの単なる商売道具、ただの添え物にしてしまうのか。何十年も先のことを見通すのは難しいと思いますが、音楽が今後どうなってしまうのか気になります。そもそもロック黄金時代のビートルズのリマスター盤などをノスタルジーよろしく買いまくる旧世代はたくさんいますが、若い人たちが買わなければ過去の音楽や新しい音楽との出会いの場はどうなっていくのか。
サエキ 非常に憂慮すべき状態、とまずは申し上げるべきですが、音楽の普及の仕方という意味では、例えば無料で配るだけでなく、「図書館が読書体験を広める」という形もあります。現在、「YouTube」でものすごくたくさんの音楽を聞くことができるわけで、いわば「ウルトラルーツ志向」とでも言うべき豊かな音楽体験が可能になっています。例えば、私も、エルヴィス初テレビ出演の「トミー・ドーシー・ステージ・ショウ」の全6回分なんて「YouTube」で見たわけです。これを市販のDVDで見ようと思ったら大変難しい。「エド・サリヴァン・ショー」なら見ることができると思いますが、「トミー・ドーシー・ステージ・ショウ」となるとマニアのお宅か米国テレビ局のアーカイブで探すしかないでしょう。このようにネットで音楽に触れるには、聴く側に調べる気があるかどうかがポイントです。
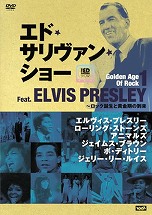 エド・サリヴァン・ショーのDVD(ビデオアーツ・ミュージック)
エド・サリヴァン・ショーのDVD(ビデオアーツ・ミュージック)今回の本のワールド・ミュージックの項でも書いたのですが、ネット化、グローバル化によって音楽の受容機会が自然に増えると思われていました。でも、それは幻想でした。新しい音楽が広まる際には、汗を流してそれを広めようとする行為がなければ広まらない。単に音楽流通のインフラを用意して、「ここに置いてあるからクリックして下さい」というだけでは広まらない。
私のところにも、よくそうやって「自分の作った音楽をクリックして聴いて下さい」というメールが来るのですが、普通はなかなか聴かない。相手にどうしても聴いてもらいたいなら、やはり最低限、CD-Rに焼いて送るしかない。あるいは、美女のヌード映像つきだから、それを見ながら聴いて下さいという案内があれば聴くかもしれない(笑い)。また、非常に親しい人、恩人の紹介なら聴いて感想を送るでしょう。そうした、何かやむにやまれぬきっかけがない限り、単にクリックして音楽を聴くというシンプルな仕組みだけでは、いくら簡単に購入できるシステムだったとしても音楽は売れない。今ならネットでキンシャサのヒットチャートからアラスカの現地住民の音楽まで何でも聴けるわけですが、ワールド・ミュージックは日本で広まらなかった。
私が一瞬だけうれしかったのは、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください