ティモシー・ブルック 著 本野英一 訳
2014年08月28日
最初に、はっきりお伝えしたい。本書には2年前再来日し人気をさらに高めた『真珠の耳飾りの少女』について、ささやかな言及はあるけれど、図版はない。精緻な技法について高い評価を与えているけれど、詳しい分析はない。それゆえ、もし画布にとどめ置かれた光と色の魅力について、じっくり語ってもらいたいのなら、小林頼子氏など日本人専門家が書いた良書を読むのをおススメします。
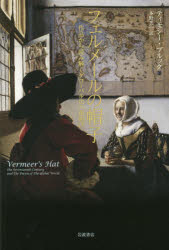 『フェルメールの帽子――作品から読み解くグローバル化の夜明け』(ティモシー・ブルック 著 本野英一 訳、岩波書店) 定価:本体2900円+税
『フェルメールの帽子――作品から読み解くグローバル化の夜明け』(ティモシー・ブルック 著 本野英一 訳、岩波書店) 定価:本体2900円+税『フェルメールの帽子――作品から読み解くグローバル化の夜明け』(ティモシー・ブルック 著 本野英一 訳、岩波書店)
中国史が専門の著者は言う。「このようなオブジェたちに思う存分語らせること」で、「絵画作品の解題をするのではなく」グローバルな現代世界で呼吸する「われわれ自身の物語に利用すること」が可能なのだ、と。
扱われるフェルメール作品(口絵あり)は、『デルフト眺望』『兵士と笑う女』『窓辺で手紙を読む女』『地理学者』『天秤を持つ女』の5点。
これらの傑作を糸口にして、オランダ人がいかにして「世界地図」を広げていったか、すなわち、17世紀のヨーロッパと非ヨーロッパ世界の間で急速に進んだグローバルなモノとヒトの流れについて、じつにワクワクする歴史を垣間見せてくれる。
例えば、陶磁器と金銀。いずれもヨーロッパ産でない商品がヨーロッパ人によってさらなる価値をもつ交換のしくみ、そこにかかわる無名の中国人たちの一筋縄で捉えられない交流の実態が、動画的に描出される。日本も点景ではない。銀産出国という役割はもちろん、多国籍商船の一員としても登場する。
そうしたモノとヒトが、中国史家ならではの文献の引用を伴って、めざましく活写されていく。提示された質量の大きさにもかかわらず、先へ先へと読み進まずにはいられない(翻訳も良い)。
筆致がもっとも雄弁なのは、書名にもなっている「帽子」(原題も『Vermeer’s Hat』)の来歴を語る第2章。材料となったのは、著者の出身地でもあるカナダ東部の森林地帯で捕獲された、ビーバーの毛皮だ。やがて北米大陸に殺到するヨーロッパ人たちの嚆矢となったフランス人探検隊の物語が語られる。行間から、現地人を震え上がらせた火縄銃の轟音が響き、硝煙の匂いも立ち上るかのよう。
フェルメールが描かなかったモノとヒトについても、別章を立てて鮮烈に綴られている。
タバコと、奴隷として売買されたアフリカ系の人々。前者は、フェルメールを生んだデルフトで作られた贋作中国製磁器の図柄によって、後者は、同時代の画家ファン・デル・ブルクが描いた人物画(構図は似ているが画力も人物の魅力もフェルメール作品には比ぶべくもない作品)によってだ。
著者は、こうしたマガイもの・粗悪品であればこそかえって明瞭に伝える当時の嗜好・風俗にも目を配っている。
本書を読んでもフェルメール作品の輝かしさはゆるがない。むしろ、画布にとどめ置かれたのが光と色だけでないことに感銘を受ける。そして、17世紀オランダの野心が獲得した恐るべき多様な「産物」(女性の微笑もその一つ)が、一人の天才の絵筆を通すことで、あたかも蒸留され熟成された類まれな「美酒」に生まれかわったことを実感する。
訳者によれば、20世紀末以降、世界経済が初めて一つになった17世紀前半への関心は、英語圏の研究者間で高まっており、中でも気鋭の一人が本書の著者であるらしい。おそらく邦訳は本書が最初となるこの著者が、今後ともこうした構想力豊かな好著を出してくれるのなら、必ず読んでみたい。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください