ニコラス・フィリップソン 著 永井大輔 訳
2014年09月04日
邦訳で400ページ近い大著だが、じっくり読むに値する本。アダム・スミスの伝記であるのは事実だが、タイトルが示すとおり、スミスの思想がどのように生まれ、どのようにはぐくまれてきたかを、広く歴史的、そして空間的コンテクストの中に位置づけ、実に明快に解明するものである。まさに「スミスの思想の伝記」と呼ぶにふさわしい。
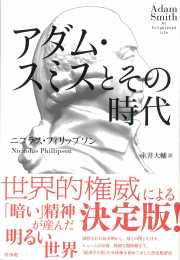 『アダム・スミスとその時代』(ニコラス・フィリップソン 著 永井大輔 訳、白水社) 定価:本体2800円+税
『アダム・スミスとその時代』(ニコラス・フィリップソン 著 永井大輔 訳、白水社) 定価:本体2800円+税『アダム・スミスとその時代』(ニコラス・フィリップソン 著 永井大輔 訳、白水社)
社交性の問題を考えてきたのに、本人は決して社交的とは言えない男である。家族関係と言えば、母を大事にしたことだけが目立つ。恋愛も結婚もしたことがないようだ。
それに加えて、書いたものを秘匿したり、焼却したりする癖がある。手紙は書いているが、決して筆まめではない。おもしろいゴシップなど皆無。
もちろん、生まれ故郷のスコットランドでは、田舎町カーコーディでの生い立ちを皮切りにして、グラスゴーでの学究生活、エディンバラでの講義や晩年の生活などがあるが、それらはもっぱら彼が勉強ないしは講義をする場所でしかなかった。
ただし、大学に籍を置いて研究教育に携わったときでも、さまざまな大学の雑用をこなさなければならないとなると、それらをきちんとやり遂げている。実に見事なものだ。
オクスフォード大学に学んだことはあるが、この時代のオクスフォードが学問とは無縁の世界だったので、もっぱら独学である。
ロンドンに行ったこと、家庭教師として大陸に同行したこともあるけれど、それらの場所で何かおもしろい事件に出くわしたこともない。ただ、ものを考えて自分の思想体系を構築することに精を出すだけだった。だとすれば、思想の伝記にならざるを得ないだろう。
しかし、その思想をはぐくむ上でよかったのは、スミスが生きた時代と場所だった。
まず、啓蒙主義が広まって、フランシス・ハチソン、デイヴィッド・ヒューム、バーナード・マンデヴィル、そしてフランスの百科全書派などが優れた考察を発表したこと。とりわけヒュームの影響は大きなものがある。同時にこの啓蒙主義がスコットランドにも影響を与え、グラスゴー、エディンバラに学問の発達が見られたことも大事である。
こうして本書は、まさにこの啓蒙の申し子であるアダム・スミスの思想形成を見事に描いているのだが、その際に特に焦点が当てられているのが『国富論』ではなく、『道徳感情論』であることも見逃してはならない。
日本におけるアダム・スミス研究にとって、この本の視点は重要な役割を果たすだろう。きちんとした訳文で読めることも大いにうれしい。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください