スティーヴン・ストロガッツ 著 冨永星 訳
2014年09月11日
数学なんて苦手と、学校の授業では落ちこぼれたものの、何か値打ちのあるものを手に入れそびれたという悔いが残り、再挑戦してみたいと思う大人たち……に向けて、電子版「ニューヨーク・タイムズ」に連載された15編の数学コラムに、さらに書き下ろしの15編を加えてまとめられたのが本書。
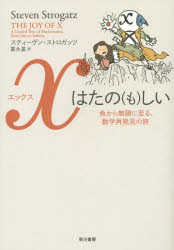 『xはたの(も)しい――魚から無限に至る、数学再発見の旅』(スティーヴン・ストロガッツ 著 冨永星 訳、早川書房) 定価:本体2200円+税
『xはたの(も)しい――魚から無限に至る、数学再発見の旅』(スティーヴン・ストロガッツ 著 冨永星 訳、早川書房) 定価:本体2200円+税『xはたの(も)しい――魚から無限に至る、数学再発見の旅』(スティーヴン・ストロガッツ 著 冨永星 訳、早川書房)
最近、仕事上の必要があって、そのごくごく一部を、読んだりチラ見したり、挑んだものの挫けたりした。
そんなサンプル数の少ない経験から言うのもなんなのだが、本書を、この手の本を初めて読む人の「最初の1冊」としてお勧めしてもいいんじゃないかと思う。
なぜなら、本書の説明は本当にわかりやすくて、おもしろい。まず「積分とは、複雑なものを薄切りにし、さいの目にして足しやすくすること」といったイメージの掴ませ方が上手い。
そしてそうやってイメージを持たせた後、もうちょっと踏み込んで説明してくれてもいいんじゃないかと思う手前で終わらせる、寸止め感がほどよい。
実はこれは大事なことで、数式とか証明とか、専門家としてはぜひ言っておきたい基礎的なことも、読者にとってはすぐ迷宮に転じてしまう。ここに踏み込まないことは、読者に「わかった。読み通せた」という心地よい読後感を与える、大きなポイントなのだ。
さらには文章も洒脱で、啓蒙書にありがちな「わかりやすさをねらった結果の、子どもを相手にしたような幼稚な語りかけ口調」にも堕していない。
そうやって巧みに解説される数学の話題は、「そうなのか!」という数々の驚きに満ちている。
算数レベルでは、なぜ-1×-1はプラスになるのか? なぜ円の面積は半径×半径×Π(パイ)なのか? ハイレベルなところでは、無限にも「大きい無限」と「小さい無限」があるとはどういうことなのか?
もちろん驚きのポイントはもっと多彩で、読み手のレベルに応じて、また再読して理解が深まることで、世界にひそむ美しい秩序の扉を、ひとつひとつ開けていくような体験を味わうことができる。
各コラム読み切りで、どこから読んでもいい体裁になってはいるけれど、決して寄せ集め的雑学ではない。算数レベルから、グーグルのページランクの基礎になっている「線形代数」や量子論の大きな発展をもたらした「群論」など最先端の知まで、正統な数学の体系に触れることができる構成になっている。
なので、難しいところは読み流してかまわないので(←私もそうでした)、ぜひ最後まで読み通してほしい。
古代メソポタミア人やギリシャ人が、日常生活の必要からつくりだした「数」という道具が、自生的に精緻で壮大な秩序をつくりだし、その秩序がなんと、物質の起源から天体の動きまで、森羅万象を統べていることの不思議。
読み終えると、本書冒頭で紹介されている「数はいったいどこから来たものなのだろう。はたして人間が発明したものなのか。それとも発見したものなのか」という問いの深遠さに、あらためて感銘を受けるのだ。
おまけとして付け加えれば、本書の原題は『THE JOY OF X』。1972年にイギリスで刊行されて800万部を超える世界的ベストセラーになった『THE JOY OF SEX』のパロディ的タイトル……とは、本書のどこにも書かれていないけれど、絶対そうですよね。そのセンスも、私は大好きです。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください