ジャック・アタリ 著 的場昭弘 訳
2014年09月25日
マルクスを読んだのは1968年から72年にかけての学生時代だけである。
あのころの学生運動は、なにかといえば革命を呼号し、マルクスやレーニンの理論をもちだしたものだが、ぼくは革命なるものに、どこかいかがわしさを感じていた。どう考えても、革命というのがよくわからなかったのだ。
『世界精神マルクス』(ジャック・アタリ 著 的場昭弘 訳、藤原書店)
1972年に連合赤軍事件がおこると、マルクス熱もすっかり冷めてしまい、それ以来マルクスを読むこともなくなってしまった。マルクスはどこかまちがっていると思うようになり、しかし、どこがまちがっているかを言いきれないまま、今日まで馬齢を重ねてきた。
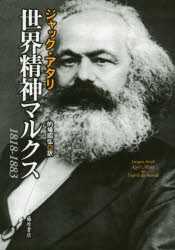 『世界精神マルクス』(ジャック・アタリ 著 的場昭弘 訳、藤原書店) 定価:本体4800円+税
『世界精神マルクス』(ジャック・アタリ 著 的場昭弘 訳、藤原書店) 定価:本体4800円+税著者のアタリはフランスの経済学者で思想家。
ミッテラン大統領の補佐官となり、欧州復興開発銀行総裁として活躍し、つづく歴代フランス政権でもアドバイザーを務めてきた。『アンチ・エコノミクス』『21世紀の歴史』『危機とサバイバル』など数多くの著作がある。
この伝記を執筆した最大の動機は、マルクスにたいするいくつかの誤解を解くことだったという。
マルクスを「20世紀の最悪の虐殺の、ある種の責任者」として紹介するのはまちがいである。
また、共産党一党独裁政権のもとでの計画経済、言い換えれば国家の指令にもとづく生産・分配システムという発想は、マルクスの考えとまるでちがっている。マルクスはなによりも自由の思想家なのだという。
マルクスは資本主義をたえずグローバル化していくものと考えていた。だから、マルクスにとっては、資本主義に対抗して社会主義があるわけではない。資本主義が限界にまで発展した先にやってくる体制が社会主義になると想定していたというのだ。
だとすれば、社会主義は終わったわけではなく、むしろこれからはじまるということになる。
国家と資本の廃棄をマルクスは唱えた。しかし、それは人びとが現在の国家の枠組みから解放され、すべての人が資本を活用できる時代がいつかやってくるという意味だった。
世界万民のための国家、世界万民のための資本というのが、マルクスのめざす方向だったとしたら、これはスターリンや毛沢東が実行した社会主義のイメージとはずいぶんことなる。
本書はマルクスの思想解説書ではなく、マルクスの伝記である。
これまでマルクスの伝記は何十と書かれてきたが、聖人伝になるか偶像破壊になるかのどちらかで、適当な距離を置いたものはほとんどなかった、と著者はいう。
そして、社会主義体制が崩壊し、マルクスの思想が権力と関係しなくなったいまこそ、マルクスを冷静かつ真剣に語れるようになったのではないかと述べている。
大冊ではあるが、ひじょうに読みやすい。マルクスの生涯も、貧乏に苦しむ一家の様子も、スキャンダルもさらりと書かれている。その後の権力闘争のなかで、マルクスの思想がいかにゆがめられていったかについても、ふれられている。時代背景もよくわかる。
大学で法学と哲学を学んだマルクスは、最初大学教授になるつもりだった。しかし、希望はかなえられず、ジャーナリズムの道を進みはじめる。ライン新聞の編集長となり、プロイセン当局と対立し、ドイツを追われたあと、パリで雑誌を発刊するものの、まったく売れなかった。それどころか、その過激な主張によってパリを追放され、ブリュッセルにやってくる。
1848年は革命の年だ。30歳のマルクスはロンドンで誕生した共産主義者同盟に依頼され、その宣言を執筆する。それが「共産党宣言」で、「全地域の労働者よ、団結せよ」がスローガンとなった。
革命の年、マルクスはエンゲルスとともにケルンに行き、ドイツの民主化を求める新聞を発行する。だが、ドイツでもフランスでも革命は弾圧され、一家はイギリスに亡命する。ロンドンでは貧困にさいなまれ、6人の子どものうち3人をなくした。
マルクスという人は、一生おカネとは縁がなかった。『経済学批判』と『資本論』第1巻は、いずれも1000部印刷して、まったくといっていいほど売れなかった。
『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』の通信員として、わずかに原稿料を稼いだが、たかが知れていた。一度、鉄道の事務員になろうとして応募したが、字がきたないという理由でことわられている。
工場経営者の息子だったエンゲルスからの毎月の援助と、わずかな遺産で糊口をしのいだ。それでもめげなかったのは、世界を変える本を執筆しようという情熱があったからである。
インターナショナルではバクーニンやプルードン主義者とたたかった。マルクスの3人の娘たちはいずれもパリ・コミューンの闘士たちとかかわり、悲劇の人生を歩む。生前、『資本論』の続刊はついに完成せず、エンゲルスとカウツキーが、残されたノートをまとめた。
マルクスとは世界精神にほかならなかった、と著者はいう。
それは国家や資本の側ではなく、民衆の側に立って、世界を根源から問うという精神だ。著者がのべるように「すべての人間が世界市民となり、最終的には世界は人間のために作られることになろう」というのが、マルクスの目標だったとすれば、たしかに、その灯はすっかり消えてしまったわけではない。マルクスを見直すための1冊である。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください