トマ・ピケティ 著 山形浩生、守岡桜、森本正史 訳
2015年01月29日
当初、日本語版タイトルは、『21世紀の資本論』と予告されていたはずだ。それが『21世紀の資本』に変えられたのは、マルクスの『資本論』と印象が重なりすぎるのを恐れたからだろう。実際、『資本論』とは方法も内容も異なる作品だといってよい。
『21世紀の資本』(トマ・ピケティ 著 山形浩生、守岡桜、森本正史 訳 みすず書房)
本書の目的は何か。それは膨大なデータと新たな理論的枠組みにもとづいて、18世紀以降、現在まで、富の分配がどう推移してきたかを分析し、いわれのない格差を生みだしている資本主義を是正する民主主義的な政策を打ちだすことである。
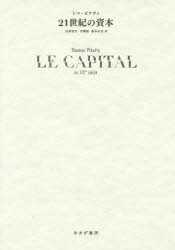 『21世紀の資本』(トマ・ピケティ 著 山形浩生、守岡桜、森本正史 訳 みすず書房) 定価:本体5500円+税
『21世紀の資本』(トマ・ピケティ 著 山形浩生、守岡桜、森本正史 訳 みすず書房) 定価:本体5500円+税1971年にパリ近郊のクリシーで生まれた著者は、ベルリンの壁が崩壊した1989年には18歳で、まったく社会主義に親近感やノスタルジーを覚えたことはないと述べている。
68年五月革命世代の父とちがい、社会主義の幻想とは、はなから無縁だった。
パリの高等師範学校(エコール・ノルマル)を卒業後、米国のマサチューセッツ工科大学で教えてからフランスに戻り、パリ経済学院を設立した。
異様なほど数学モデルにこだわる現代経済学には、ほとんど興味をもてなかったという。「実をいえば経済学者なんて、どんなことについてもほとんど何も知らない」と言い切る。
マルクスの時代以降、資本主義のかたちは大きく変わった。しかし、経済格差を生みだす資本主義の構造は変わっていない。
20世紀半ばに、いったん縮まりかけていた経済格差が、なぜ1980年代以降、ふたたび拡大するようになったのか。著者の関心は、とりわけそのことに向けられている。
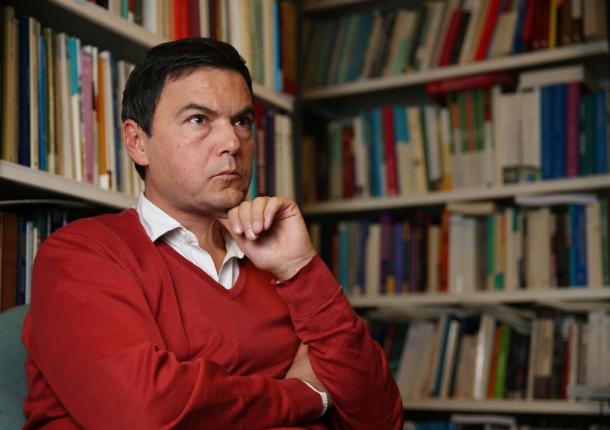 トマ・ピケティ
トマ・ピケティ実際、capitalには資本、元手などのほかに資産、純資産という意味もある。資本はマルクスよりも広義にとらえられている。日本語版で訳されている「資本税」は、会計用語でいう「純資産税」ないし富裕税と理解されねばならないだろう。
資本主義世界は20世紀にどう変わったのだろう。
人口は大きく膨らみ、経済も成長した。中流階級が出現したのも、20世紀になってからである。
機械技術の発展は、生産性の上昇と、平均労働時間の減少をうながした。いっぽう購買力は増大し、生活の物質条件が大きく改善された。食生活や住居、衣服だけではなく、旅行や学習、医療といった面でも、生活は昔よりずっとよくなった。
先進国では、いまや労働者の7割から8割がサービス部門ではたらいている。20世紀の特徴は、サービス部門の発展にあったといってもいい。
その範囲は広く、医療や教育、小売業やレジャー産業、不動産業や銀行業、輸送関連、さらに軍や警察、役所など、多岐にわたる。その分、商品世界が広がったともいえる。
企業活動で資本と経営が分離されたことも、20世紀の特徴かもしれない。企業の帳簿では労働報酬(賃金、賞与、役員報酬)と資本報酬(利益、配当、利子など)がはっきり区別されるようになっている。
資本(資産、富)の形態も大きく変わった。19世紀はじめまで資産の大部分は農地が占めていた。それがイギリスでもフランスでも、現在では、国民資産のうち農地の占める割合は2、3%にすぎなくなり、それに代わって、都市の不動産や企業資産、金融資産が資産の大部分を占めるようになった。
植民地がなくなり、植民地の資産が消滅したことも大きな進展だった。
欧米諸国が世界の中心ではなくなりつつある。いっぽうで、国家が経済社会に積極的にかかわるようになり、保健医療や社会保障、教育などの公共サービスに加え、交通、通信分野での公共インフラ投資をおこなうようになった。
こんなふうに、18世紀から21世紀にかけて、経済社会は大きく変わり、資本(資産)の性格も、それに応じて変化した。
しかし、資本の構造は変わっていない、と著者はいう。現在、人口が停滞し、低成長レジームにはいるなかで、国民所得がさほど増えないのに資本(資産)が膨張するという現象が生じている。所得格差も広がっている。
経済格差は、労働所得と資産所得を合わせた格差から生まれる(所有資産自体にも天と地ほどのちがいがある)。著者の業績は10%の富裕層(とりわけ1%の超富裕層)と40%の中間層、50%の下層にわけて、経済格差の変遷をデータで示したことにあるといってよいだろう。
現在、米国ではトップの10%層が国民総所得の半分を握り、50%の下層はわずか20%の所得しか得ていない。とりわけトップの1%層に超高額の報酬が支払われているが、その理由については、論理的な説明がつかないという。
しかも、少子高齢化の低成長時代においては、過去に生みだされた格差が、相続財産によって、そのまま次世代に継承される傾向が強い。
このような格差を是正するには、どうすればよいのか。
ひとつの方策として、著者はグローバルな累進純資産税の導入を提案している。それがグローバルな税でなければならないのは、タックスヘイブンに多くの資産が流れている可能性があるからだ。その実現可能性や、よしあし、あるいはその手ぬるさについて、多くの議論がある。本書の評価がわかれるところだろう。
しかし、著者が示そうとしているのは、資本主義は変わらないということより、資本主義は変わりうるということなのである。
ユートピアをふりまく抑圧体制にほかならぬ社会主義の可能性を、著者はまったく信じていない。
新自由主義の時代は終わり、脱格差の時代がはじまろうとしている。格差の問題を抜きにして、もはや経済は語れなくなった。
社会が国家化されるのではなく、国家が社会化されなければならない。本書がベストセラーになっているのは、著者の悲観的な見通しにもかかわらず、将来に向けての希望が、あちこちに隠されているからだろう。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください