池内紀 著
2015年04月16日
カフカの翻訳で知られる池内紀さんの旅の本は多い。『ドイツ 町から町へ』『ニッポン発見記』『町角ものがたり』『ひとり旅は楽し』『なぜかいい町一泊旅行』『川を旅する』『ニッポンの山里』『ニッポン周遊記』……まだまだたくさんある。
ということは池内さんの旅のエッセイには相当数のファンがいるということだろう。なにが魅力なのだろうか。
池内さんの旅の心得というか楽しみ方は、この本を読めばよくわかる。
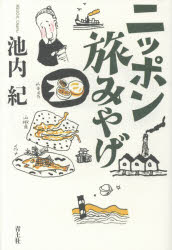 『ニッポン旅みやげ』(池内紀 著 青土社) 定価:本体1800円+税
『ニッポン旅みやげ』(池内紀 著 青土社) 定価:本体1800円+税例えば、かつては絞り染めの問屋が軒を連ねた愛知県有松の蔵造りの町並みに息を呑み、旧札幌控訴院(現・札幌市資料館)の石造りの壁や彫刻・レリーフを愛(め)で、伊那(長野県駒ヶ根市)の町角にある昔ながらの仕立て屋のたたずまいに心を動かす、といった具合。
美しさや風格のあるものにだけ関心があるわけではない。おや?と思うヘンなものにもアンテナを張りめぐらす。
中軽井沢の喫茶店では絡まりあった二つの人像、静岡の丸子の宿では奇怪な仮面をつけた等身大の鉄の人形を見つけて、何のためにそんなものが作られたのか、さまざまに思いやり、想像をふくらませるのである。
富士吉田市の民家の門の柱に「誉之家」の鉄製の文字盤が打ち付けられているのを見て、いつの時代の戦死者を顕彰したものか思いをめぐらす。
鉄製であることから日中戦争以前、日清か日露戦争のものと推測しているが、こういう「歴史の置きみやげ」の発見も旅の醍醐味なのだ。
そして、スケジュールや目的地にはとらわれない旅をする。なにか気にかかるものに出会えば、すぐに寄り道する。横浜では中華街へ向かう道にホテル・オリエンタルという古ぼけた3階建ての建物、栃木県黒磯市では銀行を再利用したレストラン、奈良では大仏池の西側に工場跡のカフェを見つけて、しげしげと観察する。
どこか味のある古い建物が好きなのである。情報よりも自分の目や耳、鼻、つまり五感を大切にする。
のんびりした時間を過ごすことで、自分との対話が生まれ、狭いと思いこんでいたニッポン列島が2倍、3倍に広がってくるという。
池内さんの旅の本には、誰でも知っているような観光名所はめったに出てこない。かといって、ツアーでもなければ行けないような僻地・秘境が紹介されるわけでもない。この本で取り上げられるのも、多少の不便を我慢すれば公共交通機関を使って行けるような、そんな場所である。
線路があれば列車、なければバスを使い、そして歩く。この本では40の旅先が紹介されているが、それぞれに「アクセス」が付いている。八王子市恩方にある「三等郵便局」では、「JR高尾駅よりバスで三十分、郵便局前下車」がそのアクセス。
三等郵便局はいまは特定郵便局と改称されているようだが、世襲制の家族経営の郵便局で、私の田舎などでは当主はただ「局長さん」とだけ呼ばれていた。それが八王子にもあるのだ。もっとも、バスは1時間に1本、高尾駅から30分の場所となると、ここも立派な田舎ではある。
また、祭りの見方は、まず、近くに泊まること。夜が楽しめ、祭りのあとが見学できるからである。次に出口から入ること。入口には参詣客が列をなしているが、出口は空いているからである。最後に祭りのあとを見ること。翌朝の光景に見るべきものがあるという。
池内さんの訪ねる、へんてこな(失礼!素敵な)場所を実際に辿ろうとする読者はあまりいないのではないかという気もする。
この本の読者たちは、あんなものが残っているのか、こんな旅の楽しみ方があるのかと感心しつつ、とりあえずはみやげ話に耳を傾けて、来るべき自らの旅へと夢をつむいでいるのではないだろうか。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください