デイビッド・シャンボー 著 加藤祐子 訳
2015年07月23日
憶測でものを言うのは避けたいが、今回の安保法制は日本側の発案というより、アメリカ側の要請にこたえたものという気がしてならない。
実際のところ、自衛隊はとっくにアメリカの世界戦略に組み込まれていた。新法制は、それをさらに推し進め、米軍が海外で戦うさいに、日本軍を常にその後方部隊として活用できるようにすることを目的としている。
自衛隊の活動範囲は日本の周辺だけではなく、アジアから中東、さらにはアフリカの一部におよぶだろう。米軍とともに戦うことは、自衛隊に交戦権を認めるもので、明らかに憲法に違反しており、安保法制は憲法改正を先取りしたものといってまちがいない。
ふり返ってみれば、ベトナム戦争にせよ、イラク・アフガン戦争にせよ、アメリカはこれまで正しい判断のもとで正しい戦争を戦ってきたとは、とても思えない。
もし今後、集団的自衛権の名のもとに、自衛隊が常にアメリカの戦場に関与することを余儀なくされるとすれば、日本の安全がより保障されるどころか、国内ではかえって危険性が増し、社会全体が抑圧的な雰囲気に包まれるようになる可能性が強い。
さらに気になるのは、安保法制を容認する意見のなかで、中国に対抗するには、日米同盟を強化し、自衛隊が米軍にいっそう協力する体制をつくらなければならないという声が聞かれることである。
コメンテーターのなかには、安保法制で「仮想敵国」中国の脅威に備えなくてはならないと主張する人もいる。これは冷戦時代の中国「封じ込め」政策への逆戻りそのものではないだろうか。戦争への備えこそ平和であるという気分が蔓延するのは、とても不幸なことだ。
ところで、本題の書評に立ち返ると、本書の真骨頂は、中国がほんとうに「脅威」なのかどうかを問うているところにある。
『中国グローバル化の深層――「未完の大国」が世界を変える』(デイビッド・シャンボー 著 加藤祐子 訳 朝日選書)
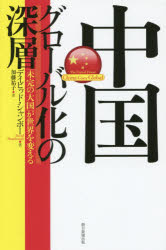 『中国グローバル化の深層――「未完の大国」が世界を変える』(デイビッド・シャンボー 著 加藤祐子 訳 朝日選書) 定価:本体1800円+税
『中国グローバル化の深層――「未完の大国」が世界を変える』(デイビッド・シャンボー 著 加藤祐子 訳 朝日選書) 定価:本体1800円+税1980年以降、中国は改革開放政策によって、長期にわたり急速な経済成長を遂げ、国力を増強させてきた。しかし、著者によれば、その外交政策は、狭い国益と共産党一党独裁政権を守ることに汲々としていて、とても世界をリードするまでにはいたっていない。
経済でいうと、中国は国内総生産(GDP)第2位の大国にのしあがったものの、輸出は低価格消費財中心で、国際市場でのブランド力はさほどなく、金融サービス面も遅れていて、見かけほど強くないという。
さらに急速に拡充される軍事力にしても、その活用範囲は、ほとんど中国国内と東アジア沿岸部にかぎられているという。
それでは、中国は「脅威」ではないのだろうか。
脅威でないとは断言できないだろう。そもそも脅威は、国と国の関係において発生するものだ。ある国が別の国を脅威と感じれば、脅威が発生すると考えてよい。
中国もまたこれまで世界からの脅威を感じてきた。中国が軍事力の近代化と拡充をはかるのは、主としてアメリカの脅威に対抗するためであり、中東石油のシーレーンを守るためであり、国内の治安を維持するためだ。
しかし、日本や韓国、台湾、東南アジア諸国からすれば、中国の軍備拡張は、やはり脅威と映るにちがいない。
本書の想定する最悪のシナリオは、中国が内政問題と割り切って、台湾を武力制圧する場合である。
軍事的観点からみれば、中国が台湾を占領するには、まず台湾上空の制空権を握り、何十万の部隊を台湾に上陸させねばならない。その前に、台湾を海上封鎖し、アメリカの介入を防ぐことが必要になってくる。
そして、もし仮に中国が台湾侵攻を意図しているとすれば、台湾やアメリカも万一の事態に備えなくてはならなくなる。
そのとき安保法制のもとでは、日本がどう対応するのかという新たな問題も生じてくるだろう。
日本の自衛隊は、米軍の指揮下で、中国と戦う姿勢をとるのだろうか。集団的自衛権を認める新法制のもとでは、台湾海峡に万一不測の事態があれば、いままで以上に、GDP世界1位のアメリカと3位の日本が、2位の中国とにらみあう事態が生じる。
さらに、それがロシアを巻き込んでいくとなると、キューバ危機の再来どころか、第3次世界大戦に発展する事態を招きかねない。
こうした最悪の事態は、なんとしても避けねばならない。集団的自衛権による日米の協力は抑止力としてはたらき、最悪の事態を回避するのに役立つという見方もある。しかし、かならずしもそう言い切れないのは、こうした「封じ込め」政策が、双方に疑心暗鬼を生じさせ、かえって対立をあおる結果を招く可能性があるからだ。
中国脅威論に不安を覚え、むやみに力で中国を押さえ込もうとするのはばかげているというのが、著者の考え方だ。
中国を「封じ込め」ようとする発想はまさに時代遅れだ。それよりも冷静に中国の力と方向、その限界を見定め、うまく中国とつきあっていくほうがよほど賢明だし、将来にも明るい展望が開けると示唆しているようにみえる。
脅威にたいしては、軍事力で対抗する以外にないのだろうか。そうなれば、相互に脅威の連鎖が生じ、脅威が累積していき、ついには沸点で暴発する危険性すらある。
そんなことにならないようにするのが、そもそも外交の役割だった。脅威に脅威をぶつける方策は、一見、勇ましいが、賢明とは思えない。脅威を相互に増幅させるのではなく、それを次第に無化していく工夫は考えられないのだろうか。
それに第一、ソ連時代ともっとも異なるのは、「世界の工場」と呼ばれる中国が、世界経済で実際に大きな役割を担っていることだ。中国にとってアメリカは最大の輸出国であり、日本にとっても中国は輸出、輸入とも最大の貿易相手国になっている。
このように日中間、米中間で経済関係が深まっているのに、そこで中国を封じ込めようという発想は、どう考えても時代錯誤だというほかない。
まして最近の日本は観光立国をめざし、デパートや旅館などは中国人観光客の「爆買い」や宿泊に一途の期待を寄せている。その中国を、今度の安保法制で「仮想敵国」とみなすのは、いささか矛盾していないだろうか。
だいじなのは、国防意識の高まりによって国を閉じることではなく、たがいに国を開くことである。人的な交流もますます盛んになるほうがいい。著者もまた、アメリカに要求されるのは、これからも中国と関与しつづけ、中国を国際秩序のなかに取り込んでいく努力をつづけていくことだと述べている。
歴史の流れとして、中国がこれから民主化していくことは必至だろう。それにはまだまだ紆余曲折があり、多くの混乱があるにちがいない。
しかし、われわれとしては日中不戦を基本理念として、中国の今後を見守っていくほかないと思う。ふたたびアジアで戦争をおこすほど、愚かなことはないのだから。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください