ラズロ・ボック 著 鬼澤忍、矢羽野薫 訳
2015年09月03日
あちこちの書店で平積みになっている黄色い装丁。ベストセラーのようなので見ると、「理想の職場」と名高いグーグルの人事のお偉いさんが書いた本、という触れ込みです。
『ワーク・ルールズ!』(ラズロ・ボック 著 鬼澤忍、矢羽野薫 訳 東洋経済新報社)
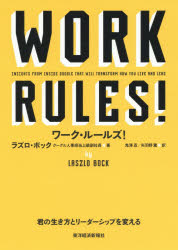 『ワーク・ルールズ!』(ラズロ・ボック 著 鬼澤忍、矢羽野薫 訳 東洋経済新報社) 定価:本体1980円+税
『ワーク・ルールズ!』(ラズロ・ボック 著 鬼澤忍、矢羽野薫 訳 東洋経済新報社) 定価:本体1980円+税この本はとても丁寧に「グーグルが何を考えているか」を解説していました。
でも、とにかくグーグルで働いている優秀な人を賞賛しつづける内容に、少し食傷気味になったのも事実です。
ですが『ハウ・グーグル・ワークス』で人材確保を扱った章は、その「優秀な人」を集めるために絶対に妥協せず、社員全員を採用にあたらせる方法論を記した面白いものでした。
今にして思えばその章に、わが社の人事のトップがどの企業にも応用できるよう詳しく書いた企画を準備している、と予告もされていました。
その企画が『ワーク・ルールズ!』だったわけで、ならばもう一冊付き合ってみようか、とグーグルの人の思惑通りに読むことにしたわけです。
ところがこの本、翻訳は高水準、本文デザインも読みやすく配慮されているのに、読んでも読んでも終わりません。550ページを軽く超える分量で、著者が何を考えて諸制度を設計し、背景にどのような思想を取り込み、どんなフィードバックを得たか、執拗に書き込んでいます。
ある程度は時系列に沿っているのですが、ひとつの制度ごとに丁寧に一連のプロセスを書くものだから、「なんでグーグルの社員食堂のメシはタダなんやろか」という疑問の答えを知るには、450ページくらいまで読み進めないといけません。
その間、著者は何度も何度も新制度のおかげでこんな感謝のメールを受け取った、というエピソードを披露。社員食堂へたどり着く前にお腹いっぱいになります。
さらに注も充実しています。
「雨が降っているときに、走るのと歩くのでは、走るほうが濡れない」という豆知識から、「社員食堂がタダだと近所の飲食産業に打撃では、という批判があるけれど、使う食材は地元のものを優先している」という言い訳まで、普通に読ませる内容です。従ってまた読み進めるのに時間を費やす、という次第です。
イヤミめいたことを書いていますが、じゃあこの本は悪い本かというとぜんぜん違います。むしろ濃密なネタが詰まった、きわめてコストパフォーマンスの高い良書です。本書から孫引きして、安直なビジネス書なら何冊も作ることができるでしょう。
ではなぜ本書はくどいくらい丁寧に諸制度の背景と実行後のフィードバックを書き込んでいるのか。おそらく本書が、グーグルの大方針である「公正」「透明」を自ら実践しているからだ、と私は考えます。
「公正」については、「賞賛される幸福な働きかたはグーグルの特殊例なのではないか?」というツッコミに先回りして、制度導入の具体的なノウハウを詳細に描きます。理屈としては、本書を読めばどの会社でもグーグル的な制度を実践できるわけです。
具体的には「無料の社員食堂」だけではなく、「管理職に無断で、社員が社員にボーナスを払える」「採用基準は『自分より優秀な人』」「社員が自分で肩書きを選べる」などの諸制度が解説されるわけですが、これを実際に導入した結果に起こるイヤな事態も書かれています。
たとえば、社員食堂からタッパーにおかずを詰めて持ち帰る人が出たらどうするか。
そこで「透明」の原則が貫かれます。つまり、起こったことを率直に全社員に開示する。すると「おかずの持ち帰りはやりすぎなんじゃないか」という空気が社内に満ち、だんだんと社員の行動は善意に従ったものになる、のだそうです。
つまり本書は、誰でも実践できるように「公正」な手続きを書き、本当に実践したらどうなるかも「透明」に正直に書く、というスタイルで、自らグーグルの企業文化を体現しているわけです。
加えて、「でも……」と「実践しない理由」を語ってしまう多くの人事担当者に対して容赦はありません。新しい試みに「イエス」という勇気を持てないのは、社員を信用してないと公言するのと同じだ、と厳しい指摘もなされています。
あまり透明ではない諸々のもとで働いている平社員としては、つい「そうだそうだ」と拍手してしまいます。
だけど、「どうすればグーグルに入社できるか」という個人的な関心への答えは、当たり前ですが透明には書かれていません。
もちろん、採用する側から見た基準は書かれています。認識能力テストで高得点を取り、構造的面接で高い評価を得れば採用されるそうですが、グーグルに憧れている凡人が知りたいのはそういうことじゃないですよね。
そういえば、元グーグルの方々を取材したときも、「グーグルの合格基準って何ですか」的な質問は、「守秘義務があるので……」と回答を断られたのでした。
ここは透明じゃないのか、と嘆くべきか、それとも「お前のレベルじゃ話にならないからこう言ってんだよ察しろ」というメタメッセージを受け取るべきなのか。
おそらく後者なんだろうと思うにつけ、自らと「理想の職場」との距離の遠さを痛感してしまう夏の終わりでありました。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください