ジェレミー・リフキン著 柴田裕之 訳
2015年11月26日
本書は、米国の文明評論家でドイツや欧州委員会の経済アドバイザーも務める著者が「共有型経済(シェアリングエコノミー)」という新しい経済社会の到来を予言する論考だ。
『限界費用ゼロ社会――<モノのインターネット>と共有型経済の台頭』(ジェレミー・リフキン 著 柴田裕之 訳 NHK出版)
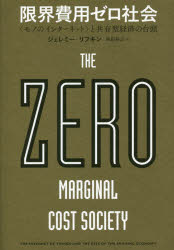 『限界費用ゼロ社会――<モノのインターネット>と共有型経済の台頭』(ジェレミー・リフキン 著 柴田裕之 訳 NHK出版) 定価:本体2400円+税
『限界費用ゼロ社会――<モノのインターネット>と共有型経済の台頭』(ジェレミー・リフキン 著 柴田裕之 訳 NHK出版) 定価:本体2400円+税そんなユートピアが来るとはにわかには信じ難い。
キーとなる概念は書名でもある「限界費用ゼロ社会」だ。
限界費用(マージナルコスト)という経済用語は、ある製品やサービスの1単位を追加で産み出す際のコストを指す。
さらに平たく言うと、例えば紙の本を100冊追加で流通させようとすれば、紙代や印刷代、輸送代などの限界費用がかかる。ところが、パソコンでテキストをコピーすれば限界費用は「ほぼゼロ」になる。
情報のコピーは分かりやすいが、3Dプリンターならば「モノ」までもが限界費用がほぼゼロになっていく。近い将来には建物や人間の臓器までもが3Dプリンターで作れる可能性もあるそうだ。
もちろん財の流通にはコピーだけではなく、電力や輸送も必要だが、エネルギーやロジスティックもテクノロジーの進歩でコストが「ほぼゼロ」になるかもしれないというのだ。
コストがほぼゼロになれば、理屈としてはモノやサービスの価格もゼロになる。
そうなると、モノやサービスをお金で交換するシステムである資本主義はもはや成り立たない。そうした「限界費用ゼロ社会」が近づいていて、既に一部はそうなっているというのが本書の大雑把な要約だ。
著者は資本主義に置き換わる共有型経済は、「協働型コモンズ」という空間で展開されると言う。
「コモンズ」とは封建時代のヨーロッパの農村で、農民たちが共有した牧草地や水車小屋などを語源にしている。領主の容赦ない税の取り立てから生き延びるために、コモンズで共に働き(協働)、生活の糧をシェア(共有)したという。
そうした農村の「囲い込み」をし、行き場を失った農民を安い労働力としてこき使い、資本主義が誕生したというのは教科書で教わった通り。著者は資本主義の誕生、発展をたどりながら、資本主義そのものが持つ矛盾ゆえに、限界費用ゼロ社会が到来し、新しいコモンズが生まれるという経済史を描く。
論理としてはシンプルで、資本主義は技術革新とコスト削減の競争を運命づけられているのだから、コストが究極までゼロに近づけば、価格もゼロに近づくということだ。
インターネット、再生可能エネルギー、モノもインターネットの情報のように行き来する「IoT(internet of things)」という3つのテクノロジーが、資本主義を終わらせようとしているというのが著者の理論の柱となっている。
もちろん資本主義は「独占」によって席に居座ろうとする。
インターネットでも大手通信会社の回線を有料で使わないといけないし、個人や中小業者がそれぞれ自前で太陽光から電力を得るより、電力会社からトップダウンに供給させようとするし、一見フリーに見える検索エンジンやSNSもユーザーから集めたビッグデータを独占してお金にしようとする。
そうした独占に対抗する新しいコモンズが、さまざまな社会的起業という形で生まれていることを著者は紹介する。
インターネットを通じた無料オンライン講座「MOOC」や、空いている部屋と借り手を結び付ける「エアビーアンドビー」、カーシェアリング、さらにそうしたシェア活動を支えるクラウドファンディングの拡大などだ。
もちろん著者も、あっという間に資本主義が共有型経済に取って替わるとは考えてはいない。数十年をかけたプロセスが続き、しばらくはシェア経済を準備するための情報やエネルギー、交通網などのインフラの整備で、資本主義的な投資が行われるだろうとする。
資本主義を「プロテスタンティズムの倫理」が用意したように、新しい経済へ向けた倫理が生まれつつあるという指摘も興味深い。
ジェネレーションX(60~70年代生まれ)やミレニアル世代(80~2000年代初頭生まれ)は、それより上の世代よりも物質主義は薄れ、「所有よりアクセス」、また他者との親交や共感に幸福を求めることが社会調査などから浮かび上がっているという。
愛とシェアが資本主義を終わらせる?とでも言おうか。
一方で、本書は楽観主義的すぎる未来像を描いているととらえる人も多いかもしれない。いま目の前にある格差や暴力は果たして経済パラダイムの転換によって解決するのだろうかという疑問は当然残る。
共有型経済に向けた非営利部門が拡大し、再生可能エネルギーを基盤としたスマートシティというインフラが整備される地域では、もしかしたらその住民は幸福を得られるかもしれない。しかし、そのインフラから除外された人々はどうなるのだろうか。
著者はあまり悲観的な側面には論を進めていない。しかし、本書の最後にある日本版向けの特別章を読んで、日本人としていくらかの危惧を感じた。
その章は、日本とドイツの経済改革への取り組みを比較している。脱原発を遂げ、10年後には太陽光と風力で45%の電力をまかなうというドイツに対し、日本は「原子力と化石燃料のエネルギーに執着」し、「産業は電力業界に手足を縛られ、日本企業は国際舞台での競争力を失う一方だ」と断じている。
ドイツは「スマートでグリーンなインフラへ急速に移行」しているのに対し、日本は「過去との訣別を恐れ、確固たる未来像を抱けない」という。
先進工業国だった日本としては、来るべき未来が明るいのならば、自分たちもその恩恵にあずかれるだろうと思うだろう。しかし、「過去と訣別」できなければ、「除外」された地域になる可能性も十分あり得る。
ユートピアとディストピアという単純な二元論はよろしくないだろうが、日本が後者に進んでいるのではないかという恐怖も、本書の読後感だ。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください