タイラー・コーエン 著 浜野志保 訳 田中秀臣 監訳・解説
2016年01月28日
日本の読者向けの序文で思わず吹き出した。
「日本の読者にお伝えしたいことが一つあります。私の祖国アメリカの食べ物のクオリティが概して低いことについては、私からもお詫びしたいと思います…この国が酷い食事だらけだということはご存知だと思います」
『エコノミストの昼ごはん――コーエン教授のグルメ経済学』(タイラー・コーエン 著 浜野志保 訳 田中秀臣 監訳・解説 作品社)
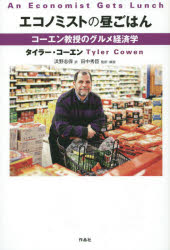 『エコノミストの昼ごはん――コーエン教授のグルメ経済学』(タイラー・コーエン 著 浜野志保 訳 田中秀臣 監訳・解説 作品社) 定価:本体2200円+税
『エコノミストの昼ごはん――コーエン教授のグルメ経済学』(タイラー・コーエン 著 浜野志保 訳 田中秀臣 監訳・解説 作品社) 定価:本体2200円+税本書は、アメリカの売れっ子の経済学者で、食通でもあるという著者が、世界中をフィールドワークし、食を経済学から分析したコラム集だ。
そう書くとしかつめらしく聞こえるが、つまりは食べ歩きをし、いかに安くてうまい食事にありつけるかを、実に執念深く書き連ねている。その食い意地ぶりが愉快だ。
日本版の副題は「グルメ経済学」とあるが、原題は「エブリデイ・フーディー」。直訳すれば「日常グルメ」。
つまり、日々の普段使いの食についての考察だ。
著者自身が認めるように、アメリカでは「底抜けにひどい食べ物がいたるところに溢れている」。
レンジでチンした料理を出すレストラン、家でもやたらとチーズソースを掛けまくり、お菓子も頭痛がするほど甘い。貧困層の最大の健康問題は肥満と糖尿病だ。
考察はアメリカの食べ物はなぜこんなにまずいのかということから始まる。
通説は効率とコストを重視しすぎた食品産業の行き過ぎと言われるが、著者は歴史的観点から異論を提出する。
ひとつには1920年代の禁酒法だという。レストランがアルコールで収益を得られなくなったため、おいしいレストランは潰れるか、料理のコストを下げたため、美食文化が一気に廃れたという。飲食店はお酒を売らないとやっていけないという経営学だ。
そして、20年代から40年間にわたる移民の制限だという。ハンバーグがドイツ、ピザがイタリア、バーベキューが中南米を由来とするようにアメリカの食文化は移民たちが支えていた。移民制限で本国との文化交流が途絶えたために食の進化が停滞したという。
また第2次大戦で、低コストの缶詰スパムソーセージなどのジャンクな食べ物が普及し、アメリカ人の舌を破壊した。
戦争で欧州も窮乏したが、地元の生産物、家庭菜園、伝統的保存食などでしのいだため、アメリカのような大量生産の劣悪食品に毒されなかったという。
この歴史仮説の真偽は検証が必要だと思うが、アメリカの食はエスニック料理だけが頼みの綱という点は、そうなのだろう。移民排斥を叫ぶトランプ氏が大統領になったらアメリカの食べ物はますますまずくなる?というのは余談として。
そこで「行動経済学」を専門とする著者は自らを被験者にしてエスニック食を調べる。
まず取りかかったのは、近所の中華系スーパー「グレート・ウォール(長城)」で1カ月間、買い物を続けるという実験だ。
中国系市民を対象にした店なので、野菜はたくさんあるが何が何だか分からない。いけすのある鮮魚売り場のにおいに耐えられない。これまで買いだめをしていたのに、その日に買ったものをその日に料理する中国的な習慣と合わない。
しかし、だんだん慣れてくると、中華系スーパーの低価格で家計が助かり、「野菜が注目される社会」というインセンティブの経済原理で野菜が好きになり、ダイエットもできた。
ここで著者は食についての「経済原則」を確固たるものにしたそうだ。「食は、経済的な需要供給の産物である。したがって、供給される品が新しく、供給者が創造的で、需要者に知識があるところを見つけるべし」。
さらに平たく言うとこうなるだろうか。
「食は売り手と買い手がともに満足するといい。売る方が新鮮な素材を提供し、さらにおいしくなるような工夫をして、消費者もそれをきちんと理解すれば、(アメリカ人だって)グルメになれる」
その経済原理をもとに、著者は外食の経済学を展開していく。
まずは大都会の高級レストランをこてんぱんに批判する。経済学としては簡単なことだが、不動産の賃料、豪華な内装のコスト、サービスの人件費などを差し引く。
さらに情報の経済学を駆使して、高級店がメディアで評判になってから味が落ちるのは長くて1年、速ければ6カ月と断言する。飲食店にとっては本当にイヤな奴だ。
結論は「安いものがうまい」。もちろんファストフードは除く。私ごとながら東京・下町の大衆食堂と赤ちょうちんをこよなく愛する人間としては海を越えて同志を見つけたような気分になる。
著名なエコノミストとして外国もたびたび訪れる著者は各国でも、独自の経済原則を物差しに安くてうまいものを評価する。
中華料理がうまいのは「タンザニア、インド、カナダ、マレーシア」で、まずいのは「イタリア、ドイツ、コスタリカ、アルゼンチン、チリ」だそうだ。分析内容は本書に譲る。
B級(本当はA級)グルメの同志感が得られつつも、日米の埋めがたい溝もある。
消費者が経済や社会の知識を踏まえて食に向き合うことや、エネルギーコストがかかるファストフードを避けることが地球環境にいいことなどは同意するとして、世界の飢餓の問題解決で著者は全面的に遺伝子組み換え食品を支持している。
確かに遺伝子組み換え食品が健康や環境に害を与えるという実証データはこれまで見つかっていないことも科学的な事実だ。
アメリカの大豆やトウモロコシは既に9割前後が遺伝子組み換え作物だ。テクノロジーやイノベーションに対する倫理感の違いは私たちがこれから考えていかなければならないテーマだろう。
TPPの行方を考えると、著者が否定するようなアメリカの酷い食事情、あるいは著者が肯定する遺伝子組み換えの問題もともに含めて、日本の食にどのような影響があるのかを考えさせられた。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください