森達也 著
2016年02月11日
作家の森達也が、第一線の先端科学者10人と自分自身とに訊いた、全11章からなるインタビュー集。PR誌の月刊『ちくま』に、2014年11月まで連載した原稿に加筆訂正したもの。
最先端の科学的知見を媒介として、「既知」の向こう側にある「不可知」の世界への憧憬と不安とに、さまざまな角度から繰り返しアプローチしている。
『私たちはどこから来て、どこへ行くのか――科学に「いのち」の根源を問う』(森達也 著 筑摩書房)
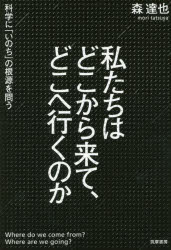 『私たちはどこから来て、どこへ行くのか――科学に「いのち」の根源を問う』(森達也 著 筑摩書房) 定価:本体1500円+税
『私たちはどこから来て、どこへ行くのか――科学に「いのち」の根源を問う』(森達也 著 筑摩書房) 定価:本体1500円+税その意味で「圧倒的に文系だ」(「はじめに」)と自己言及する森が、科学者という理系の他者たちを前にして描いた、哲学的なエッセイという趣がある。
また、彼が反逆のドキュメンタリストとして、敢えて現代社会の異物になることも厭わずに扱ってきた題材(たとえば「宗教」とか「オカルト」とか「ホロコーストの構造」など)を、科学と哲学との狭間に屹立する「解きがたい謎」や「腑に落ちない」ものごとの表象として、あらためて洗い直そうとした印象もある。
扱われる問題は、「生命」「死」「進化」「宇宙」「量子力学」そして「脳科学」「自意識」「私(自己)」など。
登場する人物は生物学の福岡伸一ほか3名、人類学の諏訪元、進化生態学の長谷川寿一、物理学の村山斉、脳科学の藤井直敬と池谷裕二ら。
対話の主題は、本のタイトルにある通り、いずれも画家・ゴーギャンの代表作に冠せられた「私たちはどこから来たのか。私たちは何ものか。私たちはどこへ行くのか」というもの。
高度に専門化され、STAP細胞問題などに見るようにジャンル相互の交通がないと批判される近代科学の俊英たちが、森自身の言葉を使えばこの「青臭い」主題に向かって、それぞれの専門知と関心を真剣に収斂させていく様子は、なかなかにスリリングで、本書の一番の読みどころと言えるだろう。
たとえば、第10章に登場するサイエンス作家の竹内薫はこう言う。
「(科学や科学者が――筆者注)何もわかっていないということに気づいている人は、その時点でけっこう哲学的な問いを発しているわけですよね。そういう人は、『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』ということを考えて、常に全体像を見ている。その一方で、今光が当たっているところしか見ていない人たちもある。彼らにはこの世界にはわからないことがあるという認識が欠如しているから、流れ作業的な研究にならざるを得ない。自分は何のためにその実験をやっているのかを考えない」
――それに対し、森は当然のようにこう反応する。「ならば、考えよう。……もちろん簡単にこの解答が手に入るとは思っていないけれど、せめてその手掛かりが欲しい。それは研究者も同じはずだ。分子生物学者も宇宙物理学者も宗教学者も文化人類学者も、少なくとも第一線で格闘しているならば、この命題を回避することはできないはずだ」と。
この森的な命題を回避しようとした対話者は、結果的にいなかったようである。
いなかったことが本書の希望だし、10人の対話者をそこに至るまで追い込んだ「圧倒的な文系」である森の、おそらく周到な準備に裏打ちされた、非専門家としての該博な知識も驚嘆ものだ――森は年季の入ったSFファンでもあり、読者はそのあたりの仔細も楽しめる。
しかし、それにも増して、周到に準備していてもなお、相撲のように手を広げ、素手で現場に臨むとでも言いたくなる、いささか乱暴で、執拗で、柔軟なコミュニケーション能力は、感動的ですらあると言えるだろう。
「数学」の「集合」の単元で学ぶベン図というものがある。大抵は、違う大きさの大小二つの円が重なってできているあの図である。
森と同じく「文科系」であった私は、同じ要素をもったものが集まってできた円の内部にある「既知」の中身やその重なりよりも、円周の外にある「未知」の部分と、その「未知」の部分が多くの場合、矩形の囲いで切り取られている不思議さのほうに注意が向いたことを覚えている。
さらに、円周が表すのは「既知」と「未知」との境界、すなわち「何もわかっていないということに気づ」く可能性がある場所であり、その場所が長いほど「未知」の部分も大きくなる、つまり、「既知」の部分が増えるに従って(その集合をあらわす円が大きくなるほど)、円周が表す「未知」の部分も増えるのだと知ったときの驚きを忘れない。
そして、未知の部分を矩形の枠で区切って問題にしない(森的な言葉で言えば「思考停止」を迫る)教科書的な傲慢に、ひっそりと苛立っていたものだ。
第11章「森達也に訊く」の中で、森は第1章で書いた次の述懐を繰り返す。
「おそらくは小学校に入るか入らないかの時期、死という概念を初めて知って、自分でも制御できないほどの恐怖に襲われたことがある。
知ったその瞬間ではなくて夜に眠るために蒲団に入ってから、自分はいつか死んで消えるのだとあらためて考えて、あまりの恐怖に眠れなくなったのだ」
「未知」にまつわるこの手のなぜか懐かしい述懐は、昔は寺田寅彦や島崎敏樹、あるいは日高敏隆やなだいなだといった科学者や医者の文章などで目にすることが多かったように思う。
大人になって思い出される幼い日々の恐怖や種々の想像といった記憶、それが何らかの発見や着想につながるという懐かしくも本質的なサイクルを、量子力学や分子生物学や脳科学が隆盛で、情報ばかりが跋扈すると見える今でも見つけることができる。
この確信犯的な直観の力と、それを一冊にまとめあげた行動力こそが、本書の一番の光栄だと言えると思う。
なお、本書で最も論争的なのは、第8章で藤井直敬を、第9章で池谷裕二を相手取って展開される、脳科学者二人との対話だ。
前者では「代替現実システム」の実体験を起点に「メディア・リテラシー」に至る論議が交わされ、後者では「自己を語る」という言語のトラップを巡って興味深い問題を俎上にのせている。
ともに、年来こだわってきた森的な題材であり、この二つの対話を終わり近くに持ってきたと思しい抜け目のない構想力にも感嘆してしまった。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください