川北稔 著
2016年02月26日
グローバル化、グローバリズムという言葉が世を席巻するようになって、いったいどのくらいの年月が経過したのだろうか。
こうした言葉に追いまくられて、大学もグローバルの波に乗り遅れてはならないとばかりに、わけのわからぬ名前の学部、学科が乱立する昨今である。挙げ句の果てに、「総合グローバル学部」なるものまで登場したのだから、何をかいわんやである。
文学、歴史などは時代遅れの学問、いや、暇人の関わるものとして、国立大学から排除する動きまであるという。
こうした潮流に負けてはならじと、「グローバル英文学」、「グローバル・ヒストリー」を看板にする御仁もいる昨今。いやいや、生きにくい世の中になったものだ。
そこで読んだのが本書。
『世界システム論講義――ヨーロッパと近代世界』(川北稔 著 ちくま学芸文庫)
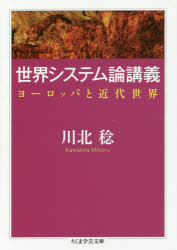 『世界システム論講義――ヨーロッパと近代世界』(川北稔 著 ちくま学芸文庫) 定価:本体1100円+税
『世界システム論講義――ヨーロッパと近代世界』(川北稔 著 ちくま学芸文庫) 定価:本体1100円+税近代の世界史とは「一つの巨大な生き物」が動き回って展開していく過程であって、そこからヨーロッパを中核とするシステムが生まれ、世界にそのシステムが波及するとともに、さまざまな地域が相互に影響しあう姿が解き明かされていく。
つまり、グローバル世界は実は今を去ること500年前から現出していたのだから、国単位の歴史叙述に留まっていては、世界の実相を見誤るというのだ。
確かに「イギリス風ライフスタイル」が生まれるには、西インドの砂糖生産、その輸入が不可欠であったはずで、そうした視点の拡がり抜きでは、近代イギリスの実相は捉えられないはずである。
本書は放送大学の講義をもととしたもので、具体的な史実への言及は極力抑えられているが、それでも歴史の見方、とらえどころが明晰に示されていて、近代世界の成立から現代に至る過程、さらには未来への見通しが腑に落ちる。
しかし、こうした視点をきちんと保ちつつ、各国の歴史、人々の生き方、過去における人間の営為の積み重ねを豊かに、そして興味深く描き出すのは大変なことになるだろう。
事実、史実を広く深く掘り起こしたとして、その解釈には歴史家の恣意が入るのは避けられないだろうし、それ以前にまず、歴史家の解釈が説得力のある明晰な文章で示されることが不可欠なはずである。
その意味で、人文系学問不要論を唱える輩の浅慮は、罪、万死に値するのではないか。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください