藤木TDC 著
2016年08月18日
たとえば新宿の「新宿ゴールデン街」や「思い出横丁」、池袋の「栄町通り」や「美久仁小路」。高層ビルを中心とした現代風の景観が周りを取り囲むなかにあって、明らかに異質な空気をまとうこれらの建物群、飲み屋街は、独特としか言いようのない存在感を放っている。行ったことがない人にとってはピンとこないかもしれない「存在感」の意味も、一度でも足を運んだ人には理解してもらえる気がする。
この「存在感」のルーツを探っていくと、突き当たるのが敗戦直後の「ヤミ市」である。高層ビル化が進む前の都市ターミナル駅周辺の佇まい、高度成長期に入る前の東京(近郊)の繁華街のすがたが敗戦直後の「ヤミ市」に由来する事実に着眼し、「ヤミ市由来の歴史的経緯」を街ごとに追いかけ、ガイドブックとしてまとめ上げたのが本書である。
『東京戦後地図——ヤミ市跡を歩く』(藤木TDC 著 実業之日本社)
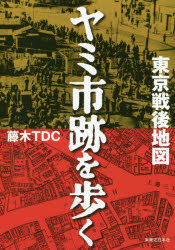 『東京戦後地図——ヤミ市跡を歩く』(藤木TDC 著 実業之日本社) 定価:本体2400円+税
『東京戦後地図——ヤミ市跡を歩く』(藤木TDC 著 実業之日本社) 定価:本体2400円+税一つは、戦前の主要な駅や軍事施設周辺には建物疎開(空襲や火災による延焼を防ぐため建物を取り壊す作業)によりできた広大な空き地があったため、焼け野原となった戦後、即座に「自由マーケット、青空市場」すなわち「ヤミ市」をオープンできたということ。
そしてそれらのマーケットが、1949(昭和24)年9月に出た東京都の露店撤去令により、都が決めた斡旋換地【かんち】(区画整理のため都が換わりに用意した土地)への移転を余儀なくされたというのが二つ目である。
戦後最も早くヤミ市が開かれた新宿を例にとれば、駅東口、現在のルミネエストの敷地にあたる場所にできた和田組マーケット(和田薫親分)の場合、露店撤去令以降の50年代に、半数の店舗が現在の「新宿ゴールデン街」へ移転。他のいくつかのグループは、いったん甲州街道沿いに移転後、現在の歌舞伎町へ、いちばん遠くは総武線・錦糸町駅近くの「花壇街」へ、それぞれ移転していった。
移転をめぐるエピソードとしては、行政が処理に困った焼け跡の瓦礫で埋め立てた用水や河川が換地に充てられた銀座、神田、深川などの例も興味深い(三十間堀川、新川、龍閑川、浜町川などが埋め立てられた)。
と言ってもすべてのヤミ市が換地に移転したわけではなく、ヤミ市に建った露店や店舗が、同じ場所で現在まで営業する新宿駅西口の「思い出横丁」、吉祥寺の「ハモニカ横丁」、三軒茶屋の「三角地帯」のようなケースもある。また、活気ある駅前商店街で知られる大山、十条、立石の場合は、斡旋換地ではなく、撤去令後に自己資金と公的融資によりみずから探した土地でオープンした新店舗が元になっている。
建築史的価値に注目すれば、自由マーケットに由来する「連鎖式店舗」(飯田橋駅や高田馬場駅近辺ほかに今も残る)や、有楽町や神田の駅ガード下でおしゃれに様変わりした煉瓦アーチ式店舗構造なども俄然、目を引く。
こうした地図好き、散歩好きの人を満足させる都市形成史上の重要アイテムは言うまでもなく魅力的だが、ヤミ市に由来する駅前空間やあの一角、この建物がどういう変遷を経て今に至るのかを探る過程では、そうした要素に留まらないものが見えてくる。
隠された人間ドラマ――テキヤ主導で作られたマーケットの権利をめぐり在日外国人と日本人やくざとの間で繰り広げられた血なまぐさい抗争(新橋)――や、戦前の花街から戦後の性風俗産業への移り変わりを生き抜く人々のすがた(新宿歌舞伎町、池袋西口、池袋人世横丁、渋谷道玄坂、立石、……)等々、多種多様に盛り込まれた風俗史・社会史・文化史的テーマが浮上することで、地図好きでなくとも、本書を片手に持ち街へ歩き出したくなるのだ。
もちろん、本書で紹介される事実は、ある世代以上の人たちや専門家にとっては自明の事柄に属すかもしれない。が、それこそ闇の世界との関わりが多くなるためか、「ヤミ市や換地の歴史は地誌資料の極端に少ない分野」(あとがき)だと言う。
著者が「ヤミ市の記憶に触れることに対するアレルギーが薄れ」(同)てきたと述べるリーマン・ショック以降の現在、「火災保険特殊地図」(50年代の町並みを知る上で貴重な資料)を使って、みずからが依って立つ土地の記憶に耳を傾ける作業の意義は決して小さくないはずだ――東京近郊以外の土地で暮らす人にとっても、著者と同様の着想で町を再発見することは可能だろう。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください