加藤陽子 著
2016年10月03日
本書を読みながら、内容とは直接関係のないさまざまな感想・感慨が頭に去来したのだが、その由って来たるところは主に三つある。
『戦争まで――歴史を決めた交渉と日本の失敗』(加藤陽子 著 朝日出版社)
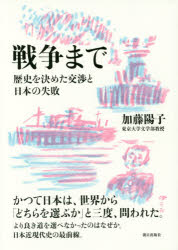 『戦争まで——歴史を決めた交渉と日本の失敗』(加藤陽子 著 朝日出版社) 定価:本体1700円+税
『戦争まで——歴史を決めた交渉と日本の失敗』(加藤陽子 著 朝日出版社) 定価:本体1700円+税「こんにちは。人間のからだの細胞は三カ月で入れ替わるというので、みなさん、最初に会ったときとは違う人になっているということですね。だんだん大人になっているなと、みなさんの顔を眺めていて思います」
著者がこう語りかける聴き手、というより本書の「共著者」でもある中高生たちは、柔軟な脳と瑞々しい感性をもつ。そのことは本書の随所に散りばめられた質問や著者から発せられる問いへの回答からわかる。
読者はその中高生とともに、いまと地続きにある日本の近現代史の現場へと誘われるのだが、あるときはこれまで信じて疑わなかった歴史上の「神話」がみごとに打ち砕かれ、またあるときは数多の史料から結論づけられる意外な真相に目を見開かされて、中高生とまったく同じ視線で胸を踊らせている自分に気づく。
そしてつくづく、このような講義を受けつつ、自分の目でしっかりと世の中を見極め、自らの頭で判断し、そして実際の交渉事に生かす術を身に付ける道が拓けている若い知性を羨ましいと思う。
もちろん、われわれ大人が経てきた戦後の安定した時代とは比べものにならないくらいの困難が彼らの前途に横たわっていることは明白だし、結果として彼らにこんな社会を用意してしまった責任も感じる。残された時間を極力その挽回のために使おうと思っていることも確かだ。
しかしなおかつ、このような困難な時代だからこそ、輝かせることのできる知性と言葉の力があるように思う。
それはちょうど著者が、次のような言葉に託す思いに重なる。
「(昨今の世界の動きの中で)、なにか人間が苦しみの中で考え抜き、ようやく発見した真理、それらを自国民に広めるだけでなく、他国民も共感を持って受容できるよう、言葉にして訴えかけ、形にして提示しうる知の力を持つ国や人々が、世界をリードしていくと思います。産業革命を契機に国民の経済学がイギリスで生まれ、明治維新を契機に国民の歴史学が日本で生まれたように(同時にまた著者は、戦前の日本の学問、たとえば吉野作造の政治学や美濃部達吉の憲法学が東アジアに与えた影響を多大なものと見る)、また何かの学問がどこかで生まれてくるのではないでしょうか」
と、ここまで周辺事項のみ取り上げてきたが、では肝心な本書の内容はといえば、それはカバーに添えられた文言が見事にまとめてくれている。
まず『戦争まで――歴史を決めた交渉と日本の失敗』というタイトルとサブタイトル。そして普通なら帯として巻かれる(本書は帯なしでカバーにそのまま刷り込まれている)惹句。
「かつて日本は、世界から『どちらを選ぶか』と三度、問われた。より良き道を選べなかったのはなぜか。日本近現代史の最前線。」
これほどまで完璧なタイトルとコピーとの連動を具えた本に、久しぶりに出会った。帯がない書容設計も気が利いている。続けて四つ目の感想・感慨を上げるとすれば、装丁や本文レイアウトも含めての、本作りの巧みさについてだ。
日本が世界から三度問われた交渉事とは、ひとつは満州事変について提出されたリットン報告書をめぐって。二つには日独伊三国軍事同盟条約締結において。そして三つ目は最終的に開戦をもたらしてしまった、1941年4月から11月までの日米交渉のことである。
先ほど中高生と同じ視線で、などと言ったが、なかなかどうして、読み進めていくに従って、自分のような浅学の徒にとっては目が覚めることばかりで、なになに、と年甲斐もなく子どもたちを掻き分けて著者の目の前に座りたくなる。
リットン報告書がここまで日本に配慮した内容だったとはつゆも知らなかったし、著者の言うように、集団的自衛権の行使が許され、軍事同盟が目前にあるいま、日独伊三国同盟がいかにして締結されたかは未だかつてなくリアルに映る。
そして例の真珠湾攻撃をめぐる「神話」だが、あれは別に日本大使館が怠慢だったせいでも、アメリカがわざと日本に先制攻撃をさせて開戦に誘おうとしたわけでもない。真実はまだ闇の中だが、ハル国務長官と丁々発止の交渉を続けていた民間きってのアメリカ通である野村吉三郎大使が、緊張が解けた瞬間、ふと新聞記者に漏らしたことで、ローズベルトと近衛の日米首脳会談が幻と化したとは知らなかった。それが実現していたら、確実に太平洋戦争は避けられたはずだ。まさに「歴史の魔」である。
さて、冒頭二つ目にあげた、感慨の由って来たるところについて述べるのを忘れていた。著者は7年前、『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(現在、新潮文庫)という本を上梓して洛陽の紙価を高めた。それも同じく中高生を相手に行った講義をまとめたものだが、今回はその講義をもった場所が異なる。ジュンク堂池袋本店のイベントは都内に住む本好きならば、一度は参加したこともあるかもしれない。せいぜいが30人ほどの席に囲まれて、作家たちは実にリラックスして自らを語る。本書のほとんどはそういう環境から生まれた言葉で出来ている。つまり、「市井の」学問である。
これからほんとうの知性というのは、大学を出て市井に生きるのではないか。そしてその学問は市民運動へと連なっていくのではないか……そんなことを夢想した。
それにしても……とページから目をあげてふと思う。これらもみな、関係諸国の当時の詳細な資料が残っていたからこそもたらされるものだ。ところがわが国においては、特定秘密保護法が国会を通過したいま、為政者の思うがまま事実に蓋ができるようになってしまった。しかも何に蓋をしたかは国民にはわからず、その蓋をいつ開けるか、あるいは永遠に開けないという選択肢もあり、それらはまったく為政者の胸先三寸にかかっている。
いまここにいる中高生が親になったとき、あるいはその子らのまた次の世代には、こうして資料を繙(ひもと)き、つぶさに歴史を学ぶ自由さえ残されていないのだ。あらためて思う。われわれはいま、なんという罪深い政府をもってしまったのだろう、と。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください