若松英輔 著
2016年10月14日
何にせき立てられているのか。その「何」がはっきりしないまま、ただただせき立てられ、前のめりに足を踏み出してしまう日々のなかにあって、足を踏み出す前方ではなく、足下への、垂直方向のまなざしを持つことでこそ自身が刷新される、と気づかせてくれる一冊だ。「ふれる」「悲しむ」「喜ぶ」「嘆く」「老いる」など、全部で25の動詞をめぐるエッセイ集である。
『生きていくうえで、かけがえのないこと』(若松英輔 著 亜紀書房)
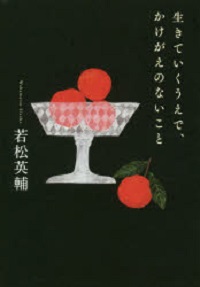 『生きていくうえで、かけがえのないこと』(若松英輔 著 亜紀書房) 定価:本体1300円+税
『生きていくうえで、かけがえのないこと』(若松英輔 著 亜紀書房) 定価:本体1300円+税「どう書くかよりも、書くとは何かを、書きながら考えなくてはならない。書くとは、生きることにおける不可欠な営為の呼び名である」(「書く」より)
この文は、「生きる」とはどういうことかを知らずに、「何のために生きるのか」を問うのは順序が逆である、と書き続けた哲学者・池田晶子の態度を紹介した文章の直後に置かれている。
「何のために生きるのか」という問いは、生きる目的にはあたかも解答があることが前提とされたような物言いだ。ところが「答えがないところを生きるのが人間の宿命であると見定めたところから」、「思索者としての人生」を始めたのが池田晶子だった。
寄り添いつつ彼女の言葉を引く著者にとって、「どう書くかよりも、書くとは何か」が問題となるのは、当然でもある。著者が足下へのまなざしを喚起するというのは、たとえばこうした身振りのことだ。
だから著者にとって、「書く」行為はけっして自明ではない。「書くとは、単にすでにある想いを文字にする営みではない。それはメモで、ここでいう『書く』という営為ではない。(中略)それは自己とは何かを知る営みでもある」(あとがき)。
そうして、「むしろ人は、書くことによってはじめて、自分が何を考えているのかを知る」とまで述べる。「書く」行為が、他者としての自己、自分のなかにある未知の自己を呼び寄せる。「書く」行為のみならず、自明と思い込んでいる「自己」さえ自明ではない、と気づかされる。
本書の「まえがき」を書く吉村氏は次のように述べる。
「どのエッセイにおいても共通して志向されているのは、『不可視なもの』、『何ものかの声』、『音にならない何か』、『彼方の世界』、『不死なる実在』、『万物を包みこむ何か』、『自らを超えた者』といった向こう側の世界である」
そして付け加える。これら「向こう側の世界」は、「オカルトや神秘主義などが扱う何か特別な領域」ではなく、「我々にもっとも身近な世界」にあるのだ、と。著者は、『魂にふれる――大震災と、生きている死者』(トランスビュー)や『悲しみの秘義』(ナナロク社)など過去の一連の散文集においても、つねに、意識の向こう側から姿を定めずやって来るもの(コトバ)へと、読者の注意を向けさせてきた。
本書は、そうした「コトバ」は確かに存在し、足下に眠っていて、誰かにふれられるのを静かに待っているのだという感触を、25の動詞が喚起する歴史・書物・風景・心情を通して読者に実感させようとしている、とも言えるように思う。つまり、本書を通して得られるのは、情報ではなく体験だ、ということだ。
解釈したり辞書を引いたり著者の経歴を調べるのでなく、ただ本書の言葉の前に佇むこと。そうすることで、読む者自身の足下が掘り返され、忘れていた自己、知らなかった自己がすがたを顕わす。さらに、読者がそうやって佇むための時間を、本書の装丁、文字組、手触りは与えてくれている。
対になる吉村氏の同タイトルのエッセイ集を読めば、どこかで重なりながら限りなく遠く、隔てられた世界のようでありながらどこか似ている互いの書き手の世界が味わえ、書く自由、読む自由、考える自由がいっそう堪能できる。
そういう趣向を凝らした本書の企画者が著者・若松英輔である事実を思い合わせると、いま、私を含め多くの人が知らぬ間に前提としてしまっている「書く」こと「読む」ことの枠組みが壊され、そのことでかえって言葉の裾野が拡がっていくようで、気持ちがいい。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください