ジェイムズ・ジョイス 著 柳瀬尚紀 訳
2017年02月16日
担当した編集者としての思い出から書かせて頂く。本書の訳者である柳瀬尚紀さんにはモーツァルトに関するエッセイを数多くご執筆頂いた(石井宏編『モーツァルト・ベスト101』所収、新書館、2004)。校正ゲラ送付のご連絡をするたびに長電話になった。柳瀬さんは話術の天才。架電したらもう二度と受話器を置けない覚悟が必要なほど。電話するたびに通話料金を気にしてくださった。きめ細かな心遣いに感激しつつ、モーツァルトについては無論のこと、飼われている猫についてもたっぷりとお話を伺った。
『ユリシーズ 1-12』(ジェイムズ・ジョイス 著 柳瀬尚紀 訳 河出書房新社)
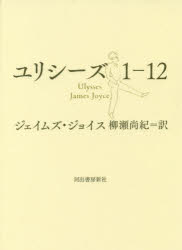 『ユリシーズ 1-12』(ジェイムズ・ジョイス 著 柳瀬尚紀 訳 河出書房新社) 定価:本体4500円+税
『ユリシーズ 1-12』(ジェイムズ・ジョイス 著 柳瀬尚紀 訳 河出書房新社) 定価:本体4500円+税柳瀬さんが笑いながら「ごめんなさいね、ぼくの翻訳のせいで苦労かけちゃって」と話されたあとで、突然口調が変わった。「御社は丸谷才一さんとおつきあいがあるんでしょ、ぼくに依頼してもよかったの?」。丸谷さんや高松雄一さん、永川玲二さんが訳された『ユリシーズ』(集英社)は常々批判しているという。
以後は電話のたびに『ユリシーズ』の話題がどーっと続いて行くようになる。「訳注を読む時間のほうが長いんだよ、それで文学と向き合ったと言えるのか?」。
たしかに、当時刊行されていた柳瀬さんの『ユリシーズ1-3』(河出書房新社)に訳注は存在しなかった(今回ご紹介する本にも訳注はない)。しかし、いつも最後は「全訳してないものが何を言ってもしようがないよね……」という自嘲で終わるのであった。
そしてとうとう、全訳しないまま(『ユリシーズ』は全18章、本書は12章まで)、昨(2016)夏、柳瀬さんは逝ってしまった。
正直な話をすると、わたしは丸谷グループによる『ユリシーズ』は、日本語として読める限度ぎりぎりまで、ジョイスの文学への挑戦に向き合った、すぐれた翻訳であると思っている。
もちろん『ユリシーズ』の翻訳をはじめて読了したのが集英社版ということもあるが(文庫版になってもあいかわらず誤植があり、ジョイスの言葉遊びと区別がつかなくて困るという欠点もあるが)、柳瀬さんが批判されている当の訳注は読むのが楽しくてまったく苦痛ではなかった。柳瀬さんの糺弾に反発するようでおそれおおいのだが、私見では集英社版の訳注は、注という名の文学研究であり、文芸評論と言ってもよいものである。
丸谷グループの中枢である高松雄一さんからは、「『ユリシーズ』では翻訳の限界をつくづく感じた、もう翻訳なんて二度とやるまいとまで思った」という正直な悔悟の言葉を、やはり電話口でお伺いしたこともあった。しみじみとした口調には翻訳と向き合ってきた高松さんの人生の息吹まで感じ取れ、感銘を受けざるをえなかった。
それでもなお、この全訳ではない柳瀬訳『ユリシーズ』最新刊を、畢生の名訳としてまず推したいと思う。理由は、柳瀬さんの独特の文体にある。まともに読もうとするならつまずくしかない難解な実験小説において、柳瀬さんの個性に由来する、まるで落語を聴いているかのように弾むリズム感は、訳注で途絶しないことも相俟って、おそるべきスピード感を生み出すのである。そこにはおそらく、『ユリシーズ』は本来、歴史に残る晦渋な大著などではなく、むしろギャグにあふれたコメディ小説であるという基本認識がある。
最初の「1 テレマコス」の比較で言うなら、集英社版は休日に午後いっぱいまでかかってじっくり読まないと頭に入ってこない。それが柳瀬訳の河出版は、行き帰りの電車内で読了可能であった。
実例にふれていただくに如くはない。バック・マリガンのおどけた口調の訳し方に、その秘密の一端があると思う。以下、巻頭「テレマコス」にあるマリガンの口調を比較してみよう。
原文:Buck Mulligan showed a shaven cheek over his right shoulder.
―God, isn't he dreadful? he said frankly. A ponderous Saxon. He thinks you're not a gentleman. God, these bloody English! Bursting with money and indigestion. Because he comes from Oxford. You know, Dedalus, you have the real Oxford manner. He can't make you out. O, my name for you is the best: Kinch, the knife-blade.
丸谷グループ訳:バック・マリガンは右の肩越しに、剃りあげた頬を向けた。
――まったく、いやなやつだよな? と彼はあけすけに言った。勿体らしいサクソン人め。おまえなんて紳士じゃないと思っているんだ。まったく、イギリスの野郎どもったら! 札束と消化不良ではちきれやがってさ。それもやつがオクスフォードを出たおかげだよ。ところが、ディーダラス、おまえは本物のオクスフォード流儀(*訳注)を身につけている。やつはおまえをどう考えたらいいかわからない。ほんと、おれにつけた名前がぴったりだよ、匕首のキンチってのがな。
(*訳注……〔前略〕……スティーヴンがいわゆるオクスフォード英語を話したとは思えない。あの独特の気取りを真似てもぼろを出して軽蔑されるだけである。「本物の紳士の心得を身につけている」ぐらいの意味か)
柳瀬尚紀訳:バック・マリガンは片方のさっぱりした頬を右肩ごしに見せた。
――どへッ、いけ好かないやつだろ? と、あけすけに言う。幅ったいサクソン野郎め。きみのことを紳士じゃないと思ってる。ちょッ、気にくわねえのばっかしよ、イギリス野郎てのは! しこたま金を肥して、いまにも腹下しの態だ。なんせオクスフォードの出だとよ。だけど、デッダラス、きみこそ本物のオクスフォード出って雰囲気があるぜ。あいつはわかっちゃいない。そうそう、おれがつけた渾名が最高だっての。切っ刃のキンチさ。
丸谷グループ訳と柳瀬訳の違いがあきらかなところは、以下の3点だと思う。マリガンの最初の言葉「まったく」と「どへッ」。丸谷グループで訳注をつけている「オクスフォード流儀」と「オクスフォード出って雰囲気」。ラストにあるスティーヴンのあだ名「匕首のキンチ」と「切っ刃のキンチ」である。
1. 「まったく」と「どへッ」――丸谷グループはただの間の手であるとはいえ、「God」を「どへッ」と訳すことは避けたほうがよいと判断したのであろう。しかしこの場面でマリガンは徹底的にキリスト教を皮肉っている。というかバカにしている。出だしからミサのパロディを自ら演じているくらいで、むしろ「どへッ」くらいの訳文がよいのかもしれない。
2. 「オクスフォード流儀」と「オクスフォード出って雰囲気」――マリガンは本気で、アイリッシュのスティーヴンがイギリスのエスタブリッシュメントと同等の「Oxford manner」を身につけている、と考えているわけではない。比較すれば相対的に上品である、という程度のことである。わざわざ訳注で断るくらいなら、訳文で意訳して「雰囲気」をつけくわえる柳瀬さんの判断に軍配を上げたい。
3. 「匕首のキンチ」と「切っ刃のキンチ」――「Kinch」は基本的には呼び名である(kid「子ども」のニュアンスも含ませているのかもしれない)。ただ「knife」の「k」と対になると考えた柳瀬さんは、「切」と「キ」で音をそろえて訳している。原文のbladeの意味である「刃」を明確にしたかったということもあろう。それを丸谷グループは「切っ刃」では意味がわからないと考え、穏当な「匕首」と、いわば普通に訳した。ここには翻訳の限界がある。読者の便に供するためには「断念」も時には必要だとする判断であり、高松さんが後悔するのはこういった部分であろう。
しかし柳瀬さんは翻訳に断念を認めない。作者の意図を、強引とも思える訳語で対応させようとする。おいてきぼりにされる読者はもちろん存在するだろうが、そういった人にも原書のノリを伝えたい、という猛烈な翻訳の欲望がここにはある。
いきなり細部の説明をしてしまったが、そもそも『ユリシーズ』とはギリシア神話の英雄オデュッセウスの英語読みである。文体の冒険を縦横に盛り込みつつ、1922年に書かれた。トロイ攻略戦後の放浪の果てに故郷に帰り着くオデュッセウスに対応するのが、本書の主人公である38歳、身長174センチのユダヤ人の広告取り、リアポウルド・ブルームである。貞淑なオデュッセウスの妻ペネロペに対応するのが、不倫中の34歳のブルームの妻モリーであり、オデュッセウスの息子テレマコスに対応するのが11年前に死んだ長男ルーディであり、その身代わりとしての小学校教師スティーヴン・デッダラス(『若き芸術家の肖像』1916年の主役、ジョイスの分身、身長180センチ)となる。彼らのダブリンのある一日(1904年6月16日)の記録が本書なのであった。
せめてあともう1章、「13 ナウシカ」だけは訳していただきたかった。処女のセクシーポーズに自瀆するブルーム、という場面はジョセフ・ストリックの映画版(1967年)でも話題になった箇所であり、まるごと婦人雑誌の文体模写で染められた、『ユリシーズ』の中では比較的「わかりやすい」章である。話者がよくわからない、なぞめいた「12 キュクロプス」を最後に終わってしまったことは、本当にせつない。
ラストにあるモリーの想念の流れ、「he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes.」(丸谷グループ訳: わたしの乳ぶさにすっかりふれることができるように匂やかにyesそして彼の心ぞうはたか鳴っていてそしてyesとあたしは言ったyesいいことよYes)という文章のラストの大文字のYesを、柳瀬さんならどう訳しただろうか? 日本の翻訳の歴史を変えるような訳文が生まれていたかもしれない。
われわれは決定的瞬間こそ見逃してしまったかもしれないが、本書を読めばその匂いはかぐことができ、心臓も高鳴るであろう。あらゆる読者が読了後にyesと言えるかどうかは保証できかねるが、すくなくともいま日本で読める『ユリシーズ』では、最高峰の1冊であることは間違いない。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください