ゲイ・タリーズ 著 白石朗 訳
2017年03月06日
中学生の時分、そんな気などまったくないのに、ある夜、隣家の若い女性の、見てはいけない姿が目に入ってしまったことがあった。あのときの気まずさ、うしろめたさと好奇心の刺激がないまぜになった感情は今でも鮮明に覚えている。映画では、ヒッチコックの『裏窓』をはじめ、「覗く」というモチーフが、様々に変奏されて描かれてきたことでもわかるとおり、この行為は危うさと、それゆえの磁力に満ちている。この快楽への依存症が昂じると「覗き魔」になるということだろうか。
『覗くモーテル 観察日誌』(ゲイ・タリーズ 著 白石朗 訳 文藝春秋)
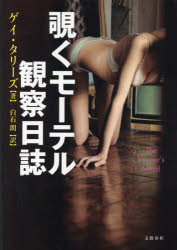 『覗くモーテル 観察日誌』(ゲイ・タリーズ 著 白石朗 訳 文藝春秋) 定価:本体1770円+税
『覗くモーテル 観察日誌』(ゲイ・タリーズ 著 白石朗 訳 文藝春秋) 定価:本体1770円+税さて、1980年、筆者のもとに40代の男から手紙が届く。アメリカのコロラド州で60年代からモーテルを経営し、客の寝室を覗いてきたとの告白だ。
モーテルの部屋21室のうち12室の天井に、通風孔に見せかけた覗き穴を開け(この時の悪戦苦闘ぶりが滑稽!)、これといった客がチェックインすると、天井裏に上がり、ひたすら観察して詳細な記録をつけたという。
その理由は「人間への飽くことなきわが好奇心ゆえであり、決して変態の覗き魔としてやったことではありません」(このくだりを読んで、ものは言いようだと笑ったが、読み進むにつれ、かなり的確な自己分析だとわかってくる)。
筆者のゲイ・タリーズは彼に直接会い、実際に天井裏から客室を覗いてカップルの性行為を目撃する。この覗き魔に関わることは「共犯」になってしまうと悩むのだが、結局、彼から膨大な記録を提供してもらうことになる。
本書はこの「観察記録」と、覗き魔との交流を軸に進む。誰にも見られていないと思い込んでいる(当たり前だ)宿泊客の姿は、あまりにリアルだ。なにせ、ベッドの足側の真上、1.8~2.4メートルの高さから丸見えなのだから。
男女のフツーの性行為はもちろん、同性愛、グループ行為、夫婦交換、コスプレ、性倒錯、近親相姦、一人客の自慰、はたまた室内で起きた殺人事件(これは覗いていた自分の身を守るために詳細を警察に通報できない)や、隣室から漏れる声を聞くべく壁に耳をそばだてる男も目撃する。ここで書くことは控えるが、気持ち悪くも抱腹絶倒のエピソードもある(なお、彼は詳細な記録魔でもあった。利用者の体位やオーガズムの回数まで集計し、「性的にかなり活発」だったか否かも調査して、カップルの4組に1組は「活発でなかった」と結論づけている)。
もっとも、ポルノグラフィとしてみれば、その表現は凡庸だ。最近の本でいえば、蓮實重彦の傑作『伯爵夫人』(新潮社)のような芳醇な性描写とは比すべくもない。だがこの本の白眉は、そうした“幸福な”性行為と相反するシーンにある。下半身がままならないベトナム戦争の帰還兵とその妻の献身的な行為。男がコトを強引に進めるケースもあれば、妻の前では不能のため、彼女がバスルームにいる間に自慰にふける夫もいる。部屋や寝具の使い方のマナーが酷く――これまた書くのがはばかられるのだが――覗き魔が憤慨することもある。
さらに、何もせず仕事のことしか話題がないカップル。金勘定でもめ、旅の行き先でもめ、何を食べるかで口論ばかりする客がいかに多いことか。テレビばかり見てほとんどコミュニケーションのないカップルも。覗き魔はこうした客たちの「時間の使い方の貧しさ」を嘆くようになる。戦場での残虐行為を誇らしげに語る男たちの話を聞いて激しく嫌悪もする。
「観察実験室」からの凝視で性的好奇心を満たす一方で、どんどん人間が嫌いになる。そう、本作は単なる好色中年男の面白おかしい記録ではないのである。客のフロントで見せる人となりと、密室での違い。「基本的に人々は不誠実で不潔だ。人は騙し、噓をつき、自分の利益だけで動く」「人前で演じている顔と自分だけになったときの顔がまるっきり別人になる」。ペシミスティック過ぎる人間観かもしれないが、これを誰が否定できるだろう。
著者のタリーズは覗き魔の行状に困惑し、記録の不正確さもあって、誇張や妄想の可能性を疑いつつも、彼を「同時代人の偽善や隠された欲望をあばこうとする批評家」とさえ呼ぶ。対面で人に接するしかないジャーナリストは、こうしたむき出しの「人間観察」を続けた彼に大いに嫉妬をしたのかもしれない。
結局、この覗き魔は高齢もあってモーテルを閉めることになるが、町中に氾濫する監視カメラや、GPS、インターネットなどによる「監視社会」への反発を語る。「お前がそれを言うか」と著者ともども呆れたが、彼が覗きを始めた当初のくだりを読み直したら、「権力を手中におさめた感覚と歓喜を味わった」とある。もしかすると、ここが本書の核心ではないのか。この覗き魔は、おそらく監視することの権力性/暴力性を身をもって実感してきたに違いない。
最近またジョージ・オーウェル『一九八四年』(ハヤカワepi文庫)が関心を集めている。監視カメラ、盗聴、盗撮、SNSなどでプライバシーの暴露が問題になるいま、本書のモーテルを現代社会の暗喩とみてはうがちすぎだろうか。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください