木谷佳楠 著
2017年04月06日
おもしろい。本書は元々、同志社大学大学院神学研究科に提出された博士論文。だが、一般向けに大幅に改めたと断りがある通り、じつに読みやすい。
『アメリカ映画とキリスト教――120年の関係史』 (木谷佳楠 著、キリスト新聞社)
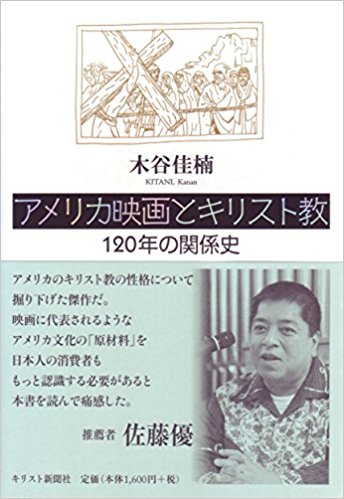 『アメリカ映画とキリスト教――120年の関係史』 (木谷佳楠 著、キリスト新聞社) 定価:本体1600円+税
『アメリカ映画とキリスト教――120年の関係史』 (木谷佳楠 著、キリスト新聞社) 定価:本体1600円+税構成は時系列で、1章「映画の誕生とキリスト教(1880-1920年代)」、2章「プロダクション・コードの施行と検閲の開始(1930-40年代)」、3章「『神の国アメリカ』とエリア・サガン(1950年代)」、4章「『古き良き時代』の終焉(1960-70年代)」、5章「キリスト教右派の台頭(1980年代)」、 6章「終末思想とアメリカ映画(1990-2000年代)」。つまり時代ごとに具体的な作品、映画業界の動向とアメリカ社会の側面が、じっくり考察される。
特に惹き込まれるのは、(一般読者には「創世記」がそうであるように)前半部。驚かされるのは、アメリカの多くのキリスト教団体が、映画が本格的に産業化される前から宣教のための有効性に注目し、聖書取材作品の製作と上映に積極的だったこと。
そもそも聖書という「オーラル・メディア」と、ステンドグラス、教会建築・音楽という「オーディオ・ビジュアル・メディア」の組み合わせ自体が映画向きと説明されると、(アメリカだけに)まさにコロンブスの卵と納得する。初期に最も普及した映像は、『キング・オブ・キングス』(1927年)のH・B・ワーナー演ずるイエス。当時の米国人の多くは、祈りの時にワーナーの顔を思い浮かべたという。
ところが映画人気が高まるにつれ、業界に放蕩が広がり、教会は圧力団体化する。一方、大衆動員を見込んだ興行主たちが巨大産業化を推進し、作り手はアングロサクソン系(発明者エジソンもそう)からユダヤ系へ、拠点もニューヨークからハリウッドへと移る。時代は、大恐慌。現実逃避を渇望する大衆に応えるため、映画界は、聖書以外の様々な物語で人々をとりこにする。暴力と性的表現は(今の目で観ると慎ましいが)、キリスト教団体から指弾され、反ユダヤの動きも活発になる。
かくして、カトリックとプロテスタント各派が共同で突きつけたのが「プロダクション・コード」。大罪を犯した映画界に示された《十戒》(本書の中の比喩)である。
このコードは、1934年から68年までハリウッドを制した。神への冒涜、性的不品行、殺人ほか違法行為の描写は、全てNGとされた。例えば、未婚の男女が寝室に「いる」だけで禁止。夫婦でも同じベッドに入る描写は禁止。そこでダブルベッドを分割した「ハリウッド・ベッド」が開発された(「ツインベッド」の起源?)。「ターザン」のヒロイン(モーリン・オサリヴァン)の衣装も変わった。34年《Tarzan and His Mate》は露出の多いビキニふう、2年後《Tarzan Escapes》では肩も隠したワンピースふうである。
もちろん、より本質的な影響も多い。例えば『カサブランカ』(1942年)。リック(ハンフリー・ボガード)とイルザ(イングリット・バーグマン)は、回想場面で明らかに恋人だが、性的な暗示は許されなかった。イルザには夫(ポール・ヘンリード)がいたから。もしリックとの性的関係を描写すると不倫の奨励となり、コードが認めない。またラストでリックは、イルザと夫だけを亡命させる。あれを我々はリックの男気と見、グッとくる。だが著者は、コードに基づく処置であり、かつ欧州の戦争に加わる米国人の意思を示すことで「時代の要請」に応えたと言い添える。傑作誕生の皮肉さである。
戦後の有名作品では、『ベン・ハー』(1959年)。イエスの姿はつねに斜め後ろか遠景で、正面からは映さない。驚愕し、畏敬するベン・ハー(チャールトン・へストン)の表情で全てが表される。この撮影手法、巧みな演出とずっと思っていたが、実は「神の子」をはっきり描写するのを冒涜とするコードへの配慮だったのだ。
こうした往年の伝説的名作の点検はわくわくする。だが、そればかりではない。考察を進める著者の姿勢は揺るがないが、読む側の気分が重い部分もある。例えば赤狩りの時代、昔の共産党員仲間の名を明かしたギリシャ系《ユダヤ人》監督エリア・カザン。まさに《ユダ》とされた名匠はハリウッドでの復権を賭け、自身の「裏切り」とキリスト教的「犠牲」を投影した『波止場』(1954年)を撮ってオスカー8部門受賞に輝いた。
だが、カザンへの毀誉褒貶は相半ばする。ことの本質は映画界だけの問題ではない。「プロダクション・コード」廃止後もアメリカ社会に存在する強い《戒め》を思い知るのだ。例えばイエスを描いた『最後の誘惑』(1988年)と『パッション』(2004年)。それぞれ経緯に光が当たるけれど気分は暗くなる。前者は宗教右派から激しく抗議され、後者は影響力のある宗教家を味方につけ大成功。だが、反ユダヤ的視点への批判は長く尾を引いた。
最終章では、「9・11」を経たアメリカが、聖書に忠実か否かにかかわらず、新たな《敵》を映画に描き込むことで(聖書にある)終末思想を伝えた諸作も、紹介される。その根底には、建国の伝統への回帰という聞きなじみのある標語が潜んでおり、極東の島の凡夫にも、強い危機感を覚えさせずにはおかない。
量産されるアメリカ映画は、メディア激変の時代でも合衆国の象徴であり、世界へ影響力を持っている。制約する社会と束縛する国家でしか生きられない個人に、巧緻であれ幼稚であれ、夢を与えてくれることもある。鑑賞後、苛烈な現実に引き戻されても、だ。
しかし著者は、非米国人がアメリカのキリスト教と映画の関係を知る意味を、「輸入された食品のパッケージに記載された『原材料』を見る行為」と、絶妙な比喩でしめくくる。確かに我々は「国産」だけで満足できず、かの国が作り出す様々な「輸入品」を口にせざるを得ない。ならば「原材料」の知識の有無は心身に大きく影響しよう。
もしも著者が《一つ一つの言葉》に聖なる何かを込めたとしても、忖度する必要はない。《パンのみ》いや《映画のみ》の魅力を貪りたい不純な動機で読んでも、本書は充分おもしろいから。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください