森まゆみ 著
2017年05月25日
本書のタイトルは、ハンナ・アレントの同名の作品から取られている。その冒頭に置かれた彼女の文章を引けば、本書の意図がより明確に伝わってくる。
――最も暗い時代においてさえ、人は何かしら光明を期待する権利を持つこと、こうした光明は理論や概念からというよりはむしろ少数の人々がともす不確かでちらちらゆれる、多くは弱い光から発すること、またこうした人々はその生活と仕事のなかで、ほとんどあらゆる環境のもとで光をともし、その光は地上でかれらに与えられたわずかな時間を超えて輝くであろうということ(ちくま学芸文庫、阿部齋訳)
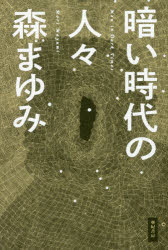 『暗い時代の人々』(森まゆみ 著 亜紀書房) 定価:本体1700円+税
『暗い時代の人々』(森まゆみ 著 亜紀書房) 定価:本体1700円+税戦前回帰などありえない。きっとどこかでブレーキがかかるだろう……頭の片隅にあったそんな甘い考えも捨てて、どうやら本気で腹を括らざるを得ないようだ。
これから迎えることになる「暗い時代」を、いったい何を指針にして生きていったらいいか……その問いに、大正末から戦争に向かう時代を生き抜いた9人の人生を描くことで、本書はある答えを提示してくれる。
斎藤隆夫、山川菊栄、山本宣治、竹久夢二、九津見房子、斎藤雷太郎、立野正一、古在由重、西村伊作。
著者も「あとがき」に書いているとおり、このうちの誰を取り上げても優に一冊の本になるだろうし、実際すでに複数の本が出ている人もいる。では本書は、それぞれの人生を駆け足で紹介したもの、ある種ダイジェストのようなものかといえば、そうではない。
まずひとつには、この9人は必ずどこかで著者の人生と繋がっているのである。それは地縁であったり、親族から聞いた言葉が忘れられなかったりすることもある。あるいは関係者に直接取材した経験があったり、古在由重のように師と仰いで謦咳(けいがい)に接した例もある。
そしてまた、取り上げた9人それぞれが様々な縁で繋がってもいる。それが同時代を生きるということで、いわば本書は、森まゆみというこれから「暗い時代」を生きることになるだろう作家の人生の軸が、かつてあった「暗い時代」を生きた人々の人生の軸と交差する様を描いたものだといえる。
この9人には、戦争へと向かう「暗い時代」を、各々のやり方で「生き抜いた」ということの他に、明らかにある共通点がある。
そのひとつは、各々の人生の驚くべき「首尾一貫性」である。決して初志を曲げない、いや、曲げられない性の下に生まれているということ。そしてふたつめにはどんな苦境にあってもどこかで「明るさ」を保っている、ということである。
その「明るさ」はいったいどこに由来するか。
たとえば著者は、帝国議会での「粛軍演説」で有名な斎藤隆夫の、よくいえば「現状に満足しない」、言葉を換えれば「堪え性のない」少年時代、京都に丁稚奉公に出たがたった3ヶ月で戻ってきてしまったことを紹介しつつ、こう綴る。
「えらいと思うのは、家出をして帰郷した末っ子を、兄や姉、兄嫁、父、母ともにしかることもなく、無事を喜んでくれたというところである。すなわち、この一家は維新後の近代的な立身の道を知らなかったが、子供、兄弟に対して愛情を持っていたとわかる。家族の愛情は人を支える」
家族愛、夫婦愛、子供を慈しむ姿。読み返してみればタイトルと裏腹に、本書のいたるところには様々な「愛の姿」が描かれている。
時代に抗い〈よく闘う〉人は、すなわち〈よく愛する〉人でもある……これから予想される「暗い時代」 にどう生きたらいいか、先に挙げた問いかけにある指針を得たと感ずるのは、本書の奥に潜むそんなメッセージに触れたときである。
だいたいがこんなしんどい時代を生きていくのに、愛でもなければやってられないではないか。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください