2017年07月31日
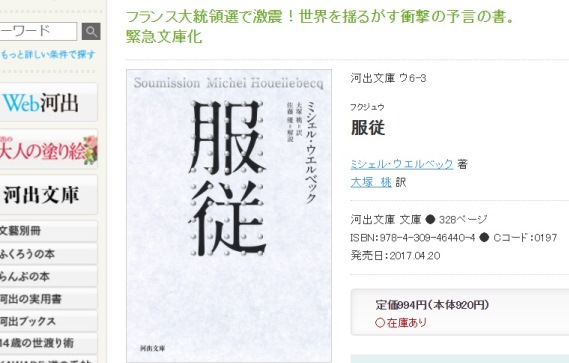 ミシェル・ウエルベック『服従』(河出文庫版)=河出書房新社の公式サイトより
ミシェル・ウエルベック『服従』(河出文庫版)=河出書房新社の公式サイトより「ぼく」が過去の恋愛関係/性生活を述懐するパートは、これまたウエルベック十八番(おはこ)の、憂鬱かつデカダンな艶笑譚(えんしょうたん)といった趣で、あられもない表現、偽悪的で辛辣なリアリズム、苦いユーモアが混然一体となった、至芸ともいうべき語り口を堪能できる(私のある知人は、主人公がなぜここまで恋愛やセックスに執着するのかわからない、またこういう描写は女性差別ではないか、と言っていたが、こんにちの日本の読者の感想としては、さもありなんと思う)。
先に触れたように、かつての「ぼく」はごく当たり前のように女子学生たちと関係していたが、以下の一節では、そうした恋愛生活を、「ぼく」はドン・ファン(女たらし)的な放蕩趣味からではなく、ある種のルーティンとか、孤独への対症療法的な気晴らしとして続けていたこと、そしてそれが「ぼく」の昇格につれて終わりを迎えた経緯が、加齢における男女差などについてのアフォリズムなどもまじえて、じつに微妙なニュアンスで記される――「〔准教授に就任して最初の何年間は〕ぼくは、毎年のように、女子学生たちと寝た。彼女たちに対して教師という立場であることは、何かを変えるものではなかった。ぼくと彼女たち学生の年齢の違いは始めの頃は大きくなかったし〔当然だ〕、それがタブーの様相を呈してきたのはどちらかと言えば大学での昇進のせいであって、自分が年を取ったからでも、老いが外見に現れたからでもなかった。女性の性的魅力の崩壊は驚くべき荒々しさで、ほんの何年か、時には何か月かの間に起こるが、男性の加齢はその性的な能力をとてもゆっくりしか変えないという基本的な不公平をぼくは十全に利用した。〔……〕自分にドン・ファンの趣味があったわけではいささかもなく、抑えがたい放蕩生活の欲望に駆られていたわけでもない。同じように一、二年生を対象に十九世紀文学を教えていた〔……〕スティーヴとは違って、ぼくは、新学期の一日目から一年生という「新入荷商品」に貪欲に飛びついたりはしなかった。〔……そして〕ぼくがそういった若い女の子たちとの関係を止めるのは、〔……〕やる気がなくなり、飽きてしまうからだった」(『服従』単行本17~18頁)。まあ、「ぼく」もスティーヴも、日本の大学ではありえないような放埓(ほうらつ)ぶりだが、しかし言うまでもなく、こうした書法が煽情的なポルノグラフィーのそれとはまったく異なるのは、性行為の行き着く先の倦怠が記されるからだ。
もっとも、「ぼく」の付き合った最後の女子学生、ミリアムとのセックスがあられもなくエロチックに
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください