2017年08月02日
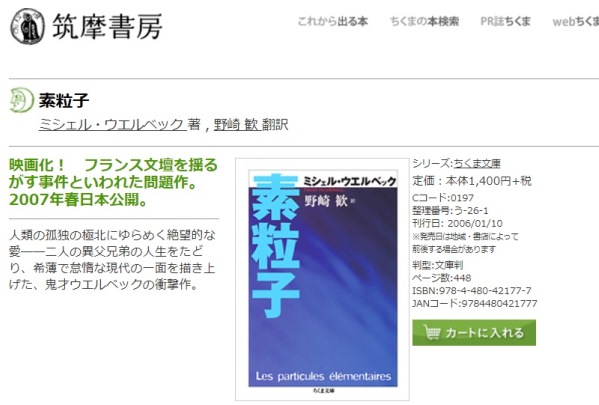 ミシェル・ウエルベック『素粒子』(ちくま文庫)=筑摩書房の公式サイトより
ミシェル・ウエルベック『素粒子』(ちくま文庫)=筑摩書房の公式サイトよりここでは、主人公の一人ミシェル・ジェルジンスキの視点から、パレゾーの町のSF映画的光景が比喩として記述されるだけだ。しかし、読み進めていくと、『素粒子』は異形のSF小説でもあることが明らかになる。
すなわち、『素粒子』の主題のひとつが、遺伝子操作による知的生命体の創造(クローニング)であるばかりか、本作の語り手は、なんと2200年代を生きる、人間によって人工的に創造された新たな知的生命体であることが、ラストで告げられるのだ(その時点では人間/人類はすでに滅亡している)。作中の時間を未来にまで拡張するSF的発想である。そしてそれは、のちの『ある島の可能性』、『地図と領土』、『服従』までを貫いているが、ではなぜ、ウエルベックはSF的構想を好むのか。
SFこそは、社会の大きな変動、ないしは文明の興亡を、終末論的ヴィジョンとともに長いスパンで描き出すうえで、もっとも効果的なジャンルだからである。とりもなおさず秀逸なSF小説とは、今現在の現実を未来に延長させ、風刺的・空想的に変形させることで――リアリズム小説とは異なる手法で――かえって人間や社会の実態をリアルに、あるいは戯画的・寓意的に描きうるジャンルだといえる。
そうしたジャンルの古典には、ジョージ・オーウェル『1984年』『動物農場』、オルダス・ハックスレー『すばらしい新世界』などなどの、反ユートピア/ディストピア小説があるが、ウエルベックの小説にも、ディストピアのモチーフは顕著だ。『素粒子』に登場するディストピアは、前記「変革の場」であるが(同131頁以降)、それは前述の『ある島の可能性』に登場したラエリアン・ムーブメントのような、東洋神秘、ヨガ、瞑想、占星術、タロットカード、火の修行、フリーセックスといった1960年代ドラッグ・カルチャー/ニューエイジ系のアイテムを掲げる、「無限の自由の謳歌」を目指す“ユートピア”的コミューンだ。
そしてむろん、性愛における無限の自由が追求されるはずの「変革の場」は、実際には優勝劣敗(とくに若さの優越)の法則が支配する過酷な性的競争の闘技場=ディストピアである。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください