R・D・ウィングフィールド 著 芹澤恵 訳
2017年10月18日
「フロスト警部」シリーズの最新作を取り上げるのは、この1作で楽しみを味わえなくなる淋しさ故である。作者のウィングフィールドは2007年7月に惜しくも逝去。その遺作が日本語訳で読めたのはこの夏の快事。「神保町の匠」で取り上げるのは異例のことかもしれないが、どうしてもこのミステリーのおもしろさを伝えたいからなのだ。どうかご容赦あれ。
『フロスト始末 上・下』(R・D・ウィングフィールド 著 芹澤恵 訳 創元推理文庫)
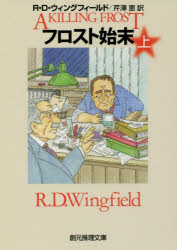 『フロスト始末 上』(R・D・ウィングフィールド 著 芹澤恵 訳 創元推理文庫) 定価:本体1300円+税
『フロスト始末 上』(R・D・ウィングフィールド 著 芹澤恵 訳 創元推理文庫) 定価:本体1300円+税まず第1に、こんなにはちゃめちゃな物語はなかった。犯罪捜査に当たる人物と言えば、常人にはない洞察力を持ち、「灰色の脳細胞」を駆使して犯人を確定するのが常套手段。しかし、フロストは行き当たりばったり、思いつきで捜査を続け、結果的に未解決事件の山に悩まされる。それでも破れかぶれな捜査の果てに、何とか結末を迎えてほっと一安心。
第2に、フロストはデントン署の警部である。法を守る立場である。それが書類の改ざんをする。証拠をでっち上げる。家宅捜索に必要な許可証もなく、勝手に家屋侵入をおこなう。ともかくやりたい放題なのだ。もちろんそれが一刻も早く犯人を捕らえたい一心からのことだとしても、フロストの仇敵マレット署長にすれば、目に余る行為なのである。
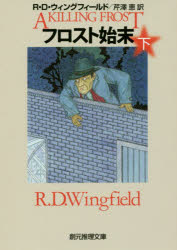 『フロスト始末 下』
『フロスト始末 下』というわけで、何とも無軌道な世界が次々に展開されるのだが、本で読むには構わないとしても、これがテレビ・ドラマになると、かなり穏やかにせざるを得ない。その結果、テレビのフロスト・シリーズは否応もなく脱色されることになる。だから原作者ウィングフィールドは、テレビ・ドラマ化されたものをほとんど見なかったとされるが、これも致し方のないことだろう。
かくいう筆者も最初はずいぶん安全な脚本だと思ったが、それでも人情の機微が見られる場面に惹きつけられることがあった。要するに別作品だと思えばいいのである。
最後に、そして何よりもこのシリーズが日本の読者を大いに惹きつけたのは、芹澤恵さんという女性の大胆な名訳によるところが大きかったことを付け加えておきたい。その一例を『フロスト始末』の下巻から引けば、次のようなものである。
「それじゃ、芋にいちゃん(タフィー)、あの塀を越えられるようにちょいとひと押ししてくれや。塀を乗り越えたら、内側から木の扉の閂をはずしておくことにするよ。目的遂行中に速やかな退却ってやつが必要にならないとも限らないから。といってもおまえさんには通じないか? 夜の姫君用語で説明するなら“ちょっと、さっさと抜いて、外で出してよ”ってやつだよ」
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください