2018年07月20日
人は本を読んで未知の世界を知る。自我の芽生え、性への目覚め、愛するということ、女が仕事をもつこと、社会の不条理・・・。
かつて読んだ本、読みそこなってしまった本、いつかは読みたい本。新しい経験への扉を開く、少女が大人になる過程で読んでほしい一冊を、さまざまに人生を切り拓いてきた女性ゲストとともに読む――。
2013年から一年にわたって開かれた、「少女は本を読んで大人になる」と銘打った読書会の「パート2」が4年ぶりに再開されることとなった。
場所は、来年50周年を迎える代官山ヒルサイドテラス。代官山は、今でこそ海外からの旅行者も多数訪れる「代官山 蔦屋書店」があるものの、10年ほど前には本屋がなく、「街には本が必要だ」ということで、同建物内に会員制図書室が設けられた。
 代官山ヒルサイドテラスの私設図書室の本棚。100人の“目利き”が選んだ10冊ずつの本が並んでいる。
代官山ヒルサイドテラスの私設図書室の本棚。100人の“目利き”が選んだ10冊ずつの本が並んでいる。会員組織「クラブヒルサイド」は誰でも入れるゆるやかな組織で、100人の"目利き″が10冊ずつ選んだ本を蔵書とするヒルサイドライブラリーの運営のほか、本やアート、建築、まちづくり、音楽、食などをテーマとしたオープンなセミナーやイベントも開催している。"目利き″には、今は亡き石牟礼道子さん、大岡信さん、筑紫哲也さんなどもいて、100人の"本棚″は貸出もしている。
「少女は」の読書会も、クラブヒルサイドの本をめぐるイベントのひとつとして企画された。パートナーは「スティルウォーター」。しなやかな活動をする女性4人組だが、特に食のセンスが素晴らしい。一緒に「日々、これ食卓」というワークショップも行っている。
パート1のときは、本と一緒に食もたのしむということで、テーマにあわせたミニサンドウィッチをハーフタイムに出してもらった。サンドウィッチは本を読みながら片手で食べられるし、本の形にどことなく似ている。参加者はそれを食べながら、同じテーブルの人と会話をはずませる、というわけだ。パート2では、ミニおむすびである。
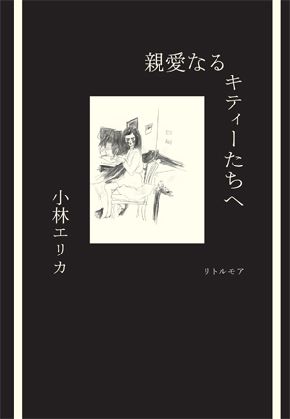 『親愛なるキティーたちへ』(リトルモア)。小林エリカさんは、現在、アンネ・フランク・ハウスから出版された子ども向けのアンネ・フランクの生涯の本を翻訳中。
『親愛なるキティーたちへ』(リトルモア)。小林エリカさんは、現在、アンネ・フランク・ハウスから出版された子ども向けのアンネ・フランクの生涯の本を翻訳中。そもそもこの読書会を企画したのは、マンガ家・作家である小林エリカさんの『親愛なるキティーたちへ』(リトルモア)に出会ったことがきっかけだった。
同書は、父の80歳の誕生日に父親の若い日の日記を発見した小林さんが、父とアンネ・フランクが同い年であったことに思い至り、アンネの足跡をたどる旅に出るところから始まる。10歳の時に『アンネの日記』を読み、「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」というアンネの言葉に揺り動かされ、作家を志した小林さんが旅の途上でつけた日記と、父の日記、そしてアンネの日記が交錯する、不思議な時空感覚を体験できる一冊だ。
人はこんな風に本と何度でも出会うことができるのだ――。
彼女の著書を読んで、浮かんだのがこの読書会の企画だった。昔読んだあの本を、もう一度読んでみたい。それもひとりではなく、誰かと。
そして組まれた10回のシリーズは、『アンネの日記』(小林エリカ)、モンゴメリー『赤毛のアン』(コミュニケーションディレクター・森本千絵)、サガン『悲しみよ こんにちは』(作家・エッセイスト・阿川佐和子)、ブロンテ『嵐が丘』(翻訳家・鴻巣友季子)、石牟礼道子『苦海浄土』(俳優・竹下景子)、尾崎翠『第七官界彷徨』(作家・角田光代)、林芙美子『放浪記』(ディレクター・湯山玲子)、高村光太郎『智恵子抄』(編集者・末盛千枝子)、伊丹十三『女たちよ』(エッセイスト・平松洋子)、エーヴ・キュリー『キュリー夫人伝』(生命誌学者・中村桂子)というラインナップである。
10人のゲストによる10冊の本へのアプローチはまさに十人十色。読書会の記録は書籍化(『少女は本を読んで大人になる』現代企画室)されているので、興味ある方は手にとっていただければと思うが、そこから伝わってくるのは、本の読み方は自由で、開かれているということだ。
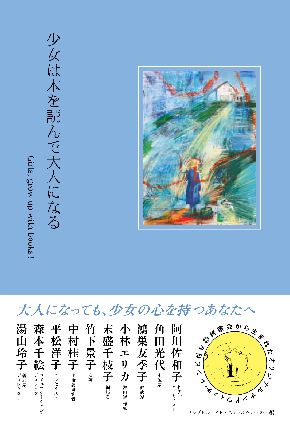 読書会パート1を記録した『少女は本を読んで大人になる』(現代企画室)。装画は出演者のひとり、森本千絵。
読書会パート1を記録した『少女は本を読んで大人になる』(現代企画室)。装画は出演者のひとり、森本千絵。 キュリー夫人の伝記はマンガ版も含めて、誰もが子どもの頃、いちどは読んだことがあるだろう。しかし、12万人が故郷を追われた3.11の福島第一原発の事故を経たこの国で、放射能の名付け親であるキュリー夫人の伝記はまったく違った読み方になる。
幼い頃に読んだ子ども向けの伝記ではなく、娘エーヴが書いた分厚い伝記を読み進めていくと、そこに描かれるキュリー夫人の偉大さ以上に、科学の矛盾とは人間存在の矛盾であることに思いがいってしまうのだ。
ラジウムの発見に至る血のにじむような彼女の努力はすさまじい。ボロボロの倉庫で大量の放射性物質の粉じんにまみれての4年に及ぶ作業。放射能の恐ろしさを知ってしまった私たちは、キュリー夫人が自らの命と引き換えに世紀の発見を手に入れた事実に慄然(りつぜん)とする。時代が本の読み方も変えてしまうのだ。
この読書会で知ったのは、再読の面白さである。再読を通して、私たちはその本と出会った時の自分と再会し、さまざまな人生経験を経て、その時とは異なる見方をする今の自分を発見する。この二重の出会いは、私たちの生を豊かにしてくれるはずだ。
 マリーナ・アブラモヴィッチ『夢の本』。新潟県越後妻有にある彼女の作品「夢の家」に宿泊した100人が見た夢の記録。石牟礼道子の他、茂木健一郎、大宮エリー、谷川俊太郎、中沢新一等が寄稿。
マリーナ・アブラモヴィッチ『夢の本』。新潟県越後妻有にある彼女の作品「夢の家」に宿泊した100人が見た夢の記録。石牟礼道子の他、茂木健一郎、大宮エリー、谷川俊太郎、中沢新一等が寄稿。今年2月、石牟礼道子さんが亡くなられた。私は直接面識はなかったが、マリーナ・アブラモヴィッチという世界的なパフォーマンスアーティストの『夢の本』を編集する機会があり、石牟礼さんに夢についての寄稿をお願いしたことがある。「どんな夢を見るか楽しみで、床につく」と語っていたと聞いたからだった。
石牟礼さんの文章には、人間の極限的状況を描きながら、夢と現実のあわいの中に立ち現れるような美しさがあって、それゆえにいっそう悲しさと静かな怒りが海のように身体のなかに拡がっていく。
思えば、読書会をシリーズとして編んだのは、石牟礼さんの『苦海浄土』を“少女たち”に読んでほしかったからだ。
初めてこの本を読んだのは学生の時だった。あまりの衝撃に、しばらくその世界から抜け出せなくて苦しんだ。
水俣病患者さんたちの言葉にならない思いを、石牟礼さんは巫女(みこ)のように、この本で伝えられた。魂が震えるような石牟礼さんの言葉を、読書会では、水俣病の問題に深く心を寄せ、石牟礼さんとも親交のあった竹下景子さんに読んでほしいとお願いした。
竹下さんは時に涙ぐみながら、朗読してくださった。竹下さんの声にのって流れる美しい水俣の言葉は、私たちを遥(はる)か不知火の海へと連れていってくれた。
今もまだ、石牟礼さんを惜しむ声は絶えることがなく、その人と文学は語り尽くされることはない。親交のあった人々は、その人柄に深く魅了され、もう会えないという寂寞(せきばく)はいかほどかと思う。
でも、石牟礼さんは本を遺(のこ)した。
「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」というアンネの望みを、果たして石牟礼さんが抱いていたかはわからない。確かなのは、私たちは本を通して、何度でも石牟礼さんに会えるということだ。
パート2では、女優・鶴田真由さんによる「川端康成」、マンガ家・内田春菊さんによるガルシア・マルケス「エレンディラ」、フォトジャーナリスト・安田菜津紀さんによる「100万回生きたねこ」、ミュージシャン・大貫妙子さんによる「茨木のり子」、編集者・若菜晃子さんによる「石井桃子」などが決定している。映画監督の石山友美さん、料理家の細川亜衣さんは、どんな本を選ぶのだろう。さらに、どんなゲストをお招きしようか。
この連載では、読書会のレポートも交えながら、さまざまな本との再会と新たな出会いを楽しみたい。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください