「菩提樹」を含む名歌曲集の奥に潜むものは? シューベルトとは何者か?
2018年09月16日
 ウイーン市立公園にあるシューベルト像=オーストリア・ウイーン =2011年11月3日
ウイーン市立公園にあるシューベルト像=オーストリア・ウイーン =2011年11月3日「歌曲の王」と称され、31歳の短い生涯に600曲にものぼる歌曲を作曲したフランツ・シューベルト(1797~1828)。彼がウィルヘルム・ミュラーの「ヴァルトホルン吹きの遺稿からの詩集第2巻」(1824年デッサウで出版)に収められた24の詩に曲を付け、1828年に作曲を完成させた歌曲集「冬の旅」は、シューベルトの代表作のひとつとして知られる。
有名な「菩提樹」を含む連作歌曲集「冬の旅」の楽曲や歌詞、その背後にあるさまざまな要素を丹念に読み解き、10年のときを経て『死せる菩提樹 シューベルト《冬の旅》と幻想』を著したのは、桐朋学園大学学長、早稲田大学講師、毎日新聞学芸部特別編集委員の梅津時比古さん。
今回はその著作を中心にシューベルトの天才性、作曲家が生きた時代、「冬の旅」の奥に潜むものなどについて、WEBRONZA編集長の吉田貴文さんと対談を行った。(構成・伊熊よし子)
――まず、『死せる菩提樹』を読んだ感想から聞かせてください。
吉田貴文(以下、吉田) 私の母はイタリアやフランス、ドイツ歌曲を専門としている歌手でしたので、子どものころから声楽曲にはかなり親しんできました。よく歌曲のリサイタルに連れて行ってもらいました。
シューベルトの「冬の旅」は中学生のころに初めて聴き、最初は長くて退屈な曲だなあと思っていましたが(笑)、高校生になったころには録音を聴いたり、歌詞をじっくり読み込んだりすることで徐々に作品のよさが理解できるようになりました。
シューベルトは美しい旋律の曲が多いのですが、「冬の旅」は第1曲の「おやすみ」から最後の「辻音楽師」にいたるまで、ただ美しい曲ではなく、非常に叙事詩的で、心に残る曲集となっています。ただし、これまで「冬の旅」をこのように研究・分析した本を読んだことはなかったため、今回は非常に興味深く拝読しました。文字で「冬の旅」を聴くというのは初めての経験ですので。
私はこれまで「菩提樹」はきれいな曲だなと思っていましたが、この本には、曲の背後に潜むある種のぞっとするもの、樹はやがて枯れていくということも含めて描かれている。いろんな意味で発見がありました。私はデーィートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)とダニエル・バレンボイム(ピアノ)のCDを聴き直しながら本を読み、さまざまなことを勉強しました。
 梅津時比古さん
梅津時比古さん
吉田 初めて買ったレコードはフィッシャー=ディースカウだったと思いますが、実演は誰だったか、よく覚えていません。ずいぶんいろんな歌手のナマの演奏を聴きました。
梅津 でも、中学生のころから「冬の旅」を聴いているというのはすごいですね。
吉田 当時、友人に「冬の旅」が大好きで、リコーダーで吹いている人がいました。歌だから吹けるんですよ。私もシューベルトはとても好きな作曲家です。本当の意味の天才だと思います。彼のまわりに若い友人が集まって音楽を聴いたシューベルティアーデは、完全にシューベルトの才能に惹かれたのだと思います。シューベルトはいわゆるスターに近い存在で、それまで宮廷で行われていた演奏会をベートーヴェンに継いで市民の間に根付かせた。新しい時代の天才だったと思います。
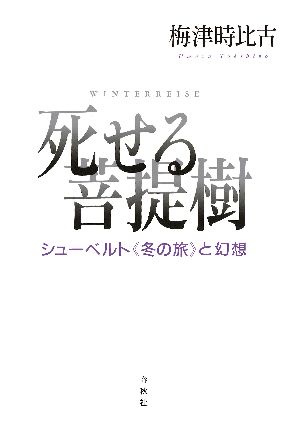 『死せる菩提樹』
『死せる菩提樹』梅津 当時のモーツァルトもベートーヴェンも旅することは学ぶことでした。中世の哲学者はケルンやローマやミラノなどいろんなところに旅して学んでいったわけです。でも、シューベルトはほとんどウィーンのなかだけで活動していました。まったく「井の中の蛙」。このことばは、そのあとに「大海を知らず」、さらに「されど天の高きを知る」と続きます。
「大海を知らず」はマイナスの要素でとらえられますが、井の中の蛙が、一点を掘り下げると、天の高さを知る。そこを突き抜けると、地域性を脱して世界的な広がりをもってしまう。シューベルトは極めて珍しい、そういう芸術家ではないでしょうか。日本でいえば、宮沢賢治のような。
吉田 人間はいまあるものを学ぶ、それを自分で深堀りしていくわけですよね。シューベルトは生まれた環境も関係しているかもしれませんが、外には行けなかった。ただし、自分のありあまる才能を徐々に掘り下げていき、常に音楽のことだけを考えています。ちょっと他の作曲家とは違う感じがします。
梅津 いまの世界は情報過多で、情報を得ることは知を得ることと誤解している面があります。情報を得ると、人間はどうしてもそれに影響される。しかし、シューベルトはそういうことを知らなかったため、自分で考え、自分の感性で自分自身に100パーセント対峙(たいじ)することができる。そのなかで深め、極めていく。人から得た情報や知識ではないため、亜流にならないわけです。それが私たちの時代へのひとつの教えになっていると思います。
近年は、音楽コンクールなどでも、ああ、この演奏はダニエル・バレンボイムのようだなとか、マルタ・アルゲリッチのまねだなとか、そういう演奏がとても多い。ですから、私はまずCDを聴いたりユーチューブを見たりして誰かの演奏を聴くのではなく、何も聴かずに自分の音楽を作り上げた方がいいと考え、学生にはいつもそう助言しています。最初に他の人の演奏を聴いてしまうと、絶対に影響を受けますから。自分で楽譜から作曲家の意図を読み取り、自分で考えて演奏すれば、必ず自分自身のものが何か出てくるはずです。
本を書くときもそうですね。ひとつのテーマを見つけたら、ずっとそれを考え抜き、その後で資料を調べる。『死せる菩提樹』に書いたシューベルトとニーチェの結びつきに関しても、資料はほとんどないので、それだけに意欲が湧いてくるわけです。さらに深く探求したくなってくるから。
吉田 このシューベルトとニーチェとの結びつきは、驚きました。まさかここでニーチェが出てくるとは思いませんでした。
梅津 シューベルトは、以前書いた『冬の旅 24の象徴の森へ』からずっと研究を続けていたのですが、それとは別にニーチェというのは自分のなかで書きたいものがあって、最後に両者がぶつかったのです。ああ、そうか、ここでつながると。ある意味、外形的にはつなげたんですが、最初からそう構想していたわけではなく、最終的に書いているうちに自分のなかで発見があったのです。
 シューベルトの生家 =ウイーン
シューベルトの生家 =ウイーン吉田 シューベルトは他から影響を受けていないという話がありましたが、いままでの常識から考えられないような変わった曲を数多く書いていますね。転調の仕方にしてもベートーヴェンのような転調とは違いますし、次から次へと転調を繰り返して、いったいどこにいってしまうのか。ピアノ・ソナタにもいえることですが、最初は不思議な曲だなあと思うものが多い。ベートーヴェン的な完成された形を考えていると、なぜ急にここでビアノが荒れ狂ったりするのだろうと。
梅津 破壊的になったり。
吉田 そうそう。ずっとこんなにのんびりしたテンポで、どこまで続くのかと思う面もあります。「冬の旅」の「辻音楽師」も、上声部と低声部の響き合いが実に不思議。私は子どものころピアノを少々弾いていて、母が練習する時に伴奏させられたりしましたが、シューベルトは難しかったですね。ニュアンスが違うと、いつも母には怒られていました(笑)。
梅津 そうですね、ベートーヴェンは素晴らしいですが、転調もある程度予測がつき、方向性がつかめます。シューベルトはまったく異なります。シューベルトは、晩年に、まだ対位法を習いたいといっています。逆に言えば、そういう影響を受けていなかった。
 ウィーン・シェーンブルン宮殿脇の菩提樹の並木=2011年10月31日
ウィーン・シェーンブルン宮殿脇の菩提樹の並木=2011年10月31日
梅津 私は吉田さんとは違って、「冬の旅」に入ったのは遅く、30代になってからです。もちろん、曲は知っていましたが、向こうの現場を知りたくて、ケルンの音楽大学に1年間学びにいったんです。その音大の歌曲伴奏のヴィルヘルム・ヘッカー教授から「冬の旅」について示唆を受け、2007年に「冬の旅 24の象徴の森へ」を書いたのですが、何か自分のなかにいまひとつ残余感があり、いろんな試みをしていたわけです。
そのなかでずっと気になっていたのは「菩提樹」で、シューベルトは初演したときから友人たちに「菩提樹」だけはいいといわれていた。それは旋律的に受けるからだと私は表面的に解釈していたのですが、実はそうではなく、「菩提樹」は曲集全体の中心にあり、表立っては見えませんが、これが24曲を変容させていくのではないかという考えが染み出してきたんです。そうした考えをいろいろ巡らしているうちに10年も経ってしまいました。日々の多忙のなかでずっと書き続けていることはできず、「菩提樹」に焦点を当てて考えていたのです。
吉田 確かに、「菩提樹」は中心にあるんですね。こういう発想は私のなかにありませんでした。平面的に24曲をとらえていたのですが、この本を読むことによって曲が立体的に見えてくる感じです。
梅津 背後に見えない形で屹立しているのが「菩提樹」だと思います。最後は倒れていくのですが、あまりにも曲がメロディアスなため、本来の意味が見逃されてしまうのでは。
吉田 最初に「冬の旅」を聴いたときは、モノトーンな感じを受けました。あまりにもきれいな旋律を聴くと、そのときは魅了されるのですが、すぐに飽きてしまいます。でも、「冬の旅」は何度聴いても飽きない。シューベルトのたどり着いた最終地だったのかなと。
 梅津時比古さん
梅津時比古さん
吉田 確かにおどろおどろしい面があります。ですから、ところどころに登場する長調の曲が美しく聴こえる。でも、驚かしてやろうというのではなく、とても内省的で等身大で、それが「辻音楽師」に表れています。
梅津 あんな世界はだれも書けないですよ。
吉田 あれほど表現が過剰なのは、すごいなあと。
梅津 過剰で抑制されている。シューベルトの時代は作品が自立した時代。それをシューベルトは突き抜けて、作品と作品が互いに注釈し合うというとらえ方をしています。「辻音楽師」はシューベルトの「白鳥の歌」の「影法師」と注釈し合っているし、「冬の旅」の前半の12曲を、後半を書いているときに注釈している。驚くべきことを無意識にやっています。
吉田 「冬の旅」のなかで梅津さんがもっともお好きな曲はどれですか。
梅津 「菩提樹」は一番ひっかかってくる曲ですが、好きな曲というと
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください