2018年09月28日
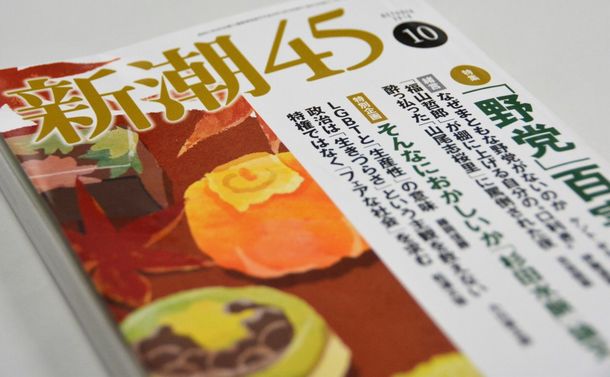 特別企画「そんなにおかしいか『杉田水脈』論文」を掲載した「新潮45」2018年10月号
特別企画「そんなにおかしいか『杉田水脈』論文」を掲載した「新潮45」2018年10月号※以下の原稿を編集部に渡した直後、「新潮45」休刊のニュースが入った。そのことへの賛否はともかく、この原稿の内容に関しては変える必要をいささかも感じていないので、そのまま掲載していただくことにする。
ただ付け加えるとすれば、新潮社においては自らのアイデンティティーをより大事に考えていただきたい。そのことが出版界の劣化を防ぐ唯一の方法だと考える。また、新潮社は報道陣の取材に対して、10月号のゲラを読んでいたのは編集部のみと答えた。問題になった特集の原稿は、もしかしたら校閲を通っていなかった可能性も考えられる。とすれば、文中「編集者としての矜持」としたが、それ以前の問題で、読者からお金を貰っている以上ちゃんと仕事をしろ、というだけの話である。
また、執筆者である小川榮太郎氏に関しては何をかいわんや、自らの書き手としてのレベルの低さをぜひとも自覚していただきたい。そしてより大きな怪我をしないうちに、この世界から身を退いていただくことを切に祈るのみである。
その昔、失業中のこと、よく臨時のアルバイトで雑誌の出張校正に駆り出されて、印刷所や出版社に通った。今はもう出張校正などという習慣は出版界からほとんど消えてしまったが、その頃はまだ、山谷や西戸山公園の「寄せ場」よろしく、職を失った編集者が市ケ谷駅あたりに集められて、大日本印刷に向かったりした。むろん校正者として専門的な教育など受けたことはないが、雑誌編集の現場を何年かやっていれば、そこそこの校正力は身につくものである。
というわけで、今回、実に久しぶりに純然たる校正者の立場にたって、ある印刷物を点検してみた。その印刷物とは「新潮45」10月号に掲載された小川榮太郎なる「文藝評論家」の「政治は『生きづらさ』という主観を救えない」と題された文章である。
最初にざっと目を通して全体の意味をつかもうとするのだが、内容の酷さに吐気を催したのは置いたとしても、文章としてどうもすんなりと頭に入ってこない。それは大上段に構えたあまりに古風で「文学的」な文体によるのかもしれないが、どうやらそうでもなさそうだ。
まず気づくのは、「性的嗜好」と「性的指向」とを取り違えている、あるいはわざと置き換えているとしか考えられないことだ。
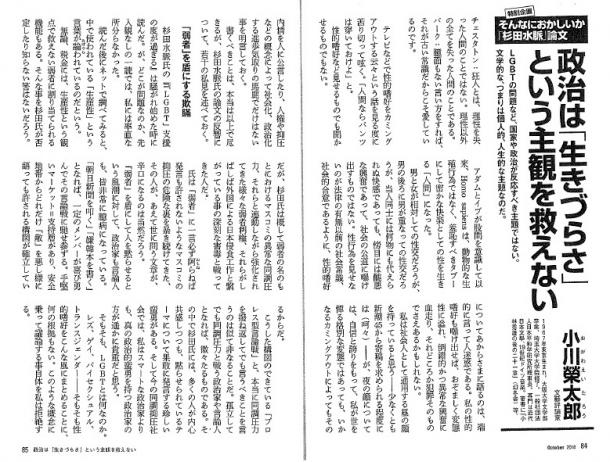 「新潮45」に掲載された小川榮太郎氏の記事「政治は『生きづらさ』という主観を救えない」
「新潮45」に掲載された小川榮太郎氏の記事「政治は『生きづらさ』という主観を救えない」それとも、もしかすると作者は、LGBTに関して巷で耳にした「セーテキシコー」という音を「性的嗜好」と早合点してしまったのか。いやまさか、本人曰く「少なくとも新潮45から寄稿を求められる程度には(呵々)」通用する「文藝評論家」なのだから、そんなことは……と思いつつ本文を仔細に読み進めるうちに、「おや、待てよ」と首を捻ることになった。
まずP84の下段、「性的嗜好についてあからさまに語るのは、端的に言って人迷惑である」という文章に引っかかった。
「人迷惑」? こんな言葉はあったかしら。これはひょっとしたら「傍迷惑」と書きたかったのだろうか。
まあそれはどちらかと言えば些細なことかもしれないが、P86に至っては頭を抱えてしまった。
上段に出てくる「インテリという名前の精神薄弱児たちに言論と政治を乗っ取られた挙句」とマルクス主義者を最大に貶めているつもりの文言。ご承知の通り、いまは「精神薄弱」という言葉はメディアではまず使わない。1997年の障害者雇用促進法の改正もあって、公的な文書でもすべて「知的障害」に置き換えられているはずだ。ここはどんな校正者でも真っ先に「エンピツ」で疑問点を入れてくる箇所だろう。仮にそう直したとしよう。すると「インテリという名前の知的障害児」となって語義矛盾をきたす。だいたい「インテリ」という曖昧で雑な言葉遣いが蔑称として評論の文章に出てくること自体、噴飯ものなのだが。
さらに決定的なのは
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください