『最初の悪い男』、『マザリング・サンデー』、『超越と実存』、『編集者 漱石』……
2018年12月14日
*書評「神保町の匠」の評者による、2018年の「わがベスト3」を紹介します(計4回シリーズ)。
井上威朗(編集者)
殺伐とした言葉ばかりがデジタルで目立っていく流れは今年も変わりませんでした。そんな年の瀬、スマホに表示されたムカつく書き込みと戦うのも大事かもしれませんが、満員電車で乗り合わせた泣いてる赤ちゃんに変顔してみせるのもいいかもしれません。こんな心持ちになれる3冊を選びました。
村瀬秀信『止めたバットでツーベース――村瀬秀信 野球短編自撰集』(双葉社)
スポーツをネット上のテキストで楽しむ人は、私も含めて匿名掲示板やまとめサイトに行ってしまいがちですが、丹念にさまざまな現場の声を拾ってくれる本著者のようなプロのライターも、ネット媒体でいい仕事を重ねてくれています。でもそれを書籍にまとめる企画は私の職場では高確率でボツになりそうです。そんなご時世、書き手の誠実さと恥じらいが魅力たっぷりの構成と装丁に結実した本書は、ついレジに持っていかされました。情熱が伝わる本作りです。いいなあ。
スティーブ・モリヤマ『その「日本人論」に異議あり!――大変革時代の日本人像を求めて』(芸術新聞社)
ネットで目立つ粗雑な議論の典型が「グローバル化が進む世界において、日本人は○○だ」的な話。これに一つ一つ逆張りしてくれるのが、まさにグローバル経済のトップで長年戦っている本著者。多彩な引き出しから落ち着いて「本質」を考えるための道筋を示してくれます。そこに上から目線がないのもありがたい。比較文化論というある種「出尽くした」ジャンルでもまだまだ好著が出現するのがうれしいです。
ミランダ・ジュライ、岸本佐知子訳『最初の悪い男』(新潮社)
ダメな現実と折り合いをつけるには妄想しかない。妄想の力をつけていけば、どんどん生活もスムーズに……。私自身そうありたいと願ってしまう『阿Q正伝』の続編のような生活を送る中年女性が、巨乳で足の臭い20歳女と強制同居させられ、あらゆる下品なトラブルに見舞われる話。と思ったら妄想と現実のハルマゲドンを怒涛の展開で読ませられ、最後は大感動に導かれます。
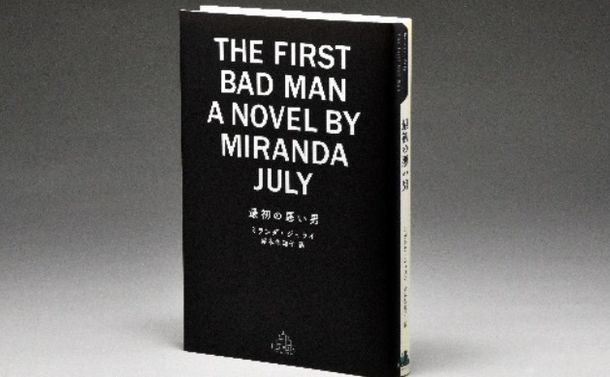 ミランダ・ジュライ、岸本佐知子訳『最初の悪い男』(新潮社)
ミランダ・ジュライ、岸本佐知子訳『最初の悪い男』(新潮社)小林章夫(帝京大学教授)
グレアム・スウィフト、真野泰訳『マザリング・サンデー』(新潮クレスト・ブックス)は、イギリス小説のもっともすぐれた特質を見事な翻訳で日本の読者に伝えるもので、細部の描写にまで行き届いた文章によって心をとらえて離さない。お屋敷に勤めるメイドに与えられる年に一度の里帰りの日に一体どのようなことが起きたのかを丁寧にしかも大胆な筆致で描き出し、やがて年を経て有名な小説家となった彼女の回想を通して若き頃のこの体験がどのような意味を持つかが語られる。本年一番の作品。
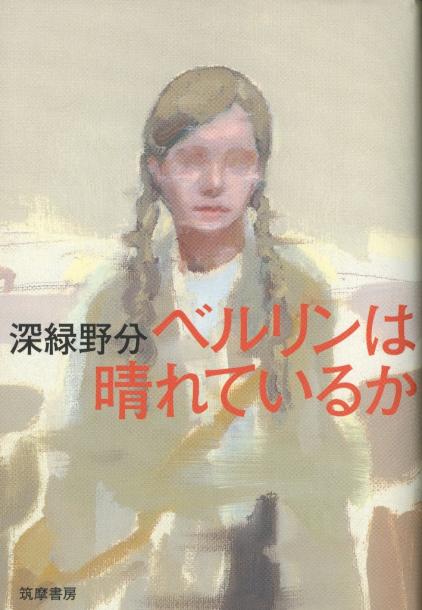 深緑野分『ベルリンは晴れているか』(筑摩書房)
深緑野分『ベルリンは晴れているか』(筑摩書房)深緑野分『ベルリンは晴れているか』(筑摩書房)は近来まれにみるミステリ。しかも日本人の手になるものとしてこれほど読みごたえのある作品はなかった。この著者、次はどのような作品を書くのか、今からワクワクしている。
[書評]『ベルリンは晴れているか』
佐藤美奈子(編集者・批評家)
南直哉『超越と実存――「無常」をめぐる仏教史』(新潮社)
「世の思想には仏教と仏教以外しかない」。この刺激的で、一見独善的とも思える冒頭近くの一文は、読了後、私の抱える問題と深く接続した。「私の」と書いたが、何も個人的事情との関連を披瀝したくて本書を挙げるわけではない。自らについて問おうとする者、生きる上で足元に不安を抱える個人すべてにとって、本書が投げかける問いは浸透するだろう、と思えるからだ。GAFAをはじめグローバル資本の流入と席捲によって、人や物の在り方、社会における個人の役割が激しく変化しつつある今、仏教最大の特質である「無常」という考え方が目を開かせてくれる度合いは計り知れない、と感じさせてくれる一冊だ。所属や帰属ではなく行為・行動がその人を規定する、「悟り」という超越的な理念・観念に意味を求めるのではなく常に動き続けるベクトルとして在ることが生きるということなのだ(と断定した先から、すでに「無常」からは離れるのですが……)。フリーランスで生活する身にとって痛く、重く響く記述に出会うと同時に希望が与えられた一書。著者は永平寺で約20年修行を重ねた僧侶。
熊野純彦『本居宣長』(作品社)
哲学者・倫理学者の著者が本居宣長と正面から対峙した大冊。外篇では、近代以降の日本に生まれた宣長をめぐる言説をつぶさに検討することで、ひとつの精神史を編み上げる。内篇では宣長の生涯と作品を丹念に論じ、とくに「古事記傳」の細部を追跡することで宣長「大人(たいじん)」の思考の襞を読み解いている。「古事記」をひたすらに読んだ宣長、その宣長を読んできた膨大な人々、さらにそれらの人々とともに新たに宣長を読み直そうとする著者。「読む」ことのとてつもない創造性に、今さらのように気づかされ、驚き、打たれた。
長谷川郁夫『編集者 漱石』(新潮社)
日本近代の「大人」である夏目漱石を「編集者」として読み解くとは。正岡子規から受け継ぎ漱石に働いていた編集機能(エディターシップ)に注目することで、こんなにも新鮮で豊かな世界が展開されるとは。漱石は語り尽くされていると感じている人たちにこそ、本書を勧めたい。漱石が文学を通して追究した「新たな可能性の途」が血肉化されるからだ。
[書評]『編集者 漱石』
ほかに、鷲見洋一『一八世紀 近代の臨界――ディドロとモーツァルト』(ぷねうま舎)は、「人文科学の危機」を背景に加えた深い洞察と、思いがけない発見に満ちた美しすぎる一冊。
松澤隆(編集者)
長谷川郁夫『編集者 漱石』(新潮社)
感銘。子規との相互の影響は誰でも論じる。だが子規の(ときに過剰な)編集者魂を、漱石が選択的に継承し、やがて自らの創作と、朝日新聞文藝欄の充実のため奮闘する過程を、かくも例証豊かに描破した本はあったろうか。しかも(編集の先達)漱石への敬愛は滲んでも溺愛はない。分析は鋭利。留学について吉田健一の辛口論評を引く呼吸なども絶品で、やはりあの名評伝の著述者。漱石関連書籍で涙腺が緩んだことはなかったが本書は別。泣けた。
宇野重規『未来をはじめる――「人と一緒にいること」の政治学』(東京大学出版会)
畏敬。私立女子校生を前に、政治の役割を説いた名講義。象徴的なのは〈悲観的なことを言う方が知的であるように見えるかもしれません〉という逆説的な矜持。つまり培った深い知見を、楽しく考えてほしいと示す意欲。それを分かりやすく伝えるゆき届いた行文と構成。聞き手の反応・無反応を挿入した(編集者の)工夫も奏功。
[書評]『未来をはじめる』
山川徹『カルピスをつくった男 三島海雲』(小学館)
脱帽。日本初の乳酸菌飲料は貧しい真宗寺院出身者が製品化した。その生涯を辿るノンフィクション。明治期の辛苦、大正期の起業、敗戦後の再建までページを繰る手は止まない。健在者への直接取材も充実。ヒット商品ゆえの戦争との関わり、家族との距離も活写。最後に明かされる著者本人のモンゴル体験が見事「発酵」した力作。
[書評]『カルピスをつくった男 三島海雲』
ほかに、安藤礼二『大拙』(講談社)。前著『折口信夫』(同上)同様、情念に流れない澄明な思想地図。いわば「知の等高線」を描画する手際に、前著以上に興奮。本欄の規定外かも知れないが、國分功一郎『100分de名著 スピノザ「エチカ」』(NHK出版)も挙げたい。〈思考のOSの入れ替え〉という卓抜な比喩で導く哲学入門、本書自身で名著。特筆すべきは、片山杜秀著作群。『ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる』(文春新書)は、既刊書でほぼ弁別されていた「思想/音楽」という著者の二つの活動分野が合体、共鳴する好著。時代の終幕に向けた『平成精神史――天皇・災害・ナショナリズム』(幻冬舎新書)は、〈平成〉の意義とその〈未完〉の意味を、昭和以前の古層から剔抉し浄化し、著者らしく自在に冷熱を切り替えて論じる快著。また、佐藤優との20時間に及ぶ対談『平成史』(小学館)は、双方の情報収集力・整理力・表現力が織り成す怪著(構成担当は上記『カルピス……』の著者)。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください